それら小さな植物プランクトンを食べて生きているのが、やはり小さな動物プランクトンです。動物プランクトンには実に多くの種類がありますが、その代表といえるのがエビやカニなどと同じ甲殻類の仲間であるオキアミです。南の海に春が訪れて、海水が滞りやすい氷山の周りの水の色が黄緑色に染まると、今度はそれを赤黒い帯が浸食しはじめます。オキアミのメスは一匹で何万個もの卵を産むため、爆発的な勢いで増えていきます。氷の海で繰りひろげられるこの緑と赤とのせめぎ合いは、何千万年もの昔からずっとずっと続いてきたに違いありません。そして、これらの無数のちっぽけな生きものたちを求めて、さまざまな種族の動物が白く映える海に集まってきます。クジラもまた、そのような動物の仲間です。
南極の生態系を建物に喩えると、よその海や陸上のそれに比べて階の数はそれほど多くはありません。しかし、いろいろな梁や柱が張りめぐらされた独特の美しさを誇っています。数で圧倒する単細胞の藻類やオキアミたちの土台の上には、アザラシやオットセイの群居するにぎにぎしい部屋、こっけいなパフォーマンスを繰りひろげるペンギンたちの踊り場、奇妙な顔つきをした魚たちのいるアルコーブ、窓に面して海鳥たちが優雅にくつろぐバルコニーなどが並びます。クジラはさしづめ重厚な中央ホールといったところでしょうか。もちろん、それぞれの生態系のビルは寂しくポツンと孤立しているわけではなく、お互いに住民が往来し合い、さまざまなやりとりをしています。ここ南極の海で生みだされた多彩な生命のわざ態は、風や海流、生きものたち自身に運ばれる形で、周囲の海や陸地の自然と結ばれています。赤道に近い低緯度の海へと回遊するクジラは、高緯度の極地方で貯えられたエネルギーを、排泄物や自らの屍という形で運搬する役目を担っています。そしてそれは、海の底へ沈み、深層の流れに乗って、やがて再び氷の海の生きものたちのもとへと還ってくるのです。親は子へ、小さな生きものは大きな生きものへ、死にゆく者も新たな稔りを生むもととなり、生命は決して途絶えることなく続いていきます。惑星の半球をつなぐ生命の長大な鎖と同じ道筋をたどる旅に、彼らクジラが巡礼にも似た性格を与えたとしても不思議はありません。
闇と氷がすべてを閉ざす厳しい季節が明け、赤道地方からの暖かい風が分厚い氷床をいただく大陸の永い眠りを呼び覚ます頃、クジラたちはこの夏の稔りを収獲しに、数千マイルの道のりを経て〈豊饒の海〉へやってきます。クジラたちが毎年決められたように遠く隔たった二つの海域を往復するのは、彼らの理解を超えたところで決められる自然のダイヤグラムに従っているだけにすぎないのかもしれません。しかし、だれが決めたことであれ、彼らにとってこれから四ヵ月ほど続く夏の収獲期が、歓喜に満ちあふれる季節であることに変わりはないのです。だからこそ、次の世代へ生命を受け継ぐために北の海へ還るときと同じように、歌を口ずさみながら、幾多の艱難が待ちかまえる長旅を続けることができるのでした。
しかし……そんなクジラたちのユートピアにも、暗い影が差しはじめていました。それは、クレアのお祖母さんの、そのまたお祖母さんがまだこどもの頃でした。〈豊饒の海〉に突如強大な敵が出現したのです。〈沈まぬ岩〉は本当にいきなりやってきました。それまでにも彼らは、南極を離れた北の海でそれらの仲間を見かけることがありました。〈沈まぬ岩〉の仲間にはたくさん種類があるらしいのですが、どれにも共通しているのは、絶えず不愉快で単調な声で鳴くことと、その行動がきわめて不可解であるということです。それらは岩と同類としか思えないのに、沈むこともなく海面をすべり、中にはクジラたちより速く移動できるものさえありました。やがて、そのうちの一部がクジラ族に対してひどく敵対的であることも判明しました。
最初に南氷洋にやってきた〈沈まぬ岩〉は、主にオットセイやゾウアザラシを餌にしていたようでしたが、ほどなくクジラたちに目をつけはじめました。それらは既存のクジラの天敵とは似ても似つかぬ不可思議な方法で、彼らの息の根を止めて連れ去りました。はじめの頃、白い大陸の周りに散在する島々を根城にしていた〈沈まぬ岩〉は、しばらくするともっと大きな同類を引き連れてきました。その〈沈まぬいわお巌〉は、自らクジラたちに襲いかかることはせず、矛盾したことのようですが、親鳥を待つヒナのように〈岩〉から餌として死んだクジラを与えられていました。それでも大きなクジラの肉を持て余すのか、暖海に住むサメが見たらびっくりするほど大量の肉を食べ残し、その場に捨てていきました。それらはクジラたちと同じく、夏になると彼らを餌食としに南氷洋へ回遊してきて、咀嚼したクジラの血に染まった真っ赤な汗を噴きだしながら氷の海を徘徊し、秋の訪れとともに見知らぬ北の海へ去っていきました。どこにあるのかはわかりませんが、たぶん自分たちの本来の生息地へ帰るのでしょう。そして、翌年にはまた〈豊饒の海〉に姿を現し、まるで〈巌〉同士で競い合うかのようにクジラを殺しまくったのです。
海というところは、生きものたちの住む自然の中では比較的変動が激しいほうで、オキアミや魚の獲れ方にも〝豊作〟の年と〝不作〟の年ではだいぶ差がありました。それでも、クジラたちは幾歳月もの時の流れを耐えしのいできました。しかし、今度襲いかかった嵐のような災厄は、いままで彼らの種族が体験してきたいかなる困難とも性質が異なり、クジラたちはなすすべもなく翻弄されるばかりでした。まず最初に、ナガスクジラ眷属でもいちばん泳ぎの遅いザトウクジラがあっという間に姿を消し、続いてクジラ族の中で最も身体の大きなシロナガスクジラが氷の海の表舞台から退きました。二番目に大きなナガスクジラもその後を追いました。魔の手は小型のイワシクジラや歯を持つ親類のマッコウクジラにまで伸びました。クジラ族すべての者たちの間に動揺が走りましたが、さりとてどうすることもできませんでした。同じ海に暮らすともがらであるアザラシや海鳥、魚たちの間にも、不穏な気配が立ちこめました。シャチたちまでが、正当な獲り分を横取りされて憤りました。壮麗な南氷洋生態系の神殿は、天井が抜け落ち、建物全体がガラガラと音を立てて崩れはじめました。いまや〈豊饒の海〉は〈騒擾の海〉と化しつつあったのです。
豊かな海が激変に見舞われ、たくさんの生きものたちが右往左往する中、生態系の崩壊をなんとか食い止めようと各種族の間で急場しのぎの対策がとられることになりました。すっかり影を失くしたシロナガスなどの大型のクジラたちには、もはや彼らが南極の自然の中でこれまで請け負ってきたつとめを果たすことができません。もともとこどもを少なく産んで時間をかけて育てるタイプだった彼らは、広大な海の中でつがいの相手を見つけることさえままならず、速やかに数を回復しろといわれても無理な相談だったのです。カニクイアザラシやミナミオットセイなどの一族が代役候補として挙がりましたが、やはりいちばん期待されたのはクジラ族の中で最後まで〈沈まぬ岩〉の獲物のリストから外れていたミンククジラ族でした。ヒゲクジラの仲間ではコセミクジラに次いで身体の小さいミンククジラは、融通の効かない大型のクジラたちより多少なりとも適応力に富んでおり、とりあえず生態系の穴埋めができるとすれば彼らをおいてほかにないと思われたのです。もし、それでも海の自然のバランスを保つことができなければ、そのときには七千世代ぶりにメタ・セティにおいでを願って、すべてを委ねる以外にありませんでした。
さて、南半球に住むミンククジラ族の七つある〈大郡〉のそれぞれにいる〈行く末の語り手〉たちは、「〈豊饒の海〉ではこれから数世代の間、大いなるものが小さきものに道を譲り、小さきものが大いなるものに成り代わって〈一なる収獲者〉となる」と予言しました。〈政を司る者〉たちは彼らの言葉を、氷山を囲む海の食卓がシロナガスやナガスなどの大柄な種族から彼ら小柄な種族に明け渡されたことを意味するものと解釈しました。なるほど、大きな種族の歌は滅多に聞かれなくなり、たまに耳にするそのメロディーは哀調に満ちたものでした。群れのリーダーたちは、自分たちの一族が〈豊饒の海〉で繁栄を声高に謳歌する時代が到来したと見てとり、仲間のメスに向かって子孫を増やす仕事にもっと精を出すよう進言しました。曰く、「産めよ、殖えよ、海に満ちよ」
しかし、〈語り手〉たちは、「〈一なる収獲者〉の地位を得る代価は高いものにつくだろう」と付け加えることも忘れませんでした。「メスは一頭のクジラであること以上に〈孕む者〉たらんことを求められる」〈語り手〉は重々しい語り口で告げました。実際、餌をとるのが容易になったミンククジラのメスたちは、望むと望まざるとにかかわらず早熟となり、子孫を残すことにより多くのエネルギーをつぎこむことを余儀なくされました。いちばん歳をとったメスが初産を迎えたのがちょうどクレアと同い歳くらいだったのに対し、クレア自身は九つのときに長子を産みましたし、今の若いメスの中には七歳で早くも出産する者までいます。最近ではまだ乳飲み子を抱えながら妊娠するメスも増え、休む暇もなく育児に明け暮れるようになってきました。こうした急激な変化によって、確かにミンククジラ一族は勢力を広げることになりました。が、その一方で、未熟な母親とその負担の増加は、死産や育たずに死ぬこどもの数を増やすことにもつながり、種族の行く末を憂える大きな種族たちとはまた違う意味で、暗雲が彼らの心の上にも覆いかぶさりました。そこへ追い討ちをかけるように、もっと大きな災難が降りかかってきました。他の大型クジラをのきなみ屠り尽くしてしまった〈沈まぬ岩〉が、ついにその矛先を彼らにも向けはじめたのです。
それはおりしも、かき乱された南極生態系の傷を癒すために、ミンククジラ族が間に合わせの増員を始めた頃でした。今まで大きな種族を専ら獲物に定めてきた〈沈まぬ岩〉が、突然彼らばかりを襲うようになったのです。これほど短期間のうちに、クジラ族の一門を次から次へと殲滅せんとはかる捕食者など、永い南極の歴史上未だかつて存在した試しはありませんでした。大海原を泳ぎまわるクジラたちのずば抜けた遊泳力も、生きものの常識を外れた〈沈まぬ岩〉の執拗さの前では用をなしませんでした。生存のために必要な知恵をすべて所蔵している彼らの伝承の中にも、この未曾有の脅威から逃れるすべは語られていませんでした。もちろん、そんなものがあったなら、大きな種族だってむざむざと潰え去ることはなかったでしょう。たまたま一度追いかけられてからくも難を逃れた者だけは、混み合った浮氷の中に運よく逃げこめれば助かる場合もあることを学びましたが、ほかにこれといって〈岩〉の襲撃を防ぐ有効な手立てはありませんでした。一族の者が年間数千頭あまりも生命を落としたこの期間、彼らミンククジラたちの心に巣くっていた予兆的な恐怖は一挙に現実味を帯び、ふくれあがりました。そうした彼らの恐怖は、同じ南極の海に暮らすすべての生きものたちに伝染しました。何しろ、大型のクジラ族のわずかな生き残りは当面滅亡の危機を脱したのに引き換え、ミンククジラたちは生態系における彼らの役割を代わって引き受ける羽目になったまさにそのとき、新たに〈岩〉の餌食として選ばれてしまったわけですから……。クレアが生まれたのはそんなおりのことでした。
最近は〈沈まぬ巌〉も一つだけが、年に一度七つの〈大郡〉のうちのどれかを脅かすくらいで、消息を断つ者も少なくなったようですが、その代わりこどもに対しても容赦しなくなったという不穏当な話もささやかれました。いつだれが犠牲になるかわからない状況で、子を持つ母親の不安はいやましにも強まりました。〈沈まぬ岩〉の出現は、彼らミンククジラの政治や伝統のありようにも必然的に影響を及ぼさずにはいませんでした。生態系の均衡が崩れたのと同じく、彼らの伝統的な価値観も崩れかけていました。群れのリーダー格であった経験豊かな〈政を司る者〉は、〈岩〉の格好の標的となって生命を落とすことが多かったため、長期間安定した政策を打ち出せる者がいなくなってしまったのです。入れ代わって若くして〈政を司る者〉の座に就いた者は、〈郡〉の仲間たちをむしろこの苦境に慣らすよう努めました。結果として、運命論的なあきらめのムードが次第に一族を支配するようになりました。伝統が彼らにとって信頼のおける羅針盤とならなくなった以上、それも無理からぬことではありましたが。まさに外を向けば南氷洋生態系全体を根底から大きく揺るがす危機、内を向けばその余波としての種族社会の混迷という、かつてない規模の破局の前触れに、〈行く末の語り手〉たちは「あと二、三世代のうちに一族の命運が決することになろう」と予言しました。すなわちそれは存続か滅亡か二つに一つという、誠に容赦のない未来を示すものでした。
不吉な将来を暗示するものはそればかりではありませんでした。〈沈まぬ岩〉の仲間には、クジラの捕食者として君臨するもの以外にもこの〈豊饒の海〉へやってくるものがありました。それらのうちのあるものはクジラに対抗する〝収獲者〟でした。それも、実際には〝収獲者〟というより〝収奪者〟といったほうが当たっていました。それらは南氷洋へオキアミや魚を獲りにやってくるのですが、そのやり口はクジラたちの直接の敵である〈クジラ食の岩〉とかなり似ていて、コオリウオやソコダラの仲間などで大きな哺乳動物の一門と同じ運命をたどった種族もあります。子孫を増やすことにかけてはクジラたちよりはるかに秀でた生きものでさえそうなのですから、彼らが不安を一層かきたてられるのも無理はありません。たとえ小さな生命たちが滅びの歌を歌うところまでいかなくとも、クジラと〝食卓を囲む者〟たちは戸惑いの表情を隠せませんでした。なぜといって、永い歳月を通じて、収獲の時期や海域、餌の種類などによってお互いの分け前を決めてきたところに、いきなり強欲な新参者が割りこんできたのですから。
また、別の〈沈まぬ岩〉の仲間は、あのたくましいコウテイペンギンのように白い氷の大陸の上に住み着きだしたらしく、北の海と大陸との間を定期的に行きかうようになりました。それらがどのようにして厳しい冬を越しているのか、ペンギンやアザラシ、あるいはコケやダニでも餌にしているのか、クジラたちの中で直接目にした者はだれもいません。あるときには、海際に面したアデリーペンギンの集団営巣地が島ごと消滅したとの噂がのぼったこともあります。ともあれ、それらが頻繁にこの海を渡るようになったのと時を合わせるように、クジラやアザラシ、海鳥たちの間で不吉なできごとが起こりはじめました。わけのわからない病気にかかって死ぬ者が現れ、死産が増え、身体に障害を持つ者がいままでより多く見受けられるようになったのです。オキアミも魚も小さな藻類も、海の水そのものまでが毒気に冒されているようでした。〈行く末の語り手〉たちは、不当な死をもたらす目に見えない災いのもとを〈疫の精霊〉と呼んで怖れました。ある〈学者〉は、〈沈まぬ岩〉の活動している地域のそばにある氷河から夏の一時期に流れ出す融水に、〈精霊〉が運ばれてくるのではないかと予想しました。実際、主に大陸沿岸に点在する〈岩の巣〉の近くでは、海水が変な色に濁ったり、見たこともない岩クズのようなものが沖合いに沈められていることがよくありました。
このように、〈豊饒の海〉ではいま、そこに生きるすべての生きものたちが試練の時を迎えていました。白い大地に、凍える大気に、滔々とうねる海の波に、翳りが差しました。それでも、今年もまた春はやってきました。喜びの季節が訪れました。クジラたちははるかな旅を経て、この豊かな海へと帰ってきたのでした。
リリとジョーイは生まれて半年あまり、ちょうどいちばんやんちゃな年頃を迎えていました。そろそろ〝食欲の夏〟も盛りを過ぎ、おとなたちは北の海への長旅と繁殖という大仕事に備えてせっせと収獲に励んでいました。はじめの頃は、双子の仔クジラもおとなたちのまねをして、小さな咽喉をめいっぱいふくらませてオキアミの群れに突っこんでみたりもしましたが、しょっぱい水をたらふく飲みこんでしまったり、逆にせっかく口の中に入れてもほとんど逃がしてしまったりで、なかなか要領を得ませんでした。
「こうやって下からすくいあげるようにして口に含んだら、舌で海水だけヒゲの間から押し出すのよ」見かねたクレアが二頭の前で実演してみせます。
いまではどうにかおとな並に食べられるようになりましたが(オキアミを一ヵ所に集めるようなより高度な食べ方はできませんけど)、結局こどもたちはまだまだお母さんのおっぱいが恋しいようです。
一方で、二頭は北の暖かい海にいた頃とは違って母親にべったりということはなく、気の合った友達同士でよく追いかけっこや隠れんぼなどをして遊ぶようになりました。多少なりとも社会性のある動物にとって、いわゆる鬼ごっこは最もポピュラーな遊びです。そうやってふざけ合っているうちに、相手の気持ちを汲みとれるようになり、群れ社会に加わったときに仲間との円滑なコミュニケーションをはかれるようになります。また、運動神経や注意力を養うことで、いざというときに危険から身を守る訓練にもなります。親から教わることと合わせて、おとなになるまでに必要なたいていのことを、こどもたちは遊びを通じて身につけるわけです。ですから、小さいうちにのびのびと遊ぶということは、クジラに限らず多くの動物たちにとって、生きていくうえでたいへん真剣な意味合いを帯びるのです。動物たちの中でもとりわけ遊び好きで、しかもいちばんの遊び盛りであるクジラのこどもたちともなれば、起きている時間の大半を遊びに費やしているといっても過言ではありません。そして、ほかならぬその遊びたがり屋の気質のゆえに、クジラたちは海の生きものたちの間で一目置かれる存在になったといえるでしょう。
「ジョーイ! ジョーイったら!!」
「へへっ、ここまでおいで~だ!」
いま、ジョーイとリリはクレアのそばを離れて、二頭だけで〈サメごっこ〉(クジラの子たちの間で流行っている鬼ごっこのことです。複数の鬼役が協同して獲物役の子を追いかけるときは、〈シャチごっこ〉という呼び名に変わります)に興じていました。双子の兄妹は同じ年頃のこどもたちの間でもひときわ活発で、二頭してこっそり遠出してお目玉をくらうこともしばしばでした。こども時代やはり腕白娘だったクレアの血を引いたせいもあるでしょうが、その母親があまりに子煩悩すぎて窮屈に感じていた部分もあったかもしれません。ともあれ、兄妹は大の仲良しで、しょっちゅうケンカもしましたけど、よその友鯨とよりも二頭だけで遊ぶことのほうが多かったくらいです。この日もみんなが遊び飽きて帰ってしまったので、残って〈サメごっこ〉の続きをしていたのでした。
南極大陸の周りには、夏でも百万平方マイルもの海氷が張りだしています。これらの海氷は主に海水が凍ってできたものですが、中には絶えず成長し続ける大陸の氷床が押し出され、分離して漂いだしたものも含まれます。そうしてできたテーブル状の氷山は、もともと内陸に降る氷雪が固まったものなので、真水から成っています。蓮の葉のように表面が平らな浮氷(パックアイス)が、さまざまな形のモザイク模様を描いて延々と連なっているさまを見ると、温暖な地域に住む生きものならそれだけで全身に震えが走ってしまうところでしょう。ですが、クジラの子たちは、北の大洋のただ中とはがらりと雰囲気の異なる天然のアスレチックコースを前にして、みな大喜びでした。何より、氷山がウヨウヨ漂っている海域は、隠れんぼをするのにもってこいの場所です。リリとジョーイは、あまり遠くへ行ってはいけないとおとなたちに釘を刺されていたにもかかわらず、いい気になっていつまでも遊びに夢中になっていました。
「ほらほら、サメさんこ~ちら!」
「もう! どうして私がサメなのよ!?」
みんなと一緒に遊んでいたとき、ジョーイもリリもサメ役になってはいなかったのですが、最後にサメの番に当たっていた子が〈託児所〉へ帰ってしまったので、ジョーイは独り勝手にリリをサメに決めつけて逃げだしたのです。二頭ともルールの上ではサメ役を引き受ける義務はなかったものの、からかいながらどんどん先へ行ってしまうジョーイを、リリも躍起になって追いかけたため、追う者と追われる者という典型的な鬼ごっこの図式ができあがってしまったのでした。
リリより茶目っ気にあふれるジョーイは、器用にクルッと反転して後方からやってくる双子の妹に向き合いました。
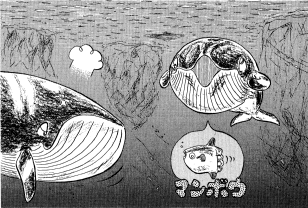 「やあい、そんなのろまなサメなんかいないぞぉ。サメというよりマンボウだな。リリののろま! のろまのマ・ン・ボー! マンボウクジラ!」
「やあい、そんなのろまなサメなんかいないぞぉ。サメというよりマンボウだな。リリののろま! のろまのマ・ン・ボー! マンボウクジラ!」ジョーイは口をすぼめて(ほんの気持ち程度ですが)目を白黒させ、暖海の遠洋を遊泳する、顔が縦にひらべったくて間の抜けたように見える魚のまねをしてみせました。二頭は〈抱擁の海〉にいた頃、海流に身を任せるばかりでほとんど泳ぐ力のないこの魚を見つけては、格好の玩具にしていたのです。兄のこっけいな顔を見て、リリは蛇腹上のお腹をプーッとふくらませました。
「ジョーイの意地悪! 意地悪の、インチキ! インチキの……」
リリは言い返そうとしましたが、ジョーイは聞く耳を持たずにまた身をひるがえらせて逃げていきました。いくら悪口を浴びせても、兄のほうは一向にこたえた様子がありません。まったくジョーイったらずるいんだから。なんとかとっ捕まえて尻尾で一発ひっぱたいてやらないと気がすまないわ! でも……彼女はそこで思いとどまりました。こういうときはかっかせずに、落ち着いて策を練ったほうがよさそうです。母はよく、「どんなときにも、海の波のように自然体でふるまうことね。気が昂ぶっているときは嵐の海をイメージして。自分の心の状態がわかるように。それでもし、気を鎮めたいと思ったら、穏やかな月夜の入江を思い浮かべるといいわ」と説いたものでした。重い体重をほとんど意識させない海中暮らしをしているクジラにとって、波の気分になるのは造作もないことでした。水面よりちょっと下の位置で円を描きながら回転している水の塊に同調して身体を揺らしていると、自分自身と周りの海水との境がなくなって、まるで水の精にでもなったかのような気になります。リリは波のリズムに逆らわずに身を浮かべながら、遠ざかっていくジョーイを追おうともせず、頭を傾けて片目で彼の行方を見やりました。兄の後ろ姿は水の中で次第にかすんでいきましたが、派手に水をかき回して遁走する音は聞き逃しようがありません。
ジョーイが手前にある中くらいの大きさの氷山の向こう側に姿を消したところで、リリは一呼吸するとその場を離れ、緩やかなモーションで泳ぎだしました。潮の流れにそよぐケルプのような身のこなしで、浮氷の群れを迂回しながら、彼女はジョーイがとった進路より深いところを等速度で進みました。流線型の身体を規則正しくゆっくり波打たせて音を立てずに進む泳ぎ方は、父親のレックスに教わったものでした。クジラのオスのほとんどが育児を母親任せにし、こどもをかまったりはしないのに、レックスは幼いクジラに対して心を砕くことをいとわない珍しいオスでした。クレアがいないときでも彼はたびたび双子のもとを訪れて遊び相手になってやり、まめな父親ぶりを発揮しました。クジラの子にとっては真の家族と呼べるのは母親だけであり、あとのおとなはみんなひっくるめておじさん、おばさんでしたが、レックスはおじさんのうちでも別格でした。
そのレックス直伝の〝忍び泳ぎ〟は、イルカたちからみればとても音を忍ばせているとはいえないしろものでしたが、ジョーイをあざむくには十分だったようです。リリはさっきまでサメといわれて憤っていたのに、青く透き通った氷の壁を目にしつつ、獲物をねらうサメのような気分を味わっていました。ギョロ目が上を向いた受け口の魚が目の前をついと横切りました。何も知らないのんきな獲物は、氷壁の裏にじっと貼りついています。
氷山の裏に隠れていたジョーイは、妹の怒鳴り声が聞こえなくなったため、いったいどうしたんだろうと隠れ場所から顔をのぞかせました。リリの姿が見当たらないためキョトンとしていると、いきなり背後から侮りがたいマンボウザメが飛びだしてきました。
「タァッチ!」不当な役どころを押しつけられた恨みとばかり、リリはジョーイの頭を胸ビレでしたたかぶちました。おかげで彼はめまいがして仰向けにひっくり返りました。
「いってえ! そんな思い切りぶたなくたっていいじゃんかよう!」自分がズルをしたことは棚に上げて、ジョーイはリリに抗議しました。
「サメは怒らすと恐いのよ」リリは平然と言ってのけました。憂さを晴らしてすっかり上機嫌です。
「さ、今度はあんたの番よ。ちゃんとルールどおりにおやんなさい」
ジョーイはしぶしぶうなずくと、頭を下に向けました。
「わかってるよ! ひとおつ、一本ウミヘビ尾っぽ。ふたあつ、二本のカモメのあんよ。三本足はサンキャクウオ、四本ウミガメ平泳ぎ──」
ジョーイは逆さまの姿勢で目をつぶって数え歌を唱えはじめました。クジラの子が隠れんぼをするときに大声で数を数えるのは、音で相手の隠れ場所を突きとめられないようにするためです。空気中の四倍の速さで海底に届き、跳ね返ってくる鬼の数え歌が聞こえるうちは、ほかの子たちはまだ逃げ場を探す余裕があるというわけです。
「いつっつ、星型ヒトデのあんよ。むっつは……ええっと~、なんだっけ? 忘れちった・・。いいや! ななつがなくて、やっつはイカさん、ウミグモさん。ここのつも飛ばして、とおはカニ、エビ、タコの足! っと」
しっかり数をごまかして(おまけに歌詞も間違って)歌い終えたジョーイは、さっそくリリがどっちの方角に向かったんだろうとちっちゃな目玉をキョロキョロと動かしました。おとなになれば、歌いながらでも逃げるときの水音から判断してちゃんと相手の居場所の見当をつけることができるようになるのですが、いまの彼にはまだ無理な相談のようです。
「あれえ、どこ行っちゃったんだろ?」
クジラの目は左右別々にものを見ることができますし、身体の側面にちょうど真横に近い向きに付いているので、かなり広い範囲を視野に収めることができます。ですから、ちょっと身体を傾けるだけで、三六〇度四方を見渡すことができるのです。もっとよく目を凝らして見たいときは、対象物が身体の真横にくるよう向きを変えます。片目ですと距離まではわかりませんが、それは〝耳で聴て〟測ればよいことです。クジラの視力は動物たちの中ではあまり鋭いとはいえないほうですが、遠くまで見通しのきかない水中ではそれで十分なのです。
いま、ジョーイの目に入ってくるのは、氷の塊がいくつか水面からぶら下がっている光景ばかりでした。彼は、やや小さめの氷山が混み合っている付近にリリが紛れこんでいるものと目星をつけました。リリよりもっと下手でしたけど、ジョーイも彼女のまねをして、極力水音を立てないようにゆっくり泳ぎ進みました。彼は氷と氷に挟まれた水路を一つ一つ調べていきましたが、リリの姿はありません。入り組んだ水路の奥までのぞいてみましたが、彼女がいた気配すら感じられませんでした。
「ここじゃなかったのかな……」
だれもいない氷の隘路は、コバルトの光線が交錯して神秘的な雰囲気を醸しだしています。氷壁にはところどころ辛抱強い波のうねりによってうがたれた穴がぽっかりと口を開き、いちばん奥の濃い紫から手前の純白に至るグラデーションが、言葉に尽くせぬ美しさを誇示していました。その恐いほどの美しさの裏側には、何か邪悪なものが潜んでいるような気もしてきます。どこまで行ってもリリが姿をあらわさないため、ジョーイはいささか心細くなってきました。おまけに折悪しく、以前レックスに話してもらったおそろしい話が頭に思い浮かびました。
それは、氷に閉じこめられて全滅した〈小郡〉の話で、レックス自身が小さい時分にも実際にそのような事件があったと彼は言っていました。その〈郡〉は、ほんのちょっぴり〈豊饒の海〉を発つのが遅すぎ、またその年の冬の歩みがほんのちょっぴり急ぎ足だったために、北の海へ抜ける狭い海峡を通過しようとした彼らは、一面を埋めつくすパックアイスを前に立往生せざるをえなかったのです。彼らが氷の罠に気づいて引き返そうとしたときには、後ろにも浮氷の群れが押し寄せていました。まだ凍りついていない水面は次第次第に狭まっていき、しまいには氷の隙間からやっと鼻先だけ出してどうにか息が継げるくらいになってしまいました。そしてとうとう、一群のクジラたちは全員氷の下で溺れ死んでしまったのです。実はこの悲劇が起こったのは、〈行く末の語り手〉が冬の早めの到来を予期していたにもかかわらず、〈政を司る者〉がそれに耳を貸さず、メスたちにもっと食事をとらせようと遅くまで居残っていたためでした。そのためこの逸話には、〈語り手〉の的確な予言と、それを〈政を司る者〉がいかに正しく読み取って迅速かつ適切な判断を下せるかどうかに、〈郡〉の存亡がかかっているのだという、一つの教訓が含まれていました。話し終わったあと、レックスはジョーイたちに言いました。
「だけど、ぼくはこの話が訓えてるのはそれだけじゃないと思うんだな。この海の中でいちばん力強いもの、そしてぼくらにとって本当に恐いものは何かといえば、シャチでも〈岩〉でもなくて、実はほかでもないぼくらをとりまく海そのものだってことさ。なぜって、海が本気を出したら、どんなに強い生きものだってひとひねりにされちゃうんだもの、この話にあるみたいに。海洋一の猛者といわれるシャチだって、そしてあの頑丈な〈沈まぬ岩〉でさえ。ぼくらはいつでも食いつ食われつしている小さなものたちに比べれば、まだ安穏として暮らしていられる。でも、ちょっと油断すれば、いつもは穏やかな顔をしている海が突然牙を剥きだして襲いかかってくるんだ。そして、ぼくらがそこで生きている以上、その牙から逃れるすべはない。僕らは日々何気なくそこを泳ぎ、そこで食べ、眠り、そうして一生を送るわけだが、死ぬのもやっぱり海の中なんだからね……」
いま、ジョーイの周りには青白い氷の壁がのしかかるようにそびえていました。それらの威圧的な壁はいまにも寄り集まって自分を取り囲み、溺れさせてやろうと企んでいるかに見えました。厚い皮下脂肪にくるまれて寒さを感じないはずなのに、ジョーイはブルッと身震いしました。彼はにわかに息苦しさを覚えて、あわてて水面に浮上しました。
勢い余ってジョーイは身体の半分以上も水の上に伸びあがりました。秋口に入りかかっているとはいえ、太陽は惜しみなく光を降り注いでいました。その陽光を受けて、氷山のゴツゴツした白い肌がキラキラと輝きます。水面下に比べて、海の上に出ている部分はなんとも貧弱で、不気味なまでの神秘的な印象は薄れていました。これなら閉じこめられて窒息する心配はなさそうです。新鮮な空気を深々と吸いこむと、ジョーイはどうにか気分が落ち着いてきました。この春離乳したばかりの若いカニクイアザラシが一頭、波間から突如頭をもたげた仔クジラに驚いて、氷上からボチャンと水の中へ飛びこみました。彼は海面上に上半身を表したままの姿勢で、尻尾を軸に回転しながら周囲を見回しました。リリの呼吸のリズムは心得ていますから、息をしに上がってくればわかるはずですが、やっぱり彼女は現れませんでした。もしかしたら、反対側の陸のほうに隠れたか、飽きて兄をほったらかしたまま〈託児所〉へ帰ってしまったのかもしれません。しばらくそうやって見張った末、ジョーイは場所を移ることに決めました。
再び水の中に潜ったとたん、だれかが水を蹴る音が耳に入りました。魚やアザラシよりずっと大きな身体の持ち主のようでした。ジョーイはリリに違いないと確信しました。はは~ん、さてはこっそりこっちの様子をうかがっていたんだな? ぼくがまた潜ったものだから、あわてて逃げだしたんだ……。予想に反して、音はさらに沖合の、残りかすのように小さくなった氷山が散らばっている辺りから聞こえてきました。ジョーイはそれらの氷の間をジグザグの航跡を描きながら泳いでいきました。ふと、三つ、四つ先の狭い水路を何か黒いものがさっと横切るのが見えました。ジョーイはさっきのお返しに彼女をびっくりさせてやろうと、慎重に接近していきました。鼻先をかすめていく透明なビロードのようなクシクラゲの姿も、もう目に映りません。妹が隠れているに違いない、やや大きめの氷山の手前にきて、彼ははたと静止しました。
ここでジョーイは、〝耳で聴る〟術を実践してみようと思いたちました。〝耳で聴る〟とは、一定の方向に向かう性質のあるいくつかの周波数の音を弾丸のように発射して、その音が対象物に当たって跳ね返ってくるのを聞くことにより、音をぶつけた物体の位置や動く速度を測るもので、専門の用語でエコロケーション:反響定位といいます。陸上の動物では、コウモリ類やウミツバメの仲間などが夜に昆虫を捕まえるのに用いる方法ですが、〝耳で聴る〟能力は海の世界でこそ断然本領を発揮します。音は水の中では空気中よりずっと速く、遠くまで進むため、物の姿形や位置を確かめるにはむしろ光よりも都合がよいのです。ただ、目で見るのと異なるのは、視覚の場合はやってくる光の情報を受け止めるだけですが、音の像を得るためにはこちらから音を投げかけてやる必要がある点です。歯を持つ小さなクジラの仲間であるイルカたちなどは、とくにこの能力に優れていて、オキアミ一匹一匹の大きさまで〝聴分け〟がつき、また相手の内部構造や材質すら細かく調べられるそうです。彼らは音のレーダーを使って、浮袋の大きさや脂肪のつき具合などをもとに、ご飯になる種類の魚かどうか判断するわけです。そのようにして、目で見、耳で聞くだけでなく、〝耳で聴る〟能力を獲得したことは、同時にクジラたちの社会で歌や物語による文化を発達させることにもつながりました。彼らの歌には音楽的要素ばかりでなく、〝映像〟的要素も含まれているのです。
単に耳を使って〝聴る〟だけなら赤ん坊にだってできることなのですが、ジョーイがこれから試そうとしているやり方は、より高度なテクニックを必要としました。これもやはりつい先日レックスからじきじきに教わった方法であり、おそらくリリもまだ聞いていないはずでした。その方法とは、いったん対象とは別な物体に絞った音をぶつけ、一回反射した音をさらに利用して目標の位置を探り当てようというものです。いわば音の〝鏡〟を使うわけです。これですと、物陰に隠れていて直接には見ることのできない相手の正体も突きとめることができます。ただ、この〝聴方〟の難しいところは、反射させる角度をうまく調節してやらないと、見当違いの方向に音が飛んでいってしまうということです。
ジョーイは精神を集中し、隣の氷山の壁に向かってさえずりを発しました。こだまは瞬時に返ってきました。相手の居所を知るてがかりとなるのは、投げた音と跳ね返ってきた音との時間差や位相のずれ──光でいうなら色の干渉模様に相当するもの──ですが、それをもとに実際に判断するには生来の勘と経験が頼りです。まず氷そのものからのこだまを聞きとることはジョーイにもできましたが、それに加えてさらに二度反射して散らばり、しかも始めの反射音と混ざっているかすかな音は、どこまで本当に聞こえているのかよくわかりませんでした。それでも、とりあえずリリらしいクジラの影が〝聴えた〟ような気がしたので、彼は氷山の下をくぐりぬけて相手の真下の位置に躍りでました。もし、ジョーイが〝耳で聴る〟能力にもっと熟達していたなら、その影に不審な点があるのを〝聴破れた〟でしょうが……。
確かに、そこにはだれかがいました。しかし、リリほど小さくはありませんでした。
「リリ、見ぃつけ──!!!」