短い夏の間、彼らは〈食堂〉に通いつめ、一日のうちに体重の三%から五%、数百キログラムもの量のオキアミをたいらげます。というのも、夏の四ヵ月の期間を除けば、彼らはほとんど絶食に近い状態に耐えなければならないからです。実際、〈豊饒の海〉へ帰ってきたての頃のクジラは、繁殖と往復の長旅のせいで皮下脂肪がごっそり落ちて、みごとにスリムな体型に変身しています。クレアなどは二頭の子に乳を与えていたものですから、空腹のあまり夢の中でまで〝赤いスープ〟がちらつくほどでした。オキアミのいる海域に入ったら、とくに彼らが群がっている部分を見つけて、必要に応じて〝スープ〟の濃さを適度な加減に調節し、一気に咽喉へと流しこみます。噛みしめて味わったりしている余裕なんてありません。食物を手に入れるのにたいして時間も労力も割かないクジラたちは、他の動物たちと比べるとずいぶん楽をしているように思われますが、たくさん食べて巨体を維持するためには仕方のないことなのです。
クレアたちが使用している〈食堂〉は、ロス海の陸寄り、オキアミが大量に湧きやすい、岸辺に接した棚氷と浮氷群との境界近くにありました。ロス海は、南極大陸を半島のある東側と円盤状の西側との二つの部分に分かつ大きな切れこみの一方にあたる内海で、真冬ともなれば半分以上の面積が氷のタイルでびっしりと敷きつめられてしまいます。それでも、その辺りの海は群れの中でもいちばん栄養をつける必要がある妊娠メスたちの指定席になっていました。メスよりも身体の小さいオスは、それより緯度の低い海域で遠慮がちに控えていました。そのさらに北では、まだ乳飲み子を抱えるメスが哺乳に専念するのが通例でした。しかし、この〈食堂〉の割り振りも、繁殖サイクルの変化に伴って様変わりし、翌年の出産のために早く現在の子を手放して〈大食堂〉へ行きたがる母親が多くなり、夏の盛りを迎える頃には大半のメスが高緯度側に押し寄せました。
いずれにしろ、冷たい海を好むオキアミは緯度の高いほうに多くいますから、母親たちはときどき自分の子を〈託児所〉に預けて食事に出かけました。〈託児所〉では、養育の当番に当たっている数頭のメスが(たいてい老齢で子育て業を引退したり、一時的に繁殖を休んでいる者が就くのですが)、親が不在の間こどもたちの面倒を看ていました。母親は留守にする前に、こどもたちに養育係の言うことをよく守るように言いつけていきました。こどもたちも、〈保母〉たちの教えを羽目を外さない程度に聞き分けながら、自分の親が授乳のために戻ってくるのをじっと待ちわびていました。
一食終えて満腹すると、メスたちは休息とこどもとのスキンシップを求めて〈託児所〉へ引き返します。〈食堂〉の営業時間はオキアミたちの活動が活発になる朝夕が中心ですが、日の沈まない夏の南極大陸周辺では必ずしも一定しているわけではなく、おとなたちは三々五々その場を離れて帰途に着きます。その日、クレアが他のメスたちとともに〈託児所〉に戻ってみると、よその子たちはさっそく母親に甘えに泳ぎ寄ってきたのに、いつも真っ先に飛んでくるはずのジョーイとリリの姿は見当たりませんでした。一頭の子が自分の親と勘違いしてクレアのそばに近づいてきましたが、彼女がやさしく声をかけると間違いに気づき、あわてて回れ右しました。周りで他の母親たちが待ちかねていたこどもたちに乳を与えるのを横目で見ながら、クレアは二頭の名を声に出して呼びましたが、返事はありません。どうせあの子たちのことだからまたほっつき泳いでいるんだろうとは思いましたけれど、彼女は念のため〈保母〉のもとを訪ねました。
この日〈保母〉の当番に当たっていたメスは、クレアより若干年上でしたが、血縁が遠かったためか双子のことをよく覚えていないようでした。クレアがその〈保母〉からどうにか聞きだしえたところでは、その日こどもたちは仲良く追いかけっこに興じていたとのことでした。遊びにいった子らはみんな帰ってきたように思う、と彼女は言いました。それ以上その〈保母〉を追及するわけにもいかず、クレアは仕方なく自力で二頭を捜しだすことにしました。
彼女は仲のよい数頭の友鯨に頼みこみ、手分けしてリリとジョーイの行方を捜し求めました。アンの息子、バートの話によれば、二頭とも最初の頃は確かに彼と一緒に〈サメごっこ〉のメンバーに加わっていたとのことです。こういうとき、海の広さがクレアにとっては恨めしく思われました。四方と下方に向かってどこまでも広がる空間のうち、視界に入るのはそのほんの一部にすぎず、そのうえ陸から離れてしまえば道しるべになるものとてないのです。刻々と形を変えながら動いていく流氷などは無論あてにできません。視覚に頼れないとなると、彼女たちクジラに利用できるのは、磁気的な方向感覚と音で描く海底地形図だけです。しかし、それらのおおまかな指標は何千マイルも隔たった海域を往復する回遊コースをたどる際に使われるのみで、こうした非常時にはたいして役に立ちません。だからこそ、クジラ族は音声で仲間の位置を確認し合う独特の方法を編みだしたのです。そして、この能力は、相手が応えてくれないことには使いものにならないのでした。
はじめのうちクレアは、こどもたちが見つかったら、二度とこんなことがないようきつくお仕置きしなくてはと心に決めていましたが、三時間、四時間と捜しまわるうちに、いらだちは不安に席を譲りました。返事がない代わりに、身の毛(クジラたちには鼻先に申しわけ程度に感覚毛が生えているのみで、体毛のほとんどは退化していますが)もよだつ悲鳴が聞こえてこないのは、まだしもの救いでした。ここ数日、この近辺の海でシャチの姿を目撃した者はいません。彼らが周辺の様子を探るために発するカチカチカチッというクリック音は、実際ねめまわされているようでいつ聞いてもいやなものでした。獲物にされるクジラにとっては、そのカチカチ音が自分に集中して向けられたが最期、年貢の納め時と覚悟を決めるほかありません。まだそうとはっきりしたわけではないとはいえ、ジョーイとリリの身に何か不吉なことが起こっていなければよいがと、クレアは気が気ではありませんでした。
「リリーッ! ジョーイッ!」
子を呼ぶ母の呼び声は、海中を逆さまにそびえたつ氷山の峰々にこだまし、その頂きに覆いかぶさるように広がる赤茶けたオキアミの密雲をつき抜けて響きわたりました。その声は、メスたちとは場所が別々になったオスたちの〈食堂〉へも届きました。こどもたちが〈サメごっこ〉をしていたという辺りの海域を中心にクレアが捜索に従事していたとき、オスのミンククジラがすぐ近くで彼女に声をかけました。
「ジョーイとリリのパパはお呼びでないかな?」
「レックス!」
クレアは双子を捜すのに夢中で、レックスが輪郭まではっきりわかるほどそばに寄るまで気づかなかったのです。
「どうしたの? 二頭がまた何か悪戯でもやらかしたのかい?」
「それが、私が食事に行ってる間にいなくなっちゃったまま帰ってこないのよ、二頭とも」彼女は両胸ビレを高くもたげるジェスチャーでいらだちをあらわにしました。
「なるほど……。でも、ぼくがこんな近くまで来てもわからないようじゃ、あの子たちがヒゲの隙間をくぐり抜けていってもきっと見逃しちゃうぞ?」
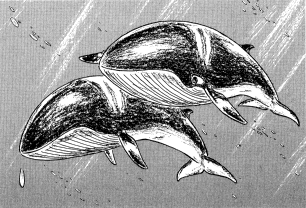 そう言うと、レックスは目を細めてクレアにやさしく微笑みかけました。どんな非常事態でも彼の語り口は穏やかで、何かしら冗談を交えて話すくせがありました。彼女はレックスが怒鳴ったり喚いたりしている場面におよそ居合わせたことがありません。クレアはこどもたちが一大事なのにそんな冗談を言っている場合じゃ……と文句を言いかけましたが、つい気が抜けて口元がほころんでしまいました。クスクス笑いに似た彼の言葉には、聞く者の心を和ませる魔法の力が備わっているみたいです。感情の波がめまぐるしく形を変えて彼女の心をかすめすぎていきます。クレアは泣きそうになるのをこらえ、言葉が出てくるのを待って押し殺した声で言いました。
そう言うと、レックスは目を細めてクレアにやさしく微笑みかけました。どんな非常事態でも彼の語り口は穏やかで、何かしら冗談を交えて話すくせがありました。彼女はレックスが怒鳴ったり喚いたりしている場面におよそ居合わせたことがありません。クレアはこどもたちが一大事なのにそんな冗談を言っている場合じゃ……と文句を言いかけましたが、つい気が抜けて口元がほころんでしまいました。クスクス笑いに似た彼の言葉には、聞く者の心を和ませる魔法の力が備わっているみたいです。感情の波がめまぐるしく形を変えて彼女の心をかすめすぎていきます。クレアは泣きそうになるのをこらえ、言葉が出てくるのを待って押し殺した声で言いました。「さっきからずっと呼びかけているんだけど、返事がないの……」
「何か口を聞けない理由があるのかもしれないよ。ヒゲを生やしたおっかない〝サメ〟に見つからないようにとかさ……。もう少し時間をかけて捜してみよう。ぼくもあっちのほうをあたってみるよ。なに、そう気に病むことはないさ。そのうち白い小山の影からでもひょっこり顔を出すんじゃないかな? 雷が落ちやしないかとビクビクしながらね。何しろ、あの子たちはサメごっこにかけちゃ、幼年時代のぼくも顔負けの名手だからなあ。ぼくがあの子たちにあんまりいろいろ遊びのテクニックを教えすぎたかな? どうもオスってのは、きみたちメスと違って分別がなくっていけない……」そう言ってレックスは、首をかしげるように振りながら泳ぎ去っていきました。
レックスに励まされ、クレアは多少元気を取り戻しました。そうして辺りの海中を見回してみますと、なるほど彼の指摘したとおり、こどもたちのことで頭がいっぱいで、いままで周囲のものがろくに目に入っていなかったことに気づきました。レックスが双子の名を呼んでいるのが聞こえてきます。クレアは気を引きしめるとともに、あらためて彼に感謝しました。もし彼に出会わなかったなら、彼女は前の子を失ったあとで身ごもる気にはなれなかったでしょう。彼ほど気立てのよいオスは、〈大郡〉中見渡してもざらにいるものではありません。二頭は来年、あるいは再来年もペアを組む約束をしていました。ただし、それはいまのこどもたちを無事に育てあげた場合の話ですが。
クレアはこどもたちが遊んでいたとみられる場所を離れ、さらに先の流氷の途絶える付近までヒレを伸ばすことにしました。サイズの小さくなった氷山のかけらは、どっしりと落ち着いた大陸付近のそれと異なり、波に翻弄されいかにも頼りなげです。はじめ一つところで生まれた氷たちは、次第に離れ離れとなって漂いだし、大きさもどんどんしぼみながら、いずれは南氷洋をとりまく暴風圏に呑まれて消えてしまうのです。ときには、ちょっとした島ほどもある巨大な氷山が、ずっと形を保ったまま十年以上も南極圏の海をウロウロしたあげく、海流に押し流されて土と緑に覆われた大陸が垣間見えるあたりまでさ迷いだすこともありますが。
いまクレアは、小粒の氷山が疎らな群れを作っている海域にやってきました。氷山に挟まれた水路を一つ残らずのぞきこみながら、彼女は二頭の名を呼び続けました。おとなのミンククジラといえど、〈食堂〉や〈託児所〉を離れて一頭でいるのはあまり安全とはいえません。クレアは絶えず周囲を警戒して耳をそばだてていましたが、それでも八方に筒抜けになるほどの大声で叫ぶことはやめませんでした。もし近くにシャチがいて、こどもたちを餌食にしたのであれば、自分の身もくれてやれば、親子はその胃袋で再会することもできようというものです。しかし、こどもたちもシャチも、彼女の呼び声に応答してはくれませんでした。自分の分担する捜索範囲はすでに隈なく捜し終わりました。二頭の仔クジラが自力でさらに沖合の海まで遠出をするというのは考えにくいことです。仮にそうだとすれば、彼らの能力では自分たちの居場所すら把握できず、いまごろ途方に暮れて泣いているに違いありません。クレアは、友鯨たちのだれかがすでに見つけて連れ帰ってくれているか、あるいは自分たちで帰り着いていることを祈りながら、いったん引き返すことにしました。万一まだ見つかっていなければ、もっと多くの応援を頼まなくてはならないでしょう。彼女は後ろ髪を引かれる思いでその場をあとにしました。
クレアは知りませんでしたが、いま彼女がいたところこそ、ジョーイが隠れんぼをしていて遭難した現場だったのです。匂いに敏感なサメなどとは違い、クジラの嗅覚はほとんど退化してしまっています。クレアが水の中でもきく鼻をもっていたなら、息子と何者かがついさっきまでそこにいたことも嗅ぎつけられたでしょうが……。
〈託児所〉に戻ってみると、友鯨たちが心配そうな面持ちでクレアの帰りを待っていました。みな安全圏を踏み越えない程度に方々を見てまわり、こどもたちが行きそうな場所はひととおり洗いだしてみたのですが、クレアの祈りも虚しく、二頭がいた形跡一つ見つけることはできませんでした。彼女は胸がつぶれそうな思いがしました。手塩にかけて育ててきた二頭の子をいっぺんに失うなんて。もしかしたら、自分にはもう母としてのつとめを果たすことができなくなってしまったのかもしれない……。
親友たちはクレアの悲嘆をわがことのように分かち合いました。クジラたちは動物の中でもとりわけ仲間同士の結びつきが強いことで知られています。特別に深い母と子の間柄を除けば、彼らはみな同じ群れのメンバー同士が友達と身内との中間の関係にあるようなものです。いわば、〈小郡〉全体が一つの大きな親族をなしているのです。傷ついて溺れかけている同族を見れば、だれもが先を競うように救援に駆けつけます。そして、身体を操る力のない仲間を、下からそっと支えて楽に呼吸ができるようにしてやります。なぜといって、クジラたちはそうせずにはいられないのです。彼らにとって、自分の助けを必要としている者はだれであれか弱いわが子も同然なのでした。クジラたちの種族が長い間に身につけた習性といってしまえばそれまでですが、もしだれかが苦しがっているのを見かけたら、助けたい一心でついついヒレを差し伸べてしまうというのは、それはそれで素晴らしいことかもしれませんね。
広大な海洋に散らばって生活しているクジラたちにとって、積極的に仲間同士の交流を図るのはとても大切なことです。一頭一頭が他のクジラのことに無関心で勝手気ままに暮らしていたら、種族はバラバラになって滅んでしまうでしょう。何しろ、いくら完璧に水中生活に適応しているとはいっても、はるか昔の祖先が水に潜って以来ずっと引きずっている空気呼吸という決定的なハンデのために、水面に浮上する力がなくなってしまえばそれで一巻の終わりなのです。幸い彼らは、溺れかけた者を救うには、呼吸孔が水面上に出るように背中で押し上げてやればいいということがわかっていますから、自力で息が継げるまでに回復する可能性さえあれば、彼らの救護手段は非常に有効です。この方法は、こどもの頃そのようにして母親に呼吸を手伝ってもらい、親になったら今度は立場を入れ代わって自分のこどもを〝背助け〟することで経験を積みます。つまり、ほとんど全員のクジラが熟練したレスキュー隊員の資格があるというわけです。この仲間への気づかい、母と子の強固な愛情、音声を用いたコミュニケーション、そして洗練された歌と語りによる伝承こそは、メタ・セティが海に生きる大いなる獣に与えた特質であり、またメタ・セティはそれらを備えるのにふさわしい生きものとして、クジラを創造したのでしょう。
しかし、クジラ仲間にとっては当たり前のことにすぎないこの美徳は、たびたび〈沈まぬ岩〉の襲撃を受けるようになってから少しずつほころびかけてきました。というのも、いったん〈岩〉につけねらわれたが最後、他のクジラが救出を試みようと試みまいと、奇跡でも起こらない限り助かる見込みはまずないからです。逆に、仲間を救おうとした行為があだとなって、自分まで生命を落とす者も少なくありませんでした。そのため、無駄な努力をしてむやみに危険に身をさらすことはない、仲間同士のつきあいは平常時にだけ当たり障りのない程度にとどめておればいいと考える者も出はじめました。さすがに友鯨をあからさまに見捨てようとする者はいませんでしたが、無我夢中で仲間を助けに走る衝動は、次第にあきらめと死にゆく者へ捧げる挽歌に置き換えられようとしていました。年配のクジラの中には、確かに哀しい気質ではあるが、同胞に対するやさしさはメタ・セティに授かった尊い贈り物であり、一族の維持と繁栄という実利的な面にばかり傾倒して魂を売り渡すべきではないと、最近の兆候を嘆く者もいました。
双子行方不明の報が伝えられたとき、アンたち何頭かのクジラは即座に駆けつけてクレアに胸ビレも尾ビレも貸しましたが、一部の者は救いを求めるクレアに対し、一種のよそよそしさをもって応じました。〈抱擁の海〉では、種族全体に強いストレスがかかっている時代にあって、双子誕生のニュースは微笑ましいできごととして方々に知れ渡りました。しかし、〈小郡〉の中にはクレアのささやかな幸福を快く思わない空気もなくはなかったのです。それでも、生一本な性格のクレアを慕う者は多く、彼女たちは真剣に子らの身を案じました。
アンは息子を愛撫するときのように、胸ビレで彼女の背をそっとたたきながら言いました。「そんなに自分を責めるものではないわ。あの子たちがシャチや〈岩〉に襲われたという証拠だってないんだし。二頭は〈託児所〉の中でも鯨一倍元気がよかったから、きっとどこかであなたが来るのを待っているはずよ。あきらめてはいけないわ」
親友の温かい励ましに、クレアは悲しみのために萎えしぼんでしまった気力を奮いたたせるようにうなずきました。仲間たちは、半分をみなのこどもの面倒を看るために残し、あとの半分は全員一致協力してジョーイとリリの捜索に当たることにしました。おりしも彼女たちが、クレアが先ほど引き返した地点よりさらに沖合に向けて出発しようとしたときでした。
「お母さん!!」
聞き間違いようのないその声の主はリリでした。たった一日足らずの間でしたが、クレアには前にその声を耳にしたのがずいぶん昔のことのように思われました。声のしたほうを振り返ると、そこには娘を脇に従えたレックスの姿がありました。
「リリ!」
「お母さん! お母さん!」
リリは母の懐に飛びこむと、泣きじゃくりながら彼女の下腹に鼻先をグイグイと押しつけました。クレアはいつもより何倍もやさしい声で、なだめるようにリリをなでさすりました。堰を切ったように安堵の波がどっと押し寄せました。しかし、それはほんの束の間しか続きませんでした。クレアはうろたえたように周囲を見回しました。
「ジョーイは……ジョーイはどこ!?」
泣いてばかりいてしゃべれないリリに代わって、レックスが口を開きました。
「二頭は、さっきぼくらがいた小氷山の広がった辺りで〈サメごっこ〉をしていたんだ。ジョーイがサメの番のとき、リリは〈託児所〉に近い場所に隠れていたんだが、彼がいつまでたっても自分を見つけにやってこないもんで、彼女のほうで捜すことにしたんだよ。ぼくらがこの子たちを連れ戻しにきたときも、リリは責任を感じて、ジョーイが見つかるまで声を出すまいと誓っていたんだ。こんなに小さいのに、本当にしっかりした子だよ……」
リリはまだしゃくりあげており、一向に泣きやむ気配がありませんでした。よっぽどこらえていたに違いありません。かわいそうに、さぞつらかったでしょう……。いまのクレアには、彼女を叱る気は微塵も起こりませんでした。
ああ、でも! 彼女はジョーイがリリと一緒でなかったことに胸が張り裂けるような思いがしました。一方では娘が見つかってほっとする気持ちと、他方では息子がこの場にいないことでさらに不安が募り、二つの感情がない交ぜになって、クレアはいまにも気が狂ってしまいそうでした。こんなへんてこな気分にさせられるなら、双子の母親になど金輪際なりたくないと思いました。
クレアはレックスのほうへ祈るような眼差しを向けました。
「それで、ジョーイはどこに……」
「……」
さしものレックスも返す言葉に詰まり、黙って首を横に振るだけでした。