チェロキーは一一歳の若さにしてはたいした口達者で、一度口を開けばいくらでもしゃべっていられるほど話題の種には事欠きませんでした。それらの多くはザトウクジラ族の社会生活にまつわることで、クレアが今まで聞いたこともない興味深いものばかりでした。そばにだれか話しかけてくれる相手がいるということは、一頭きりで捜索行を続けるよりもずっと不安を和らげてくれるものです。その意味で、クレアはチェロキーに同行してもらってつくづくよかったと思いました。それでも、レックスの死やイルカたちの大量殺戮の記憶は頭にこびりついたままなかなか離れようとしませんでした。それらの重苦しい体験の残像がしつこくつきまとい、ジョーイの置かれている状況に思いを馳せたとき、彼女の心に暗い影を落とすのです。
「ラグのやつったら、のろまな上に身だしなみを怠っていたんで、フジツボは付くわ、藻は生えるわ、シラミもわんさかたかって目の周りに切れ目のない輪を描いたほどだ。それこそ十ぺんや二十ぺんのブリーチじゃ落ちやしない。んなもんだから、『あんまり不潔にしてると娘衆に嫌われるぜ』って忠告してやったのさ。するとラグの言うことにゃ、『こいつは新手のアイシャドウさ』ときたもんだ。『かゆくてかゆくて始終目をショボショボさせてるやつが何言ってやがる』とつついてやったら、そこでまた言うことがいいんだな。『いや、これはだな、彼女のハートを蠱惑するためのウインクの練習だ』──」
再び話し相手にめぐり合えて、口をききたくてウズウズしていたチェロキーは、始めのうちクレアの気持ちなどおかまいなしにしゃべりまくっていました。が、しばらくしてようやく、彼女が自分の話を半ばうわの空で聞き流していることに気づきました。彼の話は(声のよさはともかく)おもしろいことで仲間内でも定評があり、前にエスコートしていたメスクジラもふっくらした蛇腹状の下腹を抱えてよく笑ってくれたのに、クレアはさっきから浮かない顔をして心から楽しんでいる様子がなかったのです。彼としては、相手が喜んでくれなければ自分としてもおもしろくありません。そこで話をいったん中断し、暗くよどんだ海底に沈んだままの彼女の気分を、なんとか陽光降り注ぐ海面にまで浮かび上がらせることはできないものかと思案しました。せっかくの冒険の旅なのですから、たとえ行く手に険しい壁が立ちふさがっているとしても、道中は楽しくいきたいものです。
「ねえ、アネさん。ぼくばっかりしゃべっているのにも飽きちゃったし、今度はアネさんのほうで何か話してくれませんか? ご主鯨との思い出話とかも聞きたいな」
「え?」
実は、チェロキーに話をせがまれることをクレアは恐れていたのです。前から彼女は鯨前で話すことが苦手で、専らレックスや他の仲間たちの語る話に耳を傾ける側にいました。おまけに、レックスの最期のことなど思い出したくもありません。
「まあ、別に言いたくなければ無理にとは言わないけどさ」
彼女の思考回路を不幸な事件の記憶からいったん切り離すには、幸せだったときのことを思い起こさせるのが得策だろうとチェロキーは踏んだのでした。それに、彼のほうでも、自他ともに認める旺盛な好奇心が頭をもたげたのと、新たな話のレパートリーを増やす目的もあって、ミンククジラ族の暮らしぶりについてぜひとも知りたいと思ったのです。でも、クレアのためらっている様子を見て、彼は本心を隠してさり気ないふうを装い、尾ビレを高々と水面上に振り上げて深く潜水するフルークアップダイブに入りました。
だめね、私って。せっかく彼が自分のためにわざわざつきあってくれているのに、こんな邪険な態度をとってちゃ……。チェロキーが水面に戻ってくるまでの一五分の間に心を決めたクレアは、仕方なくポツリポツリと言葉を選びながら話しだしました。
「レックスは……私より五つ年上で、〈幼心を擽る者〉って職業だったわ。仕事の内容は彼が勝手にクリエートした部分も多いんだけど。こどもたちにね、いろいろなゲームを教えたり、おもしろい場所へ連れていって見せたりするの。海で生きていくうえで必要な最低限の知識は母親が教えることになっているし、社会生活に関する決まりごとは〈学校〉やおとなになって群れに加わる段階で実地に覚えていくけど、彼はいわばそれ以外の〝不必要なこと〟を担当してたわけ。
「彼が言うにはね、『こどもの身体を用意するのも、丈夫に育つための乳を与えるのも、生きていく知恵を授けるのも、全部メスの役目だ。これじゃあオスの泳ぐ瀬がない。かといって、天性のクリエーターのまねをしようったってできっこないから、せめて余りものの領域を開拓しようと思ってね』
「レックスはメスをとても尊敬していたわ。もちろん、多くのオスたちはメスを敬っていたけど、それは〈郡〉を支える子育て業を営む者としてだったり、メスのほうが政治に長けた個体を輩出していたからだった。彼の場合はそういうんじゃなくて、生命の〈クリエーター〉としてのメスだった。そして、自分はオスなりに〈クリエーター〉になることを目指したのよ。
「『この仕事が〈郡〉にとって重要だとはお世辞にもいえない』って彼は自覚していたし、おとなたちにはこども相手の仕事だってあまり高い評価を受けていなかった。私はとっても意義のあることだと思うんだけど。実際、母親の養育を別のアプローチから補強したり、こどもたちに豊かに生きることの意味を学ばせたり、とても役に立っていたわ。例えばね、いままで全然でたらめに近かった鬼ごっこを、〈シャチごっこ〉と〈サメごっこ〉にわかりやすく整理して基本となるマニュアル作りをしたのは、実は彼だったのよ(簡単そうに思えるけど、完成までに季節が二めぐりするくらいかかったって本鯨が言ってたわ)。それは天敵への対処の仕方をこどもたちの身にしみこませるのに、授業で教えるよりも効果的だったし、そうした集団で遊ぶゲームを通じて、こどもたちが成鯨したときに社会のルールになじみやすい素地を作ったの。もちろん、彼はこどもたちが自分たちで自由にルールを考えて付け加えたり、変更したりできる余地も残した。『そういう遊び心に秀でた子は将来きっと大物になるぞ』って。それで、自分も一緒に遊びの輪に入って研究したり。行ってはいけないところ、してはいけないことはしっかり教えもしたわ。おとながいくら言い聞かせようとしてもこどもに納得させるのは骨が折れるけど、彼は決して短気にならない忍耐強さを示したし、こどもの立場に立つこと、こどもを独立した一鯨格としてちゃんと尊重することの重要性をいつも説いていたわ。こどもたちで作る〈学校〉では、彼は〝休み時間の先生〟っていうあだ名でいちばん慕われていたの。
「レックスは〈郡〉のために一応おとな向けの知的遊戯も考案していたんだけど、〝おとなだまし〟より本業のほうがやっぱりよかったみたい。『結局、ぼくはまだまだ遊び盛りなんだよ』ってね。彼は心の底からこどもが好きだったの。ただおとなとして高みからこどもを見守るってだけじゃなくて、良きにつけ悪しきにつけこどもの持つ性質を愛して、自分もこどものようであろうと努めたわ。彼は波の動きや潮の流れみたいな自然の素材をゲームに活用するのが巧みだったし、雲の形や水の色調、深海の冷たさ、風の感触、そして何より、さまざまな生きものたちの姿や仕草のおもしろさ……生命の素晴らしさに、こどもたちの注意を向けさせたわ。こどもたちの目にじかに触れるようにして、自然が隠し味として持っている抜群のエッセンスを味わわせ、惹きつけさせたわ。宇宙最高の〈クリエーター〉、メタ・セティがお創りになったこの世界が、こんなにも美しく、驚異に満ちあふれているってことに……」
クレアの語り口には始めぎこちなさがありましたが、話しているうちにレックスの姿が瞼の裏にまざまざとよみがえり、生き生きした表情が舞い戻ってきました。まるで話している間だけは生前の彼に会うことができるかのように。
「彼はどの子も選り好みせず面倒を見たわ。母親に頼まれれば二つ返事でお守をしたし。私は三番目の子のときに世話になったの。最初は変わったオスだと思ったけど、メスの評判を得ようとか、そういう下心があるわけじゃなくて、本当にこども好きなんだってことがそのうちわかったの。次の年、四番目の子を回遊中の事故で亡くして、私はひどく落ちこんだ。二年間子育てを休んだんだけど、他のオスはペアリングを申し込みはしても、私が断ったら子育てを放棄したといって非難するだけだったのに、彼はその亡くなった子、シーナのことを覚えていて、一緒に悲しんでくれたわ。一年は私を何気なく気づかってそっとしておいてくれたんだけど、二年目にはこどもをもうけることを勧めたわ、ペアリングじゃなくてよ。私はムキになって、一生こどもを作る気はないって言い張ったんだけど、彼もなかなかどうして辛抱強くてね。
「『大丈夫、君は母親失格なんかじゃないさ。二年も寂しい思いにじっと耐えるほど君はシーナを愛したんだもの。今度は次の子が君に愛される番を待ってるよ。新しい生命をこの世に送りだすってことは、これはとってもたいへん非常にまったくもってとてつもなくムチャクチャにものすごく、素晴らしいことだよ、うん。ぼくだって産めるものなら産みたいもんだ』
「彼が最後の台詞をさもマジメそうに言ったのがおかしくてね。つい、『あなただって産めはしなくとも産ませられなくはないわよ』って言っちゃったの。はじめ彼のほうは戸惑ったけど、他のメスとペアを組む予定もなかったから──本業と私の説得に忙しくて──それで交渉成立ってわけ。口説くほうも口説かれるほうもまったく妙なやり方があったものね。それでジョーイとリリが誕生して、いきなり双子だったから子育ては来年も一年休むことにしたんだけど、ペアは彼と続ける約束だったのよ。それなのに……」
クレアはそれきり黙りこんでうつむいてしまいました。胸ビレをただブラブラと揺らして、傍らにいるチェロキーの姿も目に映らないようです。
「……まさかアネさん、その旦那さんに操を立てるおつもりなんですか? クジラでそんな話なんて聞いたこともないよ」
クレアは言葉を返しませんでしたが、もしジョーイを無事に救いだすことができなければ、今度こそ二度とこどもを作らない決心を固めていました。
ううむ、これはちょっとテーマの選択をマズッたかな……。ぎゅっと口を引き結んで嗚咽をこらえているクレアの横顔を見て、チェロキーはしまったと思いました。どうやら気分を盛りあげるつもりだったのが、逆に悲しい記憶をなおさら呼び覚ましてしまったようです。こうなったらもう、自分が先導して明るい話題に引きこむしかありません。
「うんうん、ぼくもご主鯨のその〈クリエーター〉って職業はなかなか味のある仕事だと思いますよ。身内の自慢じゃないすけど、ザトウクジラは遊戯の開発にかけちゃヒゲクジラ類で右に出る種族はないといわれてますからね。跳躍とか流木運びとか追いかけっこなんかも、高尚な詩作にも劣らない芸術の一ジャンルとしてちゃんと認識されているんですよ。レックスさんは、アネさんたちの一族じゃいわば先駆者だったわけだ。こりゃあ、おちおちしていたらぼくらもミンククジラに追い越されちゃうな、ハハハ」
なんとかして和やかな雰囲気をこしらえようと腐心するチェロキーに、クレアもようやく顔をあげました。
「……レックスもあなたたちザトウクジラ族のことをよく感心していたわ。〈豊饒の海〉では少数派になってしまったけど、あれだけ〈沈まぬ岩〉から打撃を受けてもまだ明るさを失わずにいられるなんてうらやましいってね」
「それは光栄ですね。いや、まったくの話、そいつがぼくらのいちばんの取り柄みたいなもんすから」
自慢屋のチェロキーは、自分の一族のことでも誉められてさらに気をよくしました。そこで、ザトウクジラ族のことをもっとアピールしようと思いたちました。ついでに、機会がなくてなまりがちだった自慢の咽喉も披露して、クレアを慰められれば一石二鳥というものです。
「それじゃあ一つ、ザトウクジラ一族のお家芸にして至高の芸術、さらにぼく自身の天職でもある〝歌〟についてご教授しましょう。ええ、オホン、私どもザトウクジラ族の歌唱の優れた芸術性に関しては、七つの海にあまねく知れ渡っているところであり、海洋音楽における最高傑作の一つと数えられていることは、すでにご承知のとおりであります。海に住まう諸生物種族のみなさんに、私どもの歌を耳にして甘美な陶酔の一時を過ごしていただくのは、その道を極める者としてやぶさかではなく、引きこもらぬ称賛の声を浴びることもまた、秀でた才能に対する正当な対価として率直に受け止めるものであります。がしかし、本来当然のことなんだけど、この歌は私ども一族の間で社交的儀礼として交わされるものであります。ええ、そいでもって、そもそもこの歌の起こりはと申しますと、こいつは私どもの種族が他のナガスクジラ眷属と分岐しちゃったころから、すでにぼくらに備わっていた一族を特徴付ける能力だったのでありましたんだな……ありゃりゃ? まあいいか。ぼくは長たらしい朗読より軽めの短い詩歌のほうが専門なもんだからね」
いったん格調高ぶって語り始めたものの、すぐにいつもの砕けた調子に戻ってしまったので、チェロキーは言い訳をしてそのまま先を続けました。
「歌を歌うこと自体は、アネさん方をはじめクジラ族一般に備わっている能力だけど、とりわけぼくらがそれを高度な芸術の域にまで押し上げたのにはわけがある。知ってのとおり、ぼくらはどちらかというと岸に近い浅瀬を好む。とくに、コンテストの時期にあたる冬の〈抱擁の海〉は陸際だ。つまり、海面から海底までが反射音のあまり拡散しない適度な深さだから、こいつを天然の音響装置として利用しないヒレはない。そういうわけもあって、長い世代交代を通じて歌は洗練され、磨きがかけられていった。そのうち方々の〈郡〉ごとに流派ができて、独自に歌を発達させていったんだ。
「歌はそれぞれ楽章、節、小節から構成されている。一曲が大体六分から二〇分くらい、繰り返しのフレーズがあったり、結構ややこしいんだぜ。いまじゃ、オスはだれでも年頃になったら歌のてほどきを受けることになってるよ。といっても、やっぱり音楽的才能はだれもが持っているわけじゃないんだな。さらに、歌には古典音楽から最新の流行歌までいろいろとレパートリーがあって、恋歌専門のやつもいれば、大漁節が得意なのもいる。なかでも、〈聖歌鯨〉と呼ばれる歌の天才が〈大郡〉に一頭くらいずついて、彼らは〈政を司る者〉に次いで重要な地位にあるんだ。ぼくらの歌には遊びから政に至るまでのさまざまな要素がこめられているのさ。ぼくはまだ年齢的になれないんだけど、ね……」
言葉を濁したところをみると、待望の新鯨もそこまで自信過剰にはなれないのでしょう。〈聖歌鯨〉の呼称を得るには相当狭き門をくぐらなければならないようです。ザトウクジラのオスは派手好みなのだろうくらいに思っていたクレアは、歌一つとっても一筋縄ではいかないことを知って感心しました。なにしろ、彼女がまともに知っているのは子守歌と数え歌くらいのものでしたから。
「へえ、ずいぶんたいへんなのねえ。それで、歌自体はどういうきっかけで歌うの? やっぱりペアリングのときが中心なのかしら?」
「まあそれもあるけどね。確かに、メスがオスを選ぶ際の重要なポイントだし、オス同士でも互いの評価基準になるとはいえるよ。ぼくみたいに必ずしもうまければ嫁の来手があるとは限らないけれど……。けど、それはぼくらの歌の一面を表してるにすぎない。なんて言ったらいいかな……歌ってのは個鯨個鯨の関係が象徴化されたものなのさ。あるいは、アイデンティティとコミュニケーションの統合とでも言おうか……。すなわち、歌はすべてであり、すべてが歌であるといえるのさ。
「もう少し具体的に説明すると、例えば、一シーズンの始めと終わりでぼくらの歌は少しずつ変化していく。一回一回の歌もそれぞれ一曲に当たるんだけど、シーズンを通して一つの曲を歌い続けてるともいえるんだ。それから、基本的にぼくらの歌は独唱なんだけど、同時に〈郡〉全体で歌う合唱曲の一パートを担当しているともみなせる。さらに、長い歴史を通じて歌い継がれてきた一つの長大な叙事詩に、毎年新たな一章を書き足してもいるのさ。このオデュッセイの新章のできばえは年によっていろいろ違ってね。うまいやつがいっぱいいる年はやっぱりできがいい。〈豊饒の海〉が豊かな年や、子宝に恵まれた年もね。〈沈まぬ岩〉に襲われていた時代は、そりゃもう悲惨だった。いまでも終章に近い……第五楽章だったかな? は、暗澹とした旋律が大半を占めている。ラストは、いまのところまだ先の読めない未来、かすかな希望と一抹の不安がちらついているってイメージだな。……よし、いっちょ手本を示してあげようか」
実は、さっきから一曲やりたくてウズウズしていたチェロキーは、クレアの返事も待たずに三度深呼吸した後、すかさず歌の姿勢に入りました。
「歌うときはまず、倒立姿勢をとって身体の長軸を鉛直方向から一五度ないし三〇度傾け、胸を大きく張ったところでヒレの力を抜く。声の出し方は、上顎から額までのラインを突き抜けるような感じで。これが海底の音響効果をうまく利用するコツさ。深さは二〇から三〇メートルくらいのウォーターコラムがベスト」
チェロキーは声の調子を整え、気分をリラックスさせるためにいったん沈黙しました。
「では、若く勇ましいミンククジラのアネさんに一曲贈ります。これはぼくらの〈郡〉じゃ一等メジャーな旋律だよ」
そう言うと、チェロキーは目を閉じて静かに歌い始めました。
──時の回廊 回るよ回る
我らザトウの息吹を乗せて
波のごと絶え間なく
潮のごと切れ目なく
時の回廊 我らが潮路
時の回廊 駈けるよ駈ける
我らザトウの背ビレを掠め
空のごとはるけく
風のごとあてどなく
時の回廊 我らが海路
時の回廊 廻るよ廻る
我らザトウの瞳に映えて
氷のごと清やけく
水のごと安らけく
時の回廊 我らが旅路
時の回廊
今より至りて今にし還る
そは我らが往路──
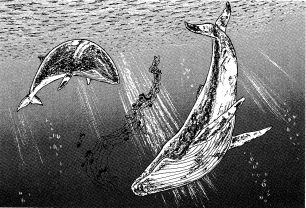 チェロキーの声は青みを増した海中によく染みとおりましたが、低音のところがうまく出せず、また繰り返しのパートを一部間違えていました。そんなこととはつゆとも知らぬクレアは、でき具合の良し悪しはさておき、こんな間近でザトウクジラの独唱が聞けたことにひたすら感激しました。ミンククジラでありながら、本来彼らの同族のメスでしか味わえない特権を享受したわけですから。しばし余韻に浸っていた彼女が瞼を開けると、チェロキーが最初出会ったときのように胸ビレを折って深々とお辞儀しました。
チェロキーの声は青みを増した海中によく染みとおりましたが、低音のところがうまく出せず、また繰り返しのパートを一部間違えていました。そんなこととはつゆとも知らぬクレアは、でき具合の良し悪しはさておき、こんな間近でザトウクジラの独唱が聞けたことにひたすら感激しました。ミンククジラでありながら、本来彼らの同族のメスでしか味わえない特権を享受したわけですから。しばし余韻に浸っていた彼女が瞼を開けると、チェロキーが最初出会ったときのように胸ビレを折って深々とお辞儀しました。「いかがでしたか、奥さん?」
「素敵だったわ……。ところで、さっきコンテストって言ってたけど?」
「ああ、それはね、もちろん歌には種々の社会的な意味合いがこめられているんだけど、純粋に歌そのもののテクニックを競い合うのがコンテストさ。会場は〈抱擁の海〉でいちばん音響効果の高い場所に設けられているんだ。〈聖歌鯨〉の審査を兼ねる厳粛なものでもあるんだけど、若いメスたちがひいきのオスの出番にエールを送ってもいいことになってたり、割と軽いノリなんだよ」
そこでチェロキーははたと、とっておきの話を一つ思いつきました。有頂天になってしゃべくっちゃったけど、当初の目的はちゃんと忘れないようにしなくっちゃ……。
「──実はあるとき、世界中の海のザトウクジラ族が一堂に会したことがあってね。どこの〈大郡〉のクジラがいちばん歌がうまいかを競うことになったんだ。まず最初に北大西洋の〈トップアーチスト〉が出場し、彼は甘く切ないブルースを披露した」
再び逆立ちの姿勢をとると、彼は哀愁を帯びたメロディーの一節を表現してみせました。
「お次は北太平洋の〈歌峰〉。こちらはパッと明るいポップスだ」
今度は陸上に住む遠い兄弟の鳴声にも似た朗らかな曲です。
「さて、いよいよ南半球出身の〈聖歌鯨〉の出番になったんだが、彼はこの夏オキアミを食いすぎて、ステージに上がったところで大きなゲップをひとっつ!」
そこで彼は言葉どおりにゲップの音を発してみせました。
「フ、フフ」
思わず笑みを漏らしたクレアに、チェロキーは首を傾けてニヤリとしました。
「やあ、初めて笑ったね、アネさん」
クレアはチェロキーの顔をじっと見つめ返しました。自分に笑顔を取り戻そうと一所懸命だった彼の気持ちが伝わってきて、胸のうちがじいんとなりました。容姿こそかけ離れているけれど、クレアはこの若くて陽気なザトウクジラにレックスの面影を見たような気がしました。他鯨の職業に口を出すつもりはありませんが、考えてみると、彼は〈歌鯨〉より〈クリエーター〉のほうが性に合っているような気がします。
彼女の隣で励ましてくれるチェロキーのために、そしてレックスのためにも、目的を果たすまでどんな目に遭おうとも笑みを忘れることはしまいと、クレアは心に誓いました。