この境界上ではまた、暖水塊から立ち昇る水蒸気が偏西風の運んでくる冷気に冷やされて、しばしば霧が発生します。いま、二頭のクジラが泳いでいる海面の上も、ミルクのように濃い霧に覆われて、潮を吹いてもほとんど見分けがつかないほどでした。こういう日は、いくら波間から顔を出して眺めまわしたところで、なんの情報も得られやしません。クレアは専ら水中での物音に神経を研ぎ澄まして聞き入りました。暴風圏を通過したときのように、もしかしたらジョーイが彼女を呼ぶ声をキャッチできるかもしれないと思ったからです。果たして、あのとき嵐にまぎれて耳にしたと思ったのは空耳だったのでしょうか? あるいは、イルカたちの悲鳴を聞き間違えたのでしょうか? いいえ、あれは確かに息子が自分に助けを求める声だった──いまではクレアはそう確信していました。母親たるもの、どうしてわが子の声を聞き違えるはずがあるでしょう。
二頭は急激な水温の変化に身体を慣らすよう、ゆっくりと潮境を通り越しました。ほのかに〈抱擁の海〉のぬくみを感じさせる温暖な海流の中に身を投じたとき、ふと不吉な予感がクレアの心をよぎりました。それはほんのかすかな印象でしたが、水がぬるんだのとは裏腹に、南氷洋に舞い戻りでもしたかのような冷ややかな感触がありました。〈豊饒の海〉の冷たさは生命の繁栄を支える恵みのもとですが、これはむしろ生命を根絶やしにせんとするもののようでした。温かな潮の流れは、この海域を覆い包む察知できない邪悪な匂いを運んできているように思えました。どうやらチェロキーも何か感づいたらしく、潮境を通過してから彼の他愛のないおしゃべりも途切れがちになりました。
「ねえ。あなた、この辺よく知ってるんでしょう? 私はアオテアロアの東のコースを通ってるから、こっちは不案内なのよ」
「ううん、ぼくらはたいていもっと大陸側の岸寄りを通ってたからねえ。ジョーイとシャチの連中はいったいどっち方面へ行ったものやら……」
チェロキーはザトウクジラ一族のうちの豪州東側〈大郡〉に属していました。彼の仲間は浅い大陸棚の上を繁殖海域に選んでおり、回遊のコースも大陸の岸辺が見えるようなところを行くか、点々と並ぶ島沿いに渡っていくのが常です。それに対して、ナガスクジラやシロナガスクジラなどは深さ二、三マイルはある海盆の上を通っていくのを好みます。クレアたちミンククジラの一族は、彼らほど遠洋にこだわりはしませんが、〈抱擁の海〉が大洋の真ん中に位置している都合上、どちらかといえば外海派です。
さて、問題はチェロキーも言うとおり、ジョーイを連れたシャチたちが進んだ経路です。シャチの仲間も沿岸と外海の両方を行き来しており、どちらが好きともいえないため、彼らがどのコースを選んだかを見極める材料がありません。迷っていても仕方がないので、二頭はとりあえずオーストラリア方面に針路を向けました。
相変わらず風はなく、霧はいよいよ深まるばかりでした。視界は一〇メートルもきかなくなり、景色が灰色一色に塗り潰されたようです。もはやどこからが水で、どこからが空気なのかすらわかりません。まるで世界全体が水の微粒子から成り立っているようで、そこに多様な生きものが息づいているとは想像もつかないほどです。メタ・セティがこの星を産み落としたばかりのころの世界は、こんな感じだったのかもしれません。
航海に支障はないといえ、先ほどの漠然とした予感もあいまって、クレアは薄気味悪い印象を拭いきれませんでした。白い霞の壁の奥から不意に得体の知れない怪物──もしくは、得体の知れたものでいえば、黒々とした背ビレをそびやかした牙を持つ兄弟の群れ──でも襲いかかってきそうです。一つはジョーイの声を聞くため、もう一つは敵の襲来を事前に察知するために、クレアはゆっくりと泳ぎ進みながら物音に意識を集中しました。ほどなく、彼女の鋭敏な聴覚が何かを捉えました。
「ねえ、何か聞こえない? ほら──」
「え?」
それは聞こえるか聞こえないかというほどの本当にかすかな音でした。出どころも、生きものの仲間が発しているのか、自然の戯れが生み出したスピーカーの仕業なのかもわかりませんが、凶兆の実体はこれだとクレアは直感しました。
「いやあ、別に……」
「あなた〈歌鯨〉なんでしょぉ? しっかり聞いてよ」
クレアに痛いところを突かれ、チェロキーは気合を入れて耳をそばだてました。ようやく彼にも、うなりとも叫びともつかぬ低い音が聞きとれました。声の主は魚でしたが、一尾だけではなくさまざまな種類のものが含まれていました。まるでたくさんの臨終のうめき声を集録したみたいです。クレアはそれらの声に、イルカたちの断末魔の悲鳴と同様、背筋を冷たくするものを感じとりました。前者が凝縮された恐慌状態を表していたとすれば、こちらは分散された孤独な苦悶の和であるという違いはありましたが。いずれにしろ、この海域に満ちている重苦しい雰囲気の正体がこれでわかりました。
「ア、アネさん、どうします?」
「行ってみましょう」
チェロキーがクレアに向けた目からは、明らかにそれとは逆の答えを期待していたことが読みとれましたが、彼女はためらくことなく前進することに決めました。
うめき声の聞こえる海域は二頭の前方数十マイル四方にわたって広がっていました。大半はビンナガとカツオでしたが、ほかにもマンボウ、サメ、カジキなどの声が混じっていました。日常的にはほとんど気にならないほど小さい魚たちの死ぬ間際の悲鳴──エラ蓋をふいごのように開け閉じする音、ヒレをときどき力なくはためかせる音、左右に扁平になった身体を背骨がよじれんばかりに打ち振る最期のあがきも、これだけ多くの数が集まると全身の総毛立つものがありました。死の訪れは途絶えることなく、ささやくようなうめき声は後から後から押し寄せてきました。冷血の魚族に強い親近感を覚えたことのないクレアでしたが、今度ばかりは耳を覆いたくなりました。
奇妙なことに、魚たちの悲鳴が聞こえてくる領域は南北に細長く帯状に走っていました。それはちょうど回遊するビンナガマグロたちの進路を横断する形になっていました。休みなく遊泳し続けないと呼吸が思うに任せないビンナガは、口とエラ穴をパクパクさせて酸素の不足を訴えていました。ビンナガは世界中の暖海に生息するマグロの一種で、ちょうどザトウクジラみたいに胸ビレが長いところに特徴があります。体長一メートルを越す魚類中の兵も、呼吸ができなくなればあっという間にお陀仏です。大きな紡錘形の身体はすぐ目につきましたが、どうしたわけかスピードを誇る彼らが、身動きもとれずに垂直の面にぶら下がっていました。まるで見えない壁が立ちはだかり、彼らを片っ端からからめ捕っているようなのです。クレアはソナーを発してみましたが、反射音を捉えることはできず、流れと平行な潮目とも全然別物でした。魚たちがかかっているのは海面から一五メートルの深さまででしたが、表層を遊泳する魚群にしてみれば行く手を完全に阻まれたも同然です。そのうえ、一度突っこんだが最後、彼らにはバックする能力もないのです。二〇マイル余りにわたって延々と続く〝死の壁〟は、この海域にさらに幾列も伸びていました。
「こいつはきっと〈ゴースト〉の親玉だな」水中に宙吊りにされた魚たちを恐々と横目で見ながら、チェロキーがつぶやきました。
「〈ゴースト〉ですって?」
「陸地に近いほうでよく出くわすんだけど、クラゲみたいに見えにくくて波間を漂ってるやつでね。うかうかして頭を突っこむとひどい目に遭う。ケルプの切れ端に似てるんだけど、頑丈でちょっとやそっとじゃ抜けられない。口の周りにまとわりつけば飯が食えなくなるし、ヒレにからめば身動きがとれなくなる。一度とっ捕まって危うく難を逃れたやつの話を聞いたんだけど、もがけばもがくほど皮膚に食いこんで痛くてかなわんそうだ。こどもにとっては生命取りになるよ」
最後の一言を聞いて、クレアはにわかに不安に駆られました。こんな化けものにジョーイが捕らえられていたらと思うと、いてもたってもいられません。クレアは〝死の壁〟に沿って泳ぎながら息子の名を叫びました。
「ジョーイ! ジョーイッ!」
「あんまり近づかないようにしてくださいよ」
二頭はなるべく見えない壁と一定の距離を保つようにしながら、北に向かって進んでいきました。潮吹き仲間はいまのところかかってはいないようでしたが、呼吸のために水面に上がることの多いクジラたちにとっても危険なものであることには変わりないはずです。クレアたち二頭はたまたま警戒を強めていたから憂き目を見ずにすみましたが、慣れない海で一頭さ迷っていたらまず確実に泳ぎをやめさせられていたことでしょう。
「ねえ、アネさん。シャチの連中はこれに引っかかるほどバカじゃないすよ、たぶん。別の海をあたりましょうや」
早いところこの危険水域を離れたいチェロキーはクレアを説き伏せにかかりましたが、彼女はなおも息子を呼ぶのをやめませんでした。
「ジョーイ!!」
そのとき、クレアたちはだれかが返事をするのを耳にしました。
「オカアサン……」
はっとしたクレアはじっと耳をすましたが、声はそれきり聞こえなくなりました。二頭は黙って顔を見合わせました。
「ジョーイ!?」
クレアがもう一度呼んでみると、今度ははっきりと「オカアサン」と呼び返す声が聞こえました。残念ながら、それはジョーイではありませんでした。けれども、その声は同じ潮吹き族のものに間違いなく、声の主が弱りきっていることも示していました。
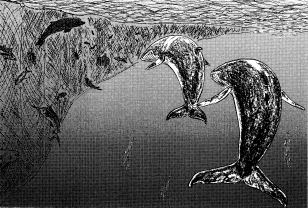 わが子でないとはいえ、母を求める声に心を動かされたクレアは、懸命になって声のした場所を捜しまわりました。〝壁際〟をたどりながら少し先へ行ったところで、ソナーにこれまでの魚とは違う大型の生きものの影が映りました。
わが子でないとはいえ、母を求める声に心を動かされたクレアは、懸命になって声のした場所を捜しまわりました。〝壁際〟をたどりながら少し先へ行ったところで、ソナーにこれまでの魚とは違う大型の生きものの影が映りました。それはミナミトックリクジラのまだ幼いこどもでした。ミナミトックリクジラは深海性の歯持ちの仲間で、いまでは南極周辺に住む大型のクジラの中でクレアたちミンククジラ族に次ぐ主要な住鯨です。主に海底近くに潜ってイカや底魚などを餌にしています。どこかで母親とはぐれてしまったのでしょうか。幸いなことに、引っかかった位置が浅かったため、息をするためにどうにか自力で水面に出ることはできるようですが、尾ビレの根元近くから血がにじんでおり、体力も消耗してアップアップの状態でした。クレアのことを自分の親と勘違いしたわけではなく、朦朧とした意識が彼女の呼び声に応答させたようです。いま、大きな異種族二頭がそばに来たのを見て緊張したのか、その子は口をつぐんでしまいました。
クレアは幼い生命が風前の灯と化しつつあるのを目の前にしてうろたえました。
「チェロキー、どうにかならないの!?」
「そ、そんなこと言ったって……手も足も出ないよ(当たり前だけど)」
「なんとかこの罠を脱け出す方法はないかしら? さっきの〈ゴースト〉から逃れたあなたのお友達はどういうふうにやったの?」
「あれはまったくの偶然に外れたんだよ。それに、体力もある成鯨したザトウクジラだったし」
こうしてなす術もなくウロウロと周囲を泳ぎまわるしかない自分に、クレアは焦れったい気持ちを抑えきれませんでした。血筋が遠く交流がほとんどないとはいえ、シャチのように敵対関係にあるわけでもありませんし、なんといっても相手はまだほんの幼子なのです。
「助けてあげて!」
「無理だよ、アネさん。こっちの身が危うくなっちまう。一本歯の子なんかほっときなよ。仕方がないって」
「いいわよ、あなたには頼まないわ!!」
尻ごみするばかりのチェロキーを無視し、クレアは思いきってミナミトックリの子がかかっている〝壁〟の真下の位置めがけて体当たりを敢行しました。チェロキーの話に従えば、健康なおとなのクジラなら力任せに見えない〝壁〟を突き破ることができるかもしれません。
「ア、アネさん、ムチャだ!!」
〝死の壁〟のあるらしき位置に来る寸前、クレアは交錯する細い糸のようなものがキラッと光るのを垣間見たような気がしました。と思いきや、何かが鼻先に触れ、彼女は水流とは異なる抵抗を感じました。突っこんだ勢いでそのまま〝壁〟をぐうんと前へへこませましたが、衝突直前の一瞬のひるみのせいか、後少しのところでにわかに強度を増した不可視の障害物にクレアは前進を阻まれました。停止した彼女はそこで頭を左右に振って見ましたが、まさに二進も三進もいきません。
「あ~あ、言わんこっちゃない!」
どうにも動きのとれない状態に陥り、クレアは後ろで右往左往しているチェロキーに懇願の視線を投げかけました。
「ええい、こうなりゃ心中だ!!」
やけくそになったチェロキーは、クレアたちに向かってまっすぐ突進しました。〝死の壁〟はピンと伸びきり、そこで一度彼を押し戻しかけましたが、さすがに三〇トンの重量物による急激な負荷には抗しきれなかったとみえ、ついに弾けるように破れました。クレアと歯持ちの坊やもやっと呪縛から解き放たれました。
「ああ、気色悪い!」
チェロキーは頭のコブに引っかかった〈ゴースト〉の切れ端をおぞましげにふるい落としました。連れのザトウにはかまわず、クレアは傷ついた仔クジラのもとへ泳ぎ寄りました。
「大丈夫? 泳げる?」
ミナミトックリクジラの子は、細長く突き出た吻を持つ頭を二度ほど上下に振りました。傷の痛みは残っているようですが、何より自由の身になれたことがうれしかったのでしょう。ちゃんと息が吸えることを確かめるように潮吹きを繰り返し、グルグルと泳ぎまわりました。
「おいおい、あんまりそっちへ行くなって。せっかく助かったのに二の舞はごめんだぜ」
「自分でおうちへ帰れる?」
ミナミトックリの坊やはうなずくと、たどたどしい〈潮吹き共通語〉で二頭に向かって礼を言いました。
「アリガトウ」
そして、親たちの待つ深みへと潜っていきました。
「もう捕まるんじゃないよ」
光は届かなくとも勝手知った平和な住家へ帰っていく幼子の後ろ姿を見送りながら、クレアはわが子が助かったように安堵しました。尾の怪我のことがちょっと気がかりですが、今度水面に上がるときは坊やも恐ろしい罠に十分気をつけるでしょう。
「アネさん、二度とあんな危なっかしいまねはしないでくださいよ。よそのこどものことまでいちいち気にかけてたんじゃ、生命がいくつあっても足りないよ」
文句を言うチェロキーを振り返ると、クレアは口をすぼめて言いました。
「そんな意気地のないことじゃ、いつまでたってもミンクの相手しかできないわよ」
「ちぇっ」
二頭は水面に身を並べ、笑いながら潮を吹き上げました。
霧はいつのまにかすっかり晴れわたっていました。太陽はそろそろ半日に及ぶダイブの準備にとりかかり、斜めに傾いた日差しは風が立てる細波のコントラストを強めました。
ミナミトックリクジラの子の救出劇は、この海域を支配する死の影に呑みこまれないようにするだけの勇気を二頭に与えましたが、現実にクジラのこどもが罠にはまっている場面に遭遇したことで、クレアのジョーイの身を案ずる思いはなおさら強まりました。一方、自ら一度捕らえられながらも逃れえたことにより、不可解さに対する無用な恐怖は減じました。彼女はこの一帯を徹底的に捜索する決意を固めました。
「ねえ、アネさんてば。ほんとに全部見て回るつもりかい? さっきも言ったけど、シャチのやつらはきっとこいつに寄りつきゃしないよ」
チェロキーはクレアの後に従いながらも、また同じ役目を背負わされるのは懲り懲りだと言わんばかりに、何度もクレアにここを立ち去るよう勧めました。
「別につきあってくれなくていいわよ。あなたにとってジョーイはどうせよその子なんだから」
「そんなつれないこと言わないでくださいよ」
はじめのころは恐怖心が先に立って注意深く観察する余裕がなかったのですが、よく目を凝らしてながめるうちに、クレアにはこの〝死の壁〟の持つ性質がある程度つかめるようになりました。魚たちは必ずしもすべてがすべて捕らえられているわけではなく、跳ね返されたり、小さいものはどういうふうにかうまくすり抜けていく者もいました。が、そうした場合でもウロコが剥げ落ちたりして、この先生き延びられるかどうかは危ぶまれました。いくら目を細めて凝視しても、例の白く光る糸の存在は見極められませんでした。よほど細くできていて、エコロケーションでは確認できないのもそのせいでしょう。そのような代物が、彼女のように大きなクジラにさえ簡単には破れないほど強靭であるなど、にわかには信じがたいことでした。しかし、よくよく気をつけると、アオブダイのベッドにも似たまゆのようなものが魚たちの周りをぼんやりととりまいているのがわかりました。逃れようと暴れまわるうちに、柔軟な見えない繊維でできた〝壁〟がひだのように自然に折りたたまれて、獲物はがんじがらめにされてしまうのです。まさに〈ゴースト〉と呼ぶにふさわしい死の罠でした。
それにしても、いったいだれが、なんのためにこれほど多くの生命を犠牲にしているのでしょう? いくら罠の仕組みが少しばかりわかったところで、なんの変哲もない海の中を何十マイルにもわたって幾千幾百という屍が吊り下げられている様は、不気味としか言いようがありませんでした。この海全体に呪いでもかかっているのでしょうか?
宵闇が近づき、水の中も藍色に染まりはじめました。クレアは息子の名を呼び続けながら、返事が戻ってこないかと耳をそばだてました。同じように耳で〝聴る〟作業に集中していたチェロキーが、不意に彼女を呼び止めました。
「アネさん! でかい影だ!!」
影は〝死の壁〟の最も北側の端に位置していました。もしかしたらジョーイかもしれないとクレアの気は逸りましたが、それはクジラよりもっと大きな物体で、水面にぽっかりと浮かんでいました。用心しながら影の正体がつかめる距離まで接近したとき、クレアの身体を戦慄が駆けぬけました。それはほかでもない〈沈まぬ岩〉だったのです。
二頭はその場にじっと静止しました。いまのところその〈岩〉には動きが見られませんでしたが、まさか〈岩〉までが罠にはまったわけではありますまい。むしろ、クレアには〝死の壁〟を裏で仕掛けていたのが何者だったかわかったような気がしました。その証拠に、〈岩〉たちは平行に並ぶそれぞれの〝壁〟の一端に一つずつ配置されていたのです。
クレアたちは慎重に〈沈まぬ岩〉のいる場所を迂回して移動しました。二頭ともしばらく口をききませんでした。やがて日は水平線の彼方に没し、水の上も下も真っ暗な闇が覆いました。ときおり罠にかかった魚たちのうめき声が聞こえてくるほかは、主だった変化はありませんでした。クレアとチェロキーは平行に水面に浮かんで、互いにゆっくりと円を描くように泳ぎながら睡眠をとりました。クジラたちは、場合によっては脳を半分ずつ休ませられるという特技を持っています。円の内側のほうの目はつぶっていても、反対側の目は開いてしっかり外を見張っていられるというわけです。そんなときはときどき泳ぐ向きを変え、左右の半身で替わりばんこに眠ることもあります。
真夜中近くになったころ、クレアは〈沈まぬ岩〉の動向が変化したのに気づいて目を覚ましました。彼女は(右左とも)うつらうつらしていたチェロキーをそっと起こしました。
「チェロキー、〈岩〉が動きだしたわ」
見ると、水平線に沿って太陽と見まがうほどの眩しい灯りが一列に並んでいます。〈沈まぬ岩〉はどうやら深海魚に勝る強力な発光装置を備えているようです。何事が始まるのかと、クレアたちが固唾を飲んで見守っていると、なんと絶命したはずの魚たちの屍が、一つの方向に向かっていっせいに泳ぎはじめたではありませんか! いうまでもなく、その方向には〈岩〉たちが待ちかまえていました。〈沈まぬ岩〉は死んだ魚たちを魔法を使っていったんよみがえらせ、わざわざ自分たちの顎門に向かって行進させているのでしょうか? 無数の死体はぶら下がったままの格好で幽鬼のように引きずられていました。クレアは身震いし、魚たちの亡霊を招き寄せている強烈な光から目を背けました。悪夢のような光景が繰り広げられる中、二頭はただ呆然として身を寄せ合っていました。
死の行進は翌朝まで続き、何千尾ものビンナガやカツオの死骸は跡形もなく片付けられました。〈沈まぬ岩〉たちはそれらの魚をことごとく飲み干してしまうと、巨大な胃袋をまだ満たしきらないとみえ、次の餌場を求めて移動しはじめました。もし、ジョーイが昨夜までの間に罠に捕らえられていたとしたら、いまごろはとっくに〈岩〉の胃袋の中に収まっているに違いありません。未練は残りましたが、チェロキーの言うように、ジョーイを連れたシャチたちが〝死の壁〟に近寄らなかったことを祈って、クレアはこの恐ろしい墓場のような海を後にしました。〈岩〉たちの向かった方角から水音が聞こえてきました。しばらくすると、またかすかな悲鳴が伝わってきましたが、クレアはもう振り返りませんでした。朝靄が何事もなかったかのごとく波の上に棚引いていました。