丂惗柦偺梙傝饽偵偟偰幚偺曣偱傕偁傞乹儊僞丒僙僥傿偺巕乺偼丄峀戝側塅拡傪昚偄側偑傜丄帺暘偺懱昞偵廧傑偆柍悢偺偪偭傐偗側婑惗拵偵擕傪梌偊偰偒傑偟偨丅惗偒傕偺偨偪偼傒側斵彈偺壎宐偵梺偟側偑傜傕丄斵彈偺惗偺昞弌偺搑曽傕側偄僗働乕儖偺慜偵偼偨偩偨偩埑搢偝傟傞偽偐傝偱丄幚姶偡傞偺偑偐偊偭偰擄偟偄傎偳偱偟偨丅斵彈偵偲偭偰偼戜晽偩偭偰偔偟傖傒偺堦偮偵偡偓側偄偱偟傚偆偟丄壩嶳偼偣偄偤偄彫偝側偍偱偒偺傛偆側傕偺偱偟傚偆丅
丂儊僞丒僙僥傿偺挒帣偑栚埨偵偟偰偄傞帪寁偺恓偺恑傒曽偼丄惗暔偺巊偭偰偄傞偦傟偵斾傋偰偼傞偐偵抶乆偲偟偨傕偺偱偡丅惗偒傕偺偨偪傪偲傝傑偔帪娫偺棳傟偑偣偣傜偓偺拞偱彫愇傪愻偆塓姫偒偩偲偡傟偽丄斵彈偑惗偒傞帪娫偼梇戝側戝壨偺備偭偨傝偟偨棳傟偵偁偨傞偱偟傚偆丅側偵偟傠丄斵彈偺擭楊偼巐榋壄嵨偱乮斵彈帺恎偵恞偹偰傒偰傕丄偒偭偲乽偁傑傝墦偄愄偺偙偲側偺偱朰傟偨乿偲偟傜偽偔傟傞偵堘偄偁傝傑偣傫乯丄偙傟偐傜偺梋柦傕傑偨摨偠偔傜偄偁傞偺偱偡偐傜丅偦偟偰丄偦偺娚傗偐側帪娫偺広搙偱尒偨偲偒丄斵彈偺昞忣偼幚偵僟僀僫儈僢僋偵曄壔傪悑偘偰偒傑偟偨丅戝婥傕丄奀傕乮斵彈偺敡偼惗傑傟偨偲偒偐傜偄傑傎偳弫偭偰偄偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫乯丄偦偟偰丄斵彈帺恎偺奜旂偲偄偆傋偒屌偄抧妅傕丄崗乆偲偦偺條憡傪曄偊偰偒傑偟偨丅偮傫偲撍偒弌偨旲椑偺傛偆側嶳柆偑偦偦傝棫偭偨偐偲巚偊偽丄塉晽偵嶍傜傟偰偨偪傑偪掅偔側偭偨傝丄昘壨偺偍偟傠偄傪岤偔揾偭偰傒偰偼傑偨怈偄嫀偭偨傝丄婄宆偦偺傕偺偱偁傞戝棨偺攝抲傪偁偪偙偪堏偟偰傒偨傝丅斵彈偼寢峔梕杄偵偼偆傞偝偄偨偪傜偟偔丄偙傟傑偱偺挿偄敿惗偺娫偵丄摨偠敮宆傗壔徬偼擇搙偲帋偝側偐偭偨偲偄偭偰傕偄偄傎偳偱偡乮傕偭偲傕丄廫枩擭傗偦偙傜偼曄偊偢偵偄偰傕暯婥側傛偆偱偡偑乯丅斵彈偺応崌丄偦傟傜偺戝偑偐傝側惍宍庤弍偼慡晹帺暘偱巤偡傢偗偱偡丅偦偺曽朄偼丄堦庬偺扙旂偵嬤偄傕偺偱偟偨丅
丂偙偺榝惎偺棨抧偵偁傞娾愇偵偼丄斵彈偑惗傑傟偨偰偺偙傠偵偱偒偨傕偺偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅偦傟偼丄斵彈偑愨偊偢屆偄旂傪帺傜偺懱撪偵庢傝偙傫偱丄怴偟偄旂傪惗偊偝偣偰偄傞偐傜偱偡丅斵彈偺旂晢偑怴惗偡傞応強偼丄戝梞偺恀傫拞傪憱傞挿戝側奀掙嶳柆偱偡丅斵彈偺懱擬偑嶌傝弌偡儅儞僩儖懳棳偵傛偭偰忋徃偟偰偒偨儅僌儅偼丄敄偄奀梞抧妅偵妱傟栚傪尒偮偗偩偟偰丄偦偙偐傜昞柺偵婄傪弌偟傑偡丅崅壏偺偨傔偵惙傝忋偑偭偨偙偺楐偗栚偺晹暘偑丄拞墰奀椾偲屇偽傟傞奀偺戝嶳柆偱偡乮偙偺偆偪丄懢暯梞偵偁傞傕偺偩偗偼丄側偤偐恀傫拞偱偼側偔撿搶傛傝偺埵抲偵曃偭偰憱偭偰偄傑偡乯丅恀怴偟偄斵彈偺旂晢偼丄擭偵悢僙儞僠儊乕僩儖偺懍搙偱偙偙偐傜嵍塃偵墴偟弌偝傟偰偄偒傑偡丅偦傟傜偑偡偭偐傝椻偨偔側偭偰丄嵟屻偵奀峚偺墱掙偵撣傒偙傑傟傞傑偱丄偮傑傝斵彈偺旂晢偑慡晹惗偊懼傢傞傑偱偵偼丄壗壄擭偲偄偆擭寧偑偐偐傝傑偡丅旂偺堦晹偼丄棨懁偐傜棳傟偙傫偱懲愊偟偨搚嵒偲偲傕偵丄晄堄偵晜忋偟偰棨抧偵晅偗壛傢傞偙偲傕偁傝傑偡丅
丂偙偆偟偨斵彈偺偨備傑偸旤梕懱憖偺寢壥乮墲乆偵偟偰偟傢傪憹傗偡偙偲偵傕側傞偺偱偡偑乯丄戝棨偑偔偭偮偄偨傝棧傟偨傝丄搰偑偱偒偨傝捑傫偩傝丄偦偺傎偐偝傑偞傑側抧宍偑惗傑傟偰丄婥岓傗挭偺棳傟偵塭嬁傪媦傏偟丄傂偄偰偼惗暔偺暘壔傗恑壔傪傕偨傜偡偺偱偡丅崱擔斏塰偟偰偄傞庬乆偺惗偒傕偺偨偪偼丄偄傢偽乹儊僞丒僙僥傿偺巕乺偺朙偐側昞忣傪傛傝堦憌嵺棫偨偣傞僠儍乕儉億僀儞僩偲偄偊傞偱偟傚偆丅偦偺偍偐偘偱丄巐榋壄嵨偺楉偟偺廼彈偼丄嵨傪傆傞偵偮傟偰傑偡傑偡旤偟偔丄惗偒惗偒偲偟偨柺棫偪傪尒偣偰偄傞偺偱偡丅
丂奀椾傗奀峚偺嬤偔偱偼妶敪側抧擬妶摦偑孞傝峀偘傜傟偰偍傝丄偄傑傑偝偵惗傑傟偮偮偁傞怴偟偄奀掙偺嶻惡傪暦偔偙偲偑偱偒傑偡丅偦偙偱偼婏夦側宍忬傪偟偨梟娾偑僑儘僑儘偲揮偑偭偰偄偨傝丄擬偣傜傟偨悈偑暚弌偟偰峼暔傪寢徎偝偣丄傕偔傕偔偲崟墝傪揻偔墝撍傪抸偒偁偘偰偄傞偺偑尒傜傟傑偡丅埮偺儀乕儖偵曪傑傟偨怺奀偺悽奅偙偦偼丄乹儊僞丒僙僥傿偺巕乺偺塩乆偨傞惗偺徹嵍傪奯娫尒傞偙偲偺偱偒傞尰応側偺偱偡丅偦偟偰丄戝抧偑柭摦偟擬悈偑偨偓傞堦尒抧崠奊恾偺傛偆側偙偺椞堟偵偼丄懢梲偺岝偵椘傪媮傔側偄婏柇側惗暔偨偪偑孮傟廤偭偰偄傑偡丅棸墿傪怘傋傞僶僋僥儕傾丄栚偺側偄僇僯丄愒偄寣偺棳傟傞戝偒側擇枃奓丄岥傕徚壔娗傕帩偨側偄晄壜巚媍側惗暔僠儏乕僽儚乕儉劅劅丅傛偦偺惗懺宯偵懏偡傞惗偒傕偺偨偪偐傜偡傟偽巰偺崙偺傛偆偵巚傢傟偰傕丄偦傟傜偺庬懓偵偲偭偰偼丄偦偙偼婅偭偰傕側偄埨妝側僐儘僯乕側偺偱偟偨丅
丂偲偒偵怺傒傪朘傟傞偙偲傕偁傞僋僕儔偨偪偼丄偦偺傛偆側怺奀偺惗暔憌傗惗乆偟偄戝抧偺塩傒偵偮偄偰傕丄曣側傞奀偑帩偮僶儔僄僥傿偵晉傓慺婄偺堦偮偲偟偰擣幆偟偰偄傑偟偨丅偲偙傠偑丄斵傜偺庬懓偺乹憂憿偺側偣傞懺偺懡條偝偵栚傪尒挘傞幰乺偵傕堷偗傪庢傜側偄傎偳擬怱偵丄偦偺偁傝偝傑傪娤嶡偡傞幰偑偁傝傑偟偨丅偦偺乹娤嶡幰乺偲偼丄傎偐偱傕側偄乹捑傑偸娾乺偱偟偨丅偦傟傜偺婷梸偲偝偊偄偊傞妛媶怱偺崅偝偼丄僋僕儔偺乹惗暔娤嶡幰乺傕徧巀傪憽傞偵壙偡傞傎偳偱偟偨丅偟偐偟丄偦偺戝偑偐傝側噣栚偺尒挘傝曽噥偼丄傗傗傕偡傟偽懠偺惗偒傕偺偨偪偺柪榝傪屭傒側偄傕偺偵側傝偑偪偱偟偨丅傑偨丄乹娾乺偺偦傟傜偺妶摦偺杮摉偺摦婡偼丄惗偒傕偺偺悽奅偺慺惏傜偟偝偵懅傪撣傓偨傔偲偄偆傛傝傕丄偳偆傗傜乹儊僞丒僙僥傿偺巕乺偑懱昞偵暘斿偟偨岰乮偟偽偟偽崅弮搙偺儅儞僈儞傗僯僢働儖傪娷傫偱偄傑偡乯傗丄懢屆偺惗偒傕偺偨偪偺巖偺曄惉暔乮偙偪傜偼帀暘偵晉傫偱偄傑偡乯偵噣栚傪尒挘傞噥偙偲偵偁偭偨傛偆偱偡乧乧丅
丂婋偆偄偲偙傠偱嫲傞傋偒僔儍僠偺捛寕傪偐傢偟偨僋儗傾偲僠僃儘僉乕偼丄僒儞僑徥偺搰乆偺峀偑傞奀傪敳偗偰丄嵞傃巐曽傪悈偽偐傝偑愯傔傞戝奀尨傪搶傊岦偗偰塲偄偱偄傑偟偨丅
丂堦搙偼僕儑乕僀傪桿夳偟偨僔儍僠偺孮傟偵擏敆偟丄屻彮偟偱斵偲偺嵞奐傪壥偨偣傞偲偄偆偲偙傠偱丄懅巕偺埨斲傪妋偐傔傞娫傕側偔丄嶦滳幰偺僔儍僠偐傜摝偘傞偨傔偵屻栠傝偟側偔偰偼側傜側偔側偭偨僋儗傾偼丄偑偭偔傝偲嫻價儗傪棊偲偟偰偄傑偟偨丅嫢朶側帟僋僕儔偵姎傒嶦偝傟傞塣柦偼柶傟偨傕偺偺丄傑偨傕傗僕儑乕僀偺嫃応強偼偮偐傔側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅偳傫側偵帹傪偡傑偟偰傒偰傕丄僕儑乕僀偺惡傕僔儍僠偨偪偺塲偖壒傕暦偙偊偰偼偒傑偣傫丅僋儗傾偨偪傪捛偄曉偟偰偄傞娫偵丄柭傝傪傂偦傔偰傕偭偲墦偔傊巔傪偔傜傑偟偰偟傑偭偨偺偱偟傚偆丅
丂桿夳斊偑偦偺傑傑捈恑僐乕僗傪曐偮偲偄偆曐徹偼偳偙偵傕偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄擇摢偼摉弶偺梊掕偳偍傝搶偺恑楬傪庢偭偰偄傑偟偨丅億儕僱僔傾傑偱偺摴拞丄僕儑乕僀偵捛偄拝偙偆偲僄儞僕儞傪僼儖夞揮偝偣偰旘偽偟偰偒偨惃偄傕丄偄傑偱偼偡偭偐傝悐偊偰偄傑偟偨丅僋儗傾偼壗傗傜偟偒傝偲峫偊偙傓傛偆偵側傝丄婥傑偢偦偆偵偮偄偰偔傞僠僃儘僉乕偺巔傕栚偵塮傜側偄偲偄偭偨條巕偱偟偨丅
丂偨偲偊傕偆堦搙僔儍僠偺孮傟偵捛偄拝偗偨偲偟偰傕丄僕儑乕僀傪媬偄偩偡庤棫偰偑側偔偰偼側傫偺堄枴傕偁傝傑偣傫丅偄偭偨偄偳偆偟偨傜丄偁偺嫸婥偺僔儍僠偨偪偺僸儗偐傜僕儑乕僀傪扗娨偡傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆乧乧丅懱宆偺揰偱偼偝偟偨傞堘偄偑側偄偲偼偄偊丄塻偄夊偲寏椶奅悘堦偺僗僺乕僪傪屩傞僔儍僠偲丄桞堦偺晲婍偑戝偒偝偱偟偐側偄僸僎僋僕儔偲偱偼丄嵟弶偐傜彑晧偼尒偊偰偄傑偡丅偍傑偗偵丄廤抍偱庪傝傪偡傞惈幙傪桳偡傞僔儍僠偼丄摢擼偺揰偱傕懠偺僋僕儔懓傛傝桪廏偱偡丅傢偗偰傕偢傞尗偦偆側偙偺憡庤偺棤傪偐偔偺偼丄惗堈偟偄偙偲偱偼側偄偱偟傚偆丅奀拞偱暔傪噣挳傞噥擻椡偵偍偄偰傕丄僔儍僠偨偪偺傎偆偑偼傞偐偵彑偭偰偄傑偡丅偳傫側偵摢傪傂偹偭偰偄偄抦宐傪嶏傝弌偦偆偲偟偰傕丄敪尒偝傟偢偵愙嬤偟丄僕儑乕僀傪偙偭偦傝楢傟弌偡曽朄側偳尒偮偐傝偦偆偵偁傝傑偣傫丅偙偪傜偑岦偙偆傪姶抦偡傞偢偭偲埲慜偵丄憡庤偺傎偆偑偙偪傜偺強嵼偵婥偯偄偨偺偱偡偟丄偄傑傗寈夲怱傪嫮傔偰偄傞偱偟傚偆偐傜丄偍偄偦傟偲偼嬤婑傜偣偰偔傟傑偡傑偄丅偣偄偤偄丄曣恊偑栚偺慜偱傓偛偨傜偟偔嶦偝傟傞偲偙傠傪懅巕偵尒偣偮偗傞偙偲偵側傞偺偑棊偪偱偟傚偆丅朣偒儗僢僋僗偲偺栺懇傪壥偨偡帺怣偑丄悈偐傜弌偨傾儊僼儔僔偺傛偆偵媫懍偵偟傏傫偱偄偔偺傪丄僋儗傾偼姶偠傑偟偨丅
丂奀偺忋偱偼杅堈晽偑丄嶐擔傕崱擔傕朞偒傕偣偢撿搶偺岦偒傪曐偪側偑傜悂偒搉偭偰偄傑偡丅娚傗偐側偆偹傝偲壐傗偐側擔嵎偟偼丄忢壞偺愒摴偺椞堟偵嬤偯偄偨偙偲傪崘偘偰偄傑偟偨偑丄僋儗傾偺摢偺拞偱偼嬯栥偺僽儕僓乕僪偑悂偒峳傟偰偄傑偟偨丅
丂僠僃儘僉乕偼僠僃儘僉乕偱丄僋儗傾偵偮偄偰偙偙傑偱棃偰偟傑偭偨偙偲偵丄偄偔傇傫屻夨偺擮傪妎偊偰偄傑偟偨丅峴曽晄柧偺斵彈偺巕傪憑偡偲偙傠傑偱偼偄偄偲偟偰傕丄嫸偭偨僔儍僠偺戝妠偐傜惗柦偐傜偑傜摝傟傞塇栚偵憳偆偺偼傕偆婅偄壓偘偱偟偨丅偨偲偊師偺崶栺憡庤偑尒偮偐傜側偔偰傕丄拠娫偲堦弿偵柍擄側堦擭傪憲偭偨傎偆偑儅僔偩偭偨偐側乧乧丅堦曽偱丄偙偺堦搑偱婥忎側儈儞僋僋僕儔偺儊僗偵丄斵偑岲姶傪書偄偰偄傞偙偲傕帠幚偱偟偨丅側傫偲偐斵彈偵懅巕傪庢傝栠偝偣偰傗傝偨偄偲巚偄傑偟偨丅弌夛偄偺弖娫偺姶摦揑側忣宨偼丄偒偭偲壧偺戣嵽偵傕偭偰偙偄偱偟傚偆丅偄傑偺帺暘偑堦旂岦偗偰惉挿偡傞偒偭偐偗偵側傞偺偱偼丄偲偁偰偵偟偰傕偄傑偟偨丅偦傟偵丄偄傗偟偔傕乹壧寏乺偺抂偔傟傪帺擣偡傞幰偲偁傟偽丄婋擄偵嵺偟偰傕埿晽摪乆偲峔偊偰偄側偔偰偼側傝傑偣傫丅僐儞僥僗僩夛応偱偁偑偭偰偟傑偭偰惡偑忋嶤傞傛偆偱偼丄偲偰傕戝暔偺壧庤偵側傟傞尒崬傒側偳側偄偺偱偡偐傜丅傑偟偰傗乹惞壧寏乺偲傕側傟偽丄偨偲偊傗偔偞幰偺僔儍僠偵偲傝埻傑傟傛偆偲丄壧傪搑拞偱拞抐偟偨傝側偳偟側偄傕偺偱偡乮偦偺揰丄僔儍僠偺塭偵偁傢偰傆偨傔偄偰恀偭愭偵摝偘偩偟偨偺偼丄傑偩傑偩斵偵廋嬈偑懌傝側偄徹嫆偱偟偨乯丅偲偄偭偰丄僋儗傾傎偳摢傪擸傑偣傞傑偱傕側偔丄嫮椡側揤揋偵帺暘偨偪偺帟偑丄偄偊丄僸僎偑棫偨側偄偙偲偼柧傜偐偱偡丅僠僃儘僉乕傕僋儗傾偲摨偠偔丄悂愥偺柪楬偵偼傑傝偙傫偱敳偗摴傪扵偟偁偖偹偰偄偨偺偱偟偨丅
丂擇摢偺椃偼丄堦揮偟偰埫偔桱偄偵捑傫偩傕偺偲側傝傑偟偨丅栙乆偲塲偖擇摢偺慜曽偵戝偒側塭偑晜偐傫偱偄傞偺傪丄愭偵尒弌偟偨偺偼僠僃儘僉乕偺傎偆偱偟偨丅応強偼偪傚偆偳撿杒偵偆偹偆偹偲楢側傞奀掙嶳柆劅劅搶懢暯梞奀朿偺恀忋偱丄斵傜偼怺奀偵弒尟偲偟偰偦傃偊傞曯乆偺捀傛傝偝傜偵堦儅僀儖埲忋偺崅傒傪墶抐偟傛偆偲偟偰偄偨偲偙傠偱偟偨丅
乽傾僱偝傫丄慜偵壗偐偄傞偧!?乿
丂擇摢偼僔儍僠偺栆捛傪庴偗偨屻偩偭偨偺偱丄傑偢偦偺応偵偲偳傑偭偰梡怱怺偔憡庤傪噣挳掕傔噥傛偆偲偟傑偟偨丅
乽乹捑傑偸娾乺偩傢両乿
丂挼偹曉偭偰偒偨僄僐乕傪暦偄偨僋儗傾偼楾攤偟偰嫨傃傑偟偨丅乹朙閌偺奀乺偱偺捝傑偟偄婰壇偑傑偞傑偞偲斵彈偺擼棤偵傛傒偑偊偭偰偒傑偟偨丅嫰偊偰偡偔傫偱偄傞僋儗傾偵懳偟丄僠僃儘僉乕偨偪僓僩僂堦懓偼媣偟偔乹捑傑偸娾乺偺峌寕傪旐偭偰偄側偐偭偨偨傔丄斵偼傕偭偲傛偔憡庤偺惓懱傪妋偐傔偨偄偲偄偆桿榝偵嬱傜傟傑偟偨丅
乽偙偙偼乹朙閌偺奀乺偠傖側偄偐傜戝忎晇偱偡傛丄傾僱偝傫丅偦傟偵丄偁偄偮偼乹僑乕僗僩乺傕揻偒弌偟偪傖偄側偄傛偆偩乿
丂僠僃儘僉乕偼偦傠偦傠偲夞傝偙傓傛偆偵乹捑傑偸娾乺偵愙嬤偟偰偄偒傑偟偨丅
乽僠僃儘僉乕丄傛偟偰傛両丂婋側偄傢!!乿
丂僋儗傾偺棅傒傪柍帇偟偰僠僃儘僉乕偼恑傒傑偟偨丅斵偲偟偰偼偙偙偱桬婥傪尒偣偰丄愭傎偳墘偠偰偟傑偭偨幐懺偵懳偟柤梍傪斠夞偟偨偄偲偄偆怱愊傕傝傕偁偭偨偺偱偡丅
丂僠僃儘僉乕偺愙嬤偵懳偟偰傕丄偦偺乹捑傑偸娾乺偼側傫偺斀墳傕帵偟傑偣傫偱偟偨丅僋儗傾傕巇曽側偔偍偦傞偍偦傞僠僃儘僉乕偺屻偵廬偄傑偟偨丅偐側傝戝宆偺晹椶偵擖傞偦偺乹捑傑偸娾乺偼丄奀偺忋偺堦儠強偵偠偭偲偟偨傑傑攇偵梙傜傟偰偄傑偟偨丅妋偐偵丄乹朙閌偺奀乺偱偼僋僕儔懓偵廝偄偐偐傞偺偼庡偲偟偰彫傇傝偺乹娾乺偺傎偆偱偟偨偟丄偦偺娫戝宆偺乹娹乺偺傎偆偼塧偑塣偽傟傞偺傪偨偩懸偭偰偄傞偩偗偱偟偨丅偄傑偺偲偙傠丄噣挳捠偟噥偺傛偄偙偺嬤曈偺奀偵丄庤壓偺彫宆乹娾乺偑傂偦傫偱偄傞婥攝偼偁傝傑偣傫丅
乽巰傫偱傞偺偐側丠乿
乽桘抐偟偪傖偩傔傛乿
丂嬤偯偔偵偮傟偰丄憡庤偺椫妔偑偼偭偒傝懆偊傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅晛捠偺乹捑傑偸娾乺偺掙偑丄撈摿偺悇恑婍姱傪旛偊偨屻旜傪彍偄偰妸傜偐側偺偵懳偟丄偦偺乹娾乺偺壓晹偵偼偄偔偮偐偺撍婲暔偑旘傃弌偟偰偄傑偟偨丅傑偨丄屻曽偺悈拞偵壗偐嫑傜偟偒宍傪偟偨彫偝側傕偺偑晅偒廬偭偰偄傑偟偨丅
乽摦偒偩偟偨傢両乿
丂乹捑傑偸娾乺偼幚偵僲儘僲儘偲偟偨僗僺乕僪偱恑傒巒傔傑偟偨丅僋儗傾偲僠僃儘僉乕偑堏摦偟偰傕丄偦傟偼恓楬傪曄偊傛偆偲偼偟傑偣傫偱偟偨丅僠僃儘僉乕偼嫲偄傕偺尒偨偝偲丄乹壧寏乺偲偟偰偺搙嫻帋偟偺偮傕傝傕偁偭偰丄偦偺応偵摜傒偲偳傑偭偰晄壜夝側摦偔柍惗暔偺峴摦傪尒嬌傔傛偆偲偟傑偟偨丅乹娾乺偑斵傜偐傜昐儊乕僩儖埲撪偵傑偱敆偭偨偲偒丄撍擛偡偝傑偠偄戝壒嬁偑偲偳傠偒傑偟偨丅
乽側丄側傫側偺偭!?乿
乽偆傂傖乣乣偭!!乿
丂崒壒偼戝抧傪揱傢傞抧恔偺傛偆偵丄巐曽偺悈夠傪寖偟偔梙偝傇傝傑偟偨丅壒尮偼乹娾乺帺恎偱偼側偔丄偦傟偑塯偄偰偄傞彫偝側晅懏暔偺傎偆偱偟偨丅偄偢傟偵偣傛丄埑弅嬻婥偺敋敪偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偨偦偺壒偼丄僋儗傾偨偪偺塻晀側挳妎傪堦帪揑偵儅僸偝偣傞偺偵廫暘側壒検傪帩偭偰偄傑偟偨丅
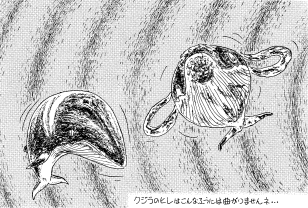 乽屰枌偑攋傟傞傛偭!!乿
乽屰枌偑攋傟傞傛偭!!乿乽摢偑捝偄傢!!乿
丂壒偼奀掙偺嶳柆偵傇偮偐傝丄墲暅擇儅僀儖偺嫍棧傪宱偰曉偭偰偒傑偟偨丅斀幩偟偨偙偩傑偑姰慡偵徚偊擖傞娫傕側偔丄戞擇攇偑廝偄偐偐傝傑偟偨丅偦傟偼摿掕偺妉暔傪慱偄寕偪偟偨傕偺偱偼側偔丄偦偙傜拞偵偽傜嶵偐傟傞壒偺嶶抏偱偟偨丅偦偺偆偊丄壒偺僗儁僋僩儖偺偁傜備傞椞堟偑堦嫇偵曻幩偝傟偰偄傑偟偨丅憶壒偑懕偄偰偄傞娫丄擇摢偺曽岦姶妎偼崿棎傪棃偟丄偍屳偄偺埵抲偝偊傢偐傜側偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅
乽僠僃儘僉乕両丂憗偔偙偙偐傜棧傟傞偺傛!!乿
乽傾僱偝傫丄側傫偰尵偭偨偺!?丂暦偙偊側偄傛偭!!乿
丂乹捑傑偸娾乺偼備偭偔傝慜恑偟側偑傜丄摍娫妘偱棫偰懕偗偵搟崋偺傛偆側壒嬁傪嶵偒嶶傜偟傑偟偨丅旐奞偵傑偒偙傑傟偨擇摢偺僋僕儔偑偡偭偐傝婥傪摦揮偝偣丄側偡弍傕側偔塃墲嵍墲偟偰偄偨偲偙傠丄晄堄偵暿偺惡偑帹偵撏偒傑偟偨丅
乽偙偭偪傊偄傜偭偟傖偄丄憗偔両乿
丂偦傟偼乹娾乺偺柭壒偺寗娫傪偮偄偰怲廳偵慖偽傟偨掅廃攇偺惡偱偟偨丅僋儗傾偨偪偼惡偺庡偑壗幰偐傪妋偐傔傞梋桾傕側偔丄屇偽傟傞傑傑偵寽柦偵僸儗傪摦偐偟傑偟偨丅
乽憗偔両丂偙偭偪偠傖両乿