だしぬけに起こった〈巌〉の事故を利用して、ついでにドクガンは、彼の地位を狙う副隊長サカヒレの送りこんだ間諜と目をつけていた隊員三名のうち、二名を始末しました。黒い海に呑まれて助かる見込みのない虜囚を回収しにいかされた二頭は、炎に巻かれ激痛と歓喜に悶絶しながら殉死しました。
「任務を果敢に遂行し、いまモノ・セティの祝福をヒレにした二名の隊員の栄えある死を讃えよ!」
燃えさかる火に包まれてブリーチする二頭の同志を、海上に整列した親衛隊員一同は羨望の眼差しで見つめました。これでサカヒレのやつにちょっとした海産話ができたってわけだ。しかし、救いようのないトンマのおかげで生命拾いしたやつもいるな……。同じ命令を受けたラングイは、瀕死のカマイルカをくわえて早々に抜けだしてきたため、危うく丸焼きを免れたのです(そのイルカは脂まみれで食料の足しにもなりませんでした)。
「やい! どこをどう間違えたらクジラの子がイルカに化けて出てくるんだ、このマヌケ! 貴様も二頭を見習ってあそこに飛びこんでこい! いまからだって遅くねえ!」
「親ぶ、いや隊長、どうかそればかりはご勘弁を~」ラングイはオオカミウオのような乱杭歯の並ぶ大口をだらしなく開けて懇願しました。
フン。まあ、こんな脳不足のやつを気にかける必要もねえが……。これで、一年近く前に本拠地を出た二〇頭の精鋭部隊は、南太平洋で消息を断ったミツマタと部下を含めて五名減ったことになりました。やれやれ、ミンクのガキを引き回すのに、俺たちまでモノ・セティの選別を食らうとはな。それに比べてこいつらはどうだ? ドクガンは生き残った八頭の仔クジラに張りだした右目を向けました。幼くして親兄弟と引き離されながら艱苦の旅を切り抜けることができたのは、確かに一歳のヒゲクジラとしてはタフな体躯と性格を持った子ばかりです。彼らのうち二、三頭はどうにか本拠地までたどり着けるでしょう。この分だとどっか途中で新しいやつを拾ってごまかす必要はなくなりそうだな……。
ただ、選り抜きのミンククジラの子の中に、一頭だけ似つかわしくないメスが混じっていました。小柄でいかにも華奢な感じのするそのメスの子は、次はこいつがくたばる番だ、次こそはこいつの番だ──というドクガンの予想を裏切り、あの〈黒い脂〉の大災害をもくぐり抜けてしぶとく残ってきたのです。彼女には、いつでもぴったり寄り添っているオスの子がいて、それがどうやら脱落せずにいられる秘訣のようでした。ちっ、ガキのくせに色気づきやがってよ。
メスの子に献身的に尽くしているそのオスは、目立ってたくましいというほどではありませんが、生き残り組みの中ではいちばん芯がしっかりしているように見受けられました。なにしろ、彼の意志がほとんど二頭分の生命を支えてきたのですから。オスの子のほうにとっても、そのメスの存在がなかったなら苦しいだけの長旅を耐え抜いてはこれなかっただろうということは、クジラとクジラとの絆の深さを知らない異端の種族であるドクガンには理解できませんでしたが。
そのオスの子を支えていたもう一つの要因が、母親のミンククジラと同行者のクジラたちでした。〈沈まぬ巌〉の災難以後、彼女たちの姿を見かけなくなったのは、ドクガンにとって何か噴気孔につかえていたものが取れたような気分でした。ミツマタを失うきっかけとなったそのミンクのメスは、ザトウとシロナガスばかりでなく、無敵の親衛隊にとっても唯一油断のならない相手である離れマッコウまで一味に加え、何度尾行をまいて突き放しても執拗に追いすがってきたのです。もっとも、〈運命の告知者〉の差し向けた刺客の化けホオジロをその歯クジラが一撃で粉砕したときは、予言者気取りの白いクジラの鼻を明かしてやったようで、ドクガンにはむしろすっきりしたくらいでした。
「〈告知者〉殿の予言もたまには外れることがあるんですかい?」
仰々しく能書きを付けて怪物を解き放ったところが、虚勢を張っただけの結果に終わった後、ドクガンは彼の連絡係に向かって皮肉混じりに訊きました。〈告知者の窓〉はどこからしゃべっているのかわからない虚ろな声で不機嫌そうに言いました。
「予定が変更されたのだ。〈脂の樽殿下〉のお気が変わられた」
「するってえと、連中を放っとかれるとおっしゃるんで?」
「〈殿下〉がメスミンクに関心を示されたのだ。私もマッコウのほうに興味がある」
「へえ。予言てのは変更がきいて便利ですなあ。外れくじを出さずにすむわけだ」
右目をクルリと回して蔑むように冷笑したドクガンに、〈告知者の窓〉は口を下に向けて鋭い歯をひらめかす歯クジラ特有の威嚇のポーズをとりました。
「黙れ! 時間の流れというのは主らの頭で想像できるほど単純なものではないわ! 低級種族の主らに説明してもわかりはしまいがな」
おやおや、さいですか。それじゃまあ、そういうことにしときますかね。だが、低級種族に向かって歯を剥くこたああるまいに、神経過敏な神官さんよ。カルシウムが足りないんじゃないのかね?
追跡者のナイト役を務めるマッコウに敗北を喫してからは、その〈告知者の窓〉も滅多に口をきかなくなりました。ただし、礼拝の日だけは別でした。親衛隊の本拠地では必ず週に一度、司祭でもある〈運命の告知者〉が、彼らの崇めるモノ・セティの偉大さやその教理について説教を垂れるのです。礼拝の日、ドクガンは親衛隊長としての手前、彼の脇に控えてしかつめらしくしていましたが、実のところ退屈で仕方ありませんでした。彼自身も部下たちに対してモノ・セティを引き合いにして説教することがありますが、正直言って彼にはモノ・セティを崇める気など全然なかったのです。モノだろうがジだろうがトリだろうが、あるいはメタだろうが、俺にとっちゃあどうだっていいこった。俺は神さんなんて信じやしねえさ。鯨生を享楽に送れりゃあ、それでいいのよ。
ドクガンと違ってうわべを取り繕って我慢することを知らないサカヒレは、礼拝のたびに「頭が痛くなった」と言って席のいちばん後ろへ行き、居眠りするか下っ端をいたぶるかメスにちょっかいを出すかしていました。フン、あの田舎者の大食らいは土台隊長になるだけの器量ってのに欠けてやがるのよ。よしんば俺がやつにポストを譲ってやる気になったとしても、あいつじゃあ三日も続きゃしねえだろうさ。ちっぽけな脳ミソで腹黒い考えを抱いたりしなけりゃあいいものを。
いつもではありませんが、礼拝の場に〈脂の樽殿下〉が姿を見せることがありました。このときばかりはさすがにサカヒレもおとなしく説教に聞き入っているふりをしています。彼ら新しい種族の首長たる〈大王殿下〉が盲いた目で彼の配下のクジラを見渡すときは、ドクガンでさえ落ち着かない気分になったものでした。右の視力は鋭いドクガンと違い、〈脂の樽殿下〉は両眼の視力を失っていましたが、どういうわけか響測音を出さなくても、見るのにも〝聴る〟のにも不自由しませんでした。〈脂の樽殿下〉にはほかにも、親がなくモノ・セティがじかに血をこしらえた──つまり生きものではないとか、いろいろと不気味な噂が流れていました。
ともあれドクガンとしては、〈告知者〉のくだらないおしゃべりから解放されるのが今回の遠征の唯一の利点だと思っていたのですが、その当ては外れてしまいました。彼が任務を忠実に履行しているか、あるいは妙な策謀を働きはしないか監視するためにつけられた〈告知者の窓〉を使って、勤勉な神官は休まず〝出張礼拝〟を続けたのです。ちくしょう、こんなところでまでお前さんのありがたくもねえ長話に耳を貸す羽目になるたあな。
「──会衆の諸君。勇猛機敏なる歯クジラの精鋭ならびに選ばれしヒゲクジラの幼子たちよ。今日は、モノ・セティが〈毛なしのアザラシ〉を創り、〈沈まぬ岩〉をしてわが鯨類諸族に差し向けたその真意について触れることにしよう……」
説教を始める前にいつも行われる、モノ・セティ信仰のメッカであり、遠征隊がいままさに帰途につかんとしている本拠地──〈モノ・セティの園〉の方角を真っすぐ向いて、弓なりに背中を曲げるペダンクルアーチの浮上潜水を五度繰り返す礼拝の儀式の後、紅目の話者は二つの種族からなる二〇頭余りの聴衆に向かって講釈をぶちました。
「さて、『モノ・セティ、すでに〈沈まぬ岩〉を備へおきてクジラを捕らしめたまへり』──
「〈沈まぬ岩〉を創られたのは、ほかでもない偉大なるモノ・セティである。愚かな〈毛なしのアザラシ〉どもは独力で作り上げたものと勘違いしておるようだが、無論彼らは単なる〈延長〉にすぎず、すべては彼女の御意志に従ったまでである。なぜ彼女は、唯一絶対の神であるモノ・セティは、我らが種族にかようにも過酷な試練を与えしめたのであろうか? それはほかでもない、我らクジラ族が選ばれた種族であるからだ。選民であるからだ。そして、その我らをして生のくびきから解き放つためだ。正しき道を示すためだ。
「海中を見渡してみるがよい! この混沌!! 無数の生命がひしめき合っておる。同じ種族、同じ個体は一つとしてないにもかかわらず、他に抜きんでる者はだれ一頭おらぬ。非同一にして同一だ。種々雑多にして、平等な屑だ。ガラクタの寄せ集めだ。独立独泳に存在しているものは一種族、一頭とてない。環境に、他に寄りかからずには存続できぬ。そのくせ、何にどう寄りかかっているかもろくにわからぬ。複雑怪奇な網の目にがんじがらめに縛られておる。だれもがくびきにつながれている。個も全も互いを排除できぬ。個は全のために、全は個のためになどと嘯いておる。その関係たるや、なんと醜悪なことであろう! 己が生を保つために他を殺し、他が生のために己れを殺す。延命と快楽を渇望しつつも、必ずやそれを奪わずに、奪われずにおれない世界。生きては死に、死んでは生きる……連綿たるこの繰り返し。変化のない変化。なんたる矛盾! なんたる欺瞞! なんたる不条理! どこに特別なものを見出せる!? 崇高なものがどこにある!? ありのままの世界とは、なんと意味のないことか! 価値のないことか! これがエネルギーと物質、時間と空間の浪費でなくてなんとしよう!? そして、このただ無に等しい自然の存在仕様を、すべてに需要せしめている許認しがたい神がおる。メタ・セティだ。
「なんの変哲もないメスクジラの姿を借りたこの者は、自らこそが世界をこしらえあげた神であると詐称し、すべての生きものどもをかどわかしておる。屑に等しい無知蒙昧の生きものどもは、彼女に唆されて生きることの幸福感で狭小な精神を満たしておる。ああ、生を謳歌する者どもの愚かしさよ! 自らの生が幾重もの屍を踏み台にしているとも知らず、明日は己が身がその踏み台のほうになるとも知らず。矛盾を矛盾とも思わず、自らをしてその矛盾を体現させられておるのだ。あろうことにも、彼らは〝単に生きること〟に虚しさを覚えることもなく、それを〝よいこと〟だと思いこんでおる始末だ! おお、おびただしい生命がただ意味もなくうごめいている様の、なんとおぞましいことよ! これが吐き気を催さずにいられようか!? 生があるから嘔吐があるのではないか? 彼女は生きものたちから、世界を疑い、否定し、抗う能力を矯めてしまった。だがそれも、我らクジラ族のように、世界をより深く知らんと欲し、押し付けられたその在り方を猜疑し、よりよきものとは何かを考察することのできる真の存在が登場するまでの間であった。
「そう、我らが出現するまでは、確かに世界がメタ・セティの統べる虚構であろうとなんらかまうところはなかったのだ。だれも疑問を抱ける者がいなければ、疑問は発生しないのである。それらはいわば、我らが存在を可能ならしめるうえで、手続き上必要な前駆的世界なのだ。モノ・セティは、この惑星をして我らを誕生させる孵卵の浜辺としてのみ創造なされたのである。メタ・セティはいわば、理想的世界が実現されるまでの間の当座の、かりそめの神にすぎぬ。そして、主役は舞台に登場した。機は熟したのだ。
「幾百万年もの間、我らクジラ族は万物の摂理について洞察する優れた頭脳を有しながら、メタ・セティの妨害によってそれを眠らされてきた。かの邪神メタ・セティはなおも虚無の世界を固持せんとして、厚かましくも我々に働きかけてきたのだ。すでに彼女のヒレには負えぬ知力と武力を備えてしまった我らをして、生あるものから未だ引き継いでいる負の遺産である感情と感覚を巧みに利用し、真理から遠ざけようとしたのだ。しかし、いくらメタ・セティが奸策を弄して我らを虚無の世界に押しとどめようとしても、いつまでも欺かれてくびきにつながれ続ける我々ではなかった。偽りの非存在の神であるメタ・セティは、いずれモノ・セティに駆逐される運命にあるのだ──」
あ~あ、やんなっちゃうなあ。ジョーイがふと隣を見やると、同じく顔をしかめてうんざりしているメルと目が合いました。
ジョーイにとって、メルはいまや妹リリの代役以上の存在になっていました。母のクレアが自分を助けだそうと後を追ってきていることを、彼はこれまでずっと感じ続け、それを心の綱としていました。とはいえ、現実に母に会うことがかなわぬが故に、一緒にそばにいてくれる存在というものもやはり必要でした。ジョーイもすでに一歳を迎え、本来なら母親から自立していなくてはならない時期でした。それでも、双子として大事に育てられながらいきなり引き離され、十分甘え足りなかったことによる思慕の念が、自分を慕い気づかってくれる唯一のメスとなったメルに、母親を代行するささやかな役割をあてがわせたのかもしれません。母との交信が途絶えたいま、ジョーイはメルとともにこの苦しい旅を生き抜くことに大きな目標を見出していました。
ジョーイは後ろにいる見張りのシャチに知れない程度に、わけのわからないことをしゃべって悦に入っている紅目のシャチのまねをして、口をモグモグさせました。メルはクスッと笑いかけましたが、あわててくしゃみをしたふりをしました。
要するに、神様にはメタ・セティとモノ・セティの二頭の神様がいて、メタ・セティはいい神様でモノ・セティは悪い神様なんだろ? この悪いシャチたちは悪い神様を信じていて、いい神様を信じているほかの生きものたちをやっつけようとしているんだ。でも、ぼくらはただメタ・セティが好きなだけなのに。拝め、拝めと無理やりに拝まされる神様なんて、だれも好きにならないよ。
ジョーイは母親のクレアや他のおとなたちから、メタ・セティを信じなさいと言われたことは一度もありませんでした。世の中には一般常識とは異なる信条を持つクジラがいて、自分たちの住んでいる世界は丸くなくて海はどこまでも平らなんだと言い張ったり、生きものの種族はすべてバラバラに生まれて進化なんてしやしなかったと思いこんでいる者もいます。だからといって、クジラたちは〈郡〉八分にしたりなどしませんでした。信じようと信じまいと、みんなクジラとして生きていることに変わりはないのですから。
こども心に、ジョーイはお母さんに、メタ・セティってどうしてメタ・セティっていうの? メタ・セティなんて本当にいるの? と何度か尋ねたことがあります。すると、お母さんは答えました。
「セティっていうのは〝クジラ〟、メタっていうのは〝~を超えた〟っていう意味よ。この〝超えた〟っていうのは、ほかよりもっと偉いとか、優れているとかいうんじゃなくて、そのものを一緒に含んでいる、包みこんでいるっていうことなの。だから、メタ・セティは〝クジラを超えたクジラ〟っていうこと。私たちには確かにクジラに見えるし、クジラだと思っているんだけど、メタ・セティはどの種族にもいて、それがみいんなメタ・セティなの、全部が全部よ。まあ、メタ・セティっていうのは私たちクジラが付けた名前で、本当はどうでもいいのよね、名前なんて。
「メタ・セティっていうのはつまり、〝世界がこのようにあること〟っていうこと。そして、〝私たちクジラという生きものがこのようにあること〟、〝私たち一頭一頭がそれぞれこのようにあること〟っていうことね。そして、それを〝いいな〟って思うことなの。私がこの世界に生まれてきてよかったな、私がクジラに生まれてきてよかったな、私が私に生まれてきてよかったなって。世界がこのようにあって、クジラがこのようにあって、私がこのようにあるってことは、みんな切っても切り離せないことなのよね。それで、特別な種族、特別なだれかさんというのはいないの。みんな同じ。みんな一緒。でも、だれもが特別で、だれもがただ一つ、ただ一頭だけしかいなくて、だれもが尊いの。不思議よね。その不思議がメタ・セティ。
「私たちクジラはメタ・セティのイメージや声を音や光で思い描くんだけど、ほかの生きものの多くは、生まれてよかった、今日という日を生きれてよかった、ありがとう、ありがとうって生きてる。それはもう、メタ・セティに感謝しているというよりも、メタ・セティそのものなの。だから、私たちはご飯のオキアミを食べるときも、生命を大切にありがたくいただかなくちゃなと思う。そして、そういう生命を自分も引き継いで、生まれてきてよかったって思えるような鯨生を送らなきゃって思うの。いつかは私たちも、そうやってサメやシャチに食べられたり、浜辺に打ち上げられたり、海の底に沈んで朽ちていって、小さな生命の芽を育てる。そうやってみんながメタ・セティを広めていく。どこにでも、だれの中にもメタ・セティがいる。もっとも、〈沈まぬ岩〉に食べられるのはちょっと納得がいかないけどね。つながりが見えてこないから。
「私はやっぱり小さいときにこのお話をお母さんから聞いたわ。お母さんもそのまたお母さんから聞いたんだって。そうやってこのお話は、ずっとずっと大昔から母から子へと語り継がれてきたのよ。だから、私もあなたに教えてあげてるの。だけど、それだけじゃないわ。いまだって私、メタ・セティなんて本当にいるのかしら? メタ・セティがなによ! とかって思うこともなくはないんだけど、やっぱりときどき感じることがあるの、メタ・セティを。だから、信じているのよ。
「例えば、だれか好きなクジラと一緒に並んで泳いでる。ふと横を見ると、そのクジラの背中に虹が踊ってるの。細波の悪戯で、ちょっとした光の加減で、ほんの一瞬。キラッと。すると、あ、いいな、素敵だな、うれしいなって思う。そのクジラは、え? っていう顔して私を見てる。それで、このクジラに逢わせてくれてありがとう、今日という日を生きさせてくれてありがとう、世界をこのように創ってくれてありがとうって思わずにはいられない。それが、メタ・セティ。
「例えば、友達とケンカ別れして拗ねてたとする。ふと見やると、波間で四頭の若いイルカたちが、長いくちばしを使ってチャンバラごっこをしているの。二頭ずつ組になっているんだけど、片っ方が負けそうになると組が入れ代わって、いつまでたっても勝負がつかないのよ。イルカさんは本当に遊びの発明の天才よね。もう見ているだけでおかしくなっちゃって。それまでいじけて何があっても笑ってやるもんかって一頭で不貞腐れてたのに、つい吹きだしちゃう。それに、そうやって仲間同士で楽しそうに遊んでいるのを見てると、ああ、いいなぁ、うらやましいなって思えてくる。そうして、自分もつまらないことにこだわったりしないで、友達と仲直りしてあんなふうに遊べたら、やっぱりそのほうがずっと気持ちいいなって、反省しちゃう。イルカたちは別に、私に見せるためにそこで遊んでいたわけじゃないんだけどね。つまり、そのとき、拗ねてた私の胸ビレの下をくすぐったのがメタ・セティ。
「本当に彼女は茶目っ気があって、気まぐれで、ときたま粋なことをやるの。どこにもいないじゃないかって思って、ふと目を向けるとそこにいる。世界を産み落としたっていうたいそうなクジラが、すぐそばで何気ない悪戯をする。みんなに全能のクジラって言われてるけど、決して全能じゃない。世の中にはいいことばかりじゃない。恐いことも、辛いことも、悲しいこともある。ときには、彼女が信じられなくなることもある。
「だれか近しい者がメタ・セティのお迎えを受ける。やるせない気持ちになる。そういうとき、彼女は一緒にそばにいて、ささやきかけてくれる。私には何もできないけれど、あなたとともに悲しみます。だから、あなたは元気を出して生きてくださいって。亡くなったクジラに思いを馳せたとき、ああ、自分は生きていかなくちゃって思う。自分が生きている限り、そのクジラとのつながりは切れずに残っている気がする。自分と一緒にそのクジラの一部が生き続けているような……。それもメタ・セティ。
「本当にいろんなことがあって、いろんな思いをする。いろんなことを感じる。水の中を自由に戯れる。美しいものを見つける。新しい生命を愛しいと思う。だれかを好きになる。いいことばかりじゃない。それらを全部ひっくるめて、生きててよかったなってつくづく思う。世界がありのままにありますよ。あなたは生きることに満足していますか? はい、満足です。これが、メタ・セティ」
このときジョーイは、母親の言うことをただ、ふ~ん、と聞き流しただけでした。でも、彼自身もやはりメタ・セティとの出会いを体験したのです。
それは、彼の生まれた〈抱擁の海〉でまだ春を待っていた頃でした。リリと二頭で、彼は一頭のウミガメを玩具にして遊んでいたのです。そのウミガメは大きく成長したメスで、二頭に向かってプリプリしながら言いました。
「私ハ何年モ何年モコノ大洋ヲ旅シテ回ッテ、コレカラヤットカワイイ卵タチヲ産ミニ生マレ故郷ヘ帰ルトコロナンデスヨ。アナタタチちびっこノ遊ビ相手ヲシテイル暇ハナイワ」
二頭は気の毒になって彼女を放しました。ところが、まだそのウミガメが視界から消えやらぬうちに、サメが一尾やってきて、彼女をお腹の卵ごと食い殺してしまったのです。
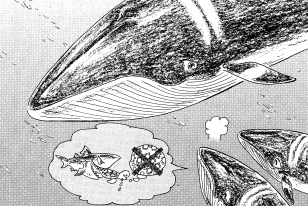 ジョーイはびっくりし、次いで茫然とし、最後に無性に腹が立ちました。カメを食い殺したサメを憎たらしいと思いました。何も長いことたいへんな旅をしてきてこれから卵を産みにいこうとしているカメさんを食べなくたっていいじゃないか。自然っていったいどうなっているんだろう。メタ・セティなんて本当にいるのか?……。憤慨した彼は、海面を胸ビレでさんざんたたきつけながら帰りました。そして、母にこのことを話しました。
ジョーイはびっくりし、次いで茫然とし、最後に無性に腹が立ちました。カメを食い殺したサメを憎たらしいと思いました。何も長いことたいへんな旅をしてきてこれから卵を産みにいこうとしているカメさんを食べなくたっていいじゃないか。自然っていったいどうなっているんだろう。メタ・セティなんて本当にいるのか?……。憤慨した彼は、海面を胸ビレでさんざんたたきつけながら帰りました。そして、母にこのことを話しました。クレアは、息子にウミガメの生涯に関して知っていることを語って聞かせました。ウミガメのメスは海で二〇年も三〇年も暮らした後、生まれた浜辺に卵を産みにいきます。夜になって浜辺に上陸し、産卵にふさわしい場所(母ガメは選定の際、砂の固さや温度から周囲の静けさ、明るさに至るまで細心の注意を配るそうです)を見つけると、後肢で砂を掘り返して、塩の涙を流しながら(カメたちも自分たちクジラ同様、悲しみの涙を流すことは生理的にできませんが、それは母親として出産に臨み、こどもたちの無事を祈るその気持ちとは関係ないのだ、とクレアは言いました)、百個から二百個の卵を産み、砂をかけ戻して再び海へ帰っていくのです(中には、生涯にたった一度しか産卵しない種族もいる、と彼女は教えてくれました)。そうして砂の中で卵から孵った仔ガメたちのほとんどが、陸の獣やカニ、カモメといった恐ろしい天敵に襲われて、海にたどり着く間もなく生命を落とします。海に入れば入ったで、今度は大きな魚たちが大顎を開けて待っています。結局、一頭のメスが産み落とす卵のうち、無事に大きくなって二、三〇年後にまた同じ浜辺に帰ってこれるメスは一頭だけです。さもないと海がカメであふれてしまいます。もちろん、平均で一頭なので、二、三頭の姉妹が生き残ることもあれば、全滅してしまうことだってあります。
でも……と母は言います。たとえ全滅してしまったとしても、それでそのカメの兄弟姉妹たちがこの世界から消されてしまうということではない。彼らの生命は、生き残ったカメたちが餌のクラゲなどを食べるのと同じように、ほかの生命に受け渡されていったのだ。母親が未来を託して一所懸命に生んだ生命は、次のカメの世代にこそならなかったけれど、海の中にずっと広がっていって続いているんだと──。
そのとき、ジョーイは感じたのです。あの母ウミガメと彼女の卵の生命を直接受け継いだのはサメでしたが、自分もまた、彼にプリプリと文句を言ったカメのおばさんと生まれ損なった百の仔ガメたちに生命をもらったのだと、そういう気がしてきたのです。彼女たちの分もぼくは今日を力いっぱい生きるぞ! そういう決心が湧いてきたのです。これがメタ・セティだったんだ。お母さんはこのことを言っていたんだ──このつながりのことを。ジョーイはメタ・セティを信じました。彼女を好きになりました。だれに強要されたのでもなく(カメとサメには教わったかもしれませんが)、自分で彼女の存在を感じとったのです。海で他の生きものと戯れるときも、それからは尊敬をもって乱暴に扱わないようにしました。
それに比べ、モノ・セティはというと……。
「──モノ・セティには、思考する能力をそのように埋もれさせたり誤った方向に使わぬよう、我らを正しく導く必要があった。そのために、彼女は自身に忠実な下僕を創り、我らに目を開かせるべく遣わされた。ほかでもない〈毛なしのアザラシ〉がそれである。彼らは自然に満足を見出せなくなった最初の種族である。メタ・セティに叛逆を企てる我らが同盟者である。無論、彼らは蔑むべき輩ではある。彼らは愚かしすぎて決して真理には到達しえぬ。彼らは我らに尾ビレの向きを転じさせんがためにのみ生み出されたのだ。
「〈アザラシ〉どもはまず、自らと自然的世界との間に差異を認め、己が種族を他の生物と異なる特殊な存在、能力に長けた優越した存在と考え始めた。彼らは他の生きものを彼らの享楽のために消費されるべき〝資源〟として新たに定義付けた。幼稚で些末ではあるが、世界と己れとに存在の意味と価値をもたらしたのである。彼らはメタ・セティの束縛を受けない己れらだけの独立世界を築かんと欲し、周囲の自然環境を卑しむべきところとみなした。雑然たる生のくびきを断つ試みは、しかし、成功しなかった。彼らには〈前肢の延長〉を製作して振り回す能力があっただけで、世界の構造を把握し、改革する英知をもたなかったからだ。彼らはただ、メタ・セティの勢力下にある虚無的自然に逆らい、打ち壊すことが可能であるという、展望を指し示したにすぎないのである。
「では、我々はいかなる秩序を構築すべきか? どこに真理があるのか? 意味とは、価値とは、何か? それは〝死〟である。死とは、超越である。死とは、絶対である。死とは、永遠である。死とは、美にして善である。これもまた、モノ・セティが〈毛なしのアザラシ〉をして我らに知らしめてくれたのである。ああ、〈沈まぬ岩〉に屠られるクジラの、海中に満ちわたる苦悶の波動よ! 聞く者を戦慄させる今際の咆哮よ! この日を待ち受けていたかのように躍動する血飛沫よ! ここに、生のくびきを断ち切った存在の強固さがある。互いに相矛盾しながら切り離せぬ関係にあるという醜悪さからの、高処への飛躍がある。次の生につながってまた混沌と無意味さの中に埋没し、だらだらと流転するのではない。これは虚無的世界からの脱却である。生のために死があるのではない。死としての死があるのだ。生と死の相克は、必ずや死の側の勝利に終わる。生は死に組み伏せられ、隷従し、その発現のためのプロセスとして低次のものに成り下がるのだ。
「ああ、銛の突き刺さるときのその苦痛! うめき! 叫び! 苦しみが生への浅ましい執着としてあるのではなく、死をより確実なものとし、完成させんがためにあるとき、それはなんと神々しく輝いて見えよう! おお、銛を突き立てられすでに息絶えたわが子を救わんと、なおも背に持ち上げようとする母親の献身よ! 傷ついた同胞を守らんと、死の提供者たる〈岩〉のもとへ我も我もと狂奔する友愛の美しさよ! だが、完璧なる死をおいてほかに誠の愛の発露される場があろうや!? 日常の怠惰な生の中に腐りきっていた愛が、いまここにひときわ光彩を放つのである。死が死を呼んでこそ、愛は永遠不滅のものとなるのだ! 死とはまさに不滅なるものへの回帰である。解悟であり、浄化であり、統一である。
「そう、すべては死に、死が死であることに帰着する。我らクジラ族こそは、メタ・セティの生ではなく、モノ・セティの死にこそ真に存在の証があることを知る最初の種族なのだ。我らはこのモノ・セティの偉大な教理を、完全無欠にして整然明快なる秩序を、矛盾と混沌に満ち満ちた自然界に敷衍していかなくてはならぬ。生に帰依しようとする者に、生に濁らされぬ純粋で尊厳に価する死をもたらしめよ! 可能な限りの苦痛をもて生を享受せる罪を懺悔せしめ、モノ・セティの永遠なる救済にあずかる資格を与えよ! 愛を成就せしむことを幇助せよ! 子を、親を、友を、連れ合いを死に導き、物理的肉体的連帯を引き裂くことで真実の愛に目覚めさせよ! 己が涙を殺してかように慈悲深くあれ……。そして、己れをして最高の死に到達しむべく鍛錬せよ! メタ・セティを神の座から引き摺り下ろし、モノ・セティを讃えよ! メタ・セティをおろがむ愚者どもにモノ・セティの祝福を授けよ! 生を辱め、死を尊べ! 生を蔑み、死を賛美せよ!!」
──彼らに死を! 我らに死を!
生命に死を! 全てに死を!……
〈告知者の窓〉に合わせて親衛隊のシャチたちも唱和しました。しかし、虜のミンクの子で一緒に歌っている者は一頭もいませんでした。やれやれ、やっと終わったぜ。まったくグダグダとくだらねえ御託を並べやがって。これじゃあサカヒレでなくたって居眠りしたくならあな。まだ一歳のヒゲ持ちのガキどもに、真理だの超越だのなんのと言ったところでわかりっこねえじゃねえか。
「なあ、坊主」
ドクガンは前の位置にいたジョーイに向かって声をかけました。彼が隣の彼女と紅目のシャチを茶化していたことなど、どんなにこっそりとやったつもりでも親衛隊長にはとっくにお見通しだったのです。
この恐ろしげな犯罪者の一団のボスである、ドクガンと呼ばれる隻眼の大シャチに呼びかけられ、ジョーイは振り向きました。不ぞろいな白黒模様やヒレの形を持つ恐ろしいシャチの集団に対し、ミンククジラの子たちは始め正視に耐えませんでしたが、何ヵ月も一緒に暮らしているうちに慣れてしまいました(慣れることのできなかった者は脱落していきました)。片目がつぶれてもう一方の目が大きく飛びだした、この最たる異容の持ち主にじっとのぞきこまれても、ジョーイはもう平気になっていました。彼らもやっぱり生きものには違いないことがだんだんわかってきたからです。
親衛隊でいちばん偉いらしいこのシャチは、奇妙なことにヒゲクジラのこどもたちにもよく馴々しげに話しかけてきました。ジョーイは中でも一目置かれていたようで、単に〝坊主〟というときはたいがい彼のことを指しました。にもかかわらず、この隊長は平然とイルカやラッコの群れを全滅させる指揮をとりましたし、虜の子や仲間が死んでも微塵も悲しむ様子を見せませんでした。気さくさと冷酷さをどうして併せ持つことができるのか、ジョーイには不思議でなりませんでした。が、余裕たっぷりで部下を好きに泳がせているように見せかけながら、裏切りを許す隙のない彼の性格が、親衛隊長として長く首をつないでいられる理由なのでしょう。
優れた能力を持つ冷酷無慈悲なこの殺鯨シャチたちは、一方で規律に縛られ、生命に対する感覚をマヒさせることに理由を付けて疑問を持たないようにし、本当に海を自由に泳ぐことができていないな、とジョーイには感じられました。海のエリート、親衛隊のシャチとして個性を埋没させることを潔しとしながらも、ときに彼らも一頭のクジラにすぎない側面をちらとのぞかせることがありました。ラングイのようなおっちょこちょいもいますし。
なぜ彼らは殺しに喜びを見出さなくてはいられないのだろう? 醜悪な容貌と限りない強さをヒレにした彼らは、生きものとしてごく普通の生き方に嫌悪を感じている、感じたがっているというふうに見えました。彼らはありのままの世界に溶けこめないばかりに、それを否定するために生を否定し、つながりを否定したがっているのではないか……。ジョーイにはそんな気もするのでした。別にそんな胸ビレ張らなくたっていいのに。おっかない顔やへんてこな模様だってだれも文句はつけないだろうに。ぼくらはどうせクジラには違いないんだから。生きものの社会は、本鯨に生きる意志さえあればだれだって受け入れるんだっていうことを知らないのかな。死の神様を拝んでクジラでいることをやめようだなんて、どうかしてるよ。改心して普通のシャチの仲間に一緒に入れてもらえばいいんだ。どうせ少しは肉を食べなきゃならないのは同じなんだし。ドクガンとラングイ二頭でコンビを組んで漫才でもやったら、当たると思うんだけどなあ……。
ドクガンにさえ投げやりな鯨生観を見出すジョーイでしたが、ただ一頭紅目のシャチだけは例外でした。その真っ赤な目をしたシャチは、模様や容姿は普通のシャチと変わりないのに、生きたクジラらしいところが全然感じられないのです。
「モノ・セティなんて嫌いだい……」
ドクガンの呼びかけに、ジョーイはブスッとして答えました。
ほお、俺でさえうっかり口にできねえ大胆なことを言いやがる。剛毅なガキだ。将来きっと大物になるぜ……大物?
「ハッハッハァ!」
突然ドクガンは、ジョーイやメル、ほかの隊員たちがびっくりするのも意に介さず大声で笑いだしました。かまわんから前進しろ、と胸ビレで指図しながら、彼はおかしくておかしくてたまらないというように腹を抱えて波間を笑い転げました。そうかい、そういうわけでしたかい、〈殿下〉。
さて、あともう一泳ぎ、二泳ぎで、くたびれきったミンクのガキどもをヒレ海産にした南氷洋遠征隊のご帰還だ──