二~四ノットの速さでグイグイと流れていく黒潮は、しかし、常に流路が定まっているわけではありません。大気圏に低気圧や高気圧があるように、海の中にも冷たい水や温かい水の塊が渦を巻いています。前線にあたるのが冷水と暖水との狭間である潮目であり、黒潮のような海流はその水の境目を流れていきます。生成と消滅を繰り返すそうした水塊の一つが、〈列島〉の南岸の遠州灘と呼ばれる部分にできると、黒潮はそれを迂回するために大きく蛇行します。クレアたちがここを訪れたのは、ちょうど遠州灘沖に一年半居座っていた冷水塊がしぼんでどこかへ蒸発してしまったときで、このため黒潮が〈列島〉の沿岸にかなり迫っていました。四ノットの水流に真正面からぶつかっていくのでは体力を消耗するため、四頭はなるべく陸際に接近する形で探索行を続けました。
いくつかの湾に探りを入れ、なだらかな浜をざっと〝聴渡し〟、彼らはやや海岸線の入り組んだ、南に突き出た半島のあるところまでやってきました。
「この辺も〈マッコウ食の岩〉が出ねえんだったら、住んでみるのも案外悪くねえかもしれねえな」水深半マイルを越える駿河と相模のトラフでイカをたっぷり頬張りご満悦のジャンセンが言いました。
「まったく、いい気なもんね」
奇怪なシャチの死体を発見して以降、ジョーイの消息を知る次のてがかりがつかめないでいるクレアは、他鯨の気も知らないで……とぼやきます。彼女たちは一つ手前の湾の近くで三〇頭のハナゴンドウのポッドとすれ違いましたが、彼らからも有益な情報は得られませんでした。ジョーイと彼を誘拐したシャチたちの行方を追って〈クジラ食の列島〉の海岸めぐりを始めてからすでに一月、秋分を過ぎて日没の時間も急速に早まっていました。
クレアたちが〈列島〉で最大級のその半島の東岸を南下し、黒潮の本流を目前に控えたとき、進行方向からけたたましいさざめき声が聞こえてきました。たくさんの潮吹きで海面が煙って見えます。それはバンドウイルカの群れでした。バンドウイルカはやや沿岸寄りに住む、いわゆるクチバシのあるイルカの仲間では最も大柄な種族です。彼らはクジラ族の間でも元気のよい愛嬌者として定評があります。
イルカたちはときに千頭を越える大きな群れを作りますが、群れのメンバーは入れ代わり立ち代わり泳ぎ代わりしていてかなり融通性があります。開放的な大きなグループの下には数十頭単位のサブグループがあり、これらの緊密なグループを中心に、休息したり、〈食堂〉にヒレを運んだり、ゲームをしたり、語らったり、あるいは小旅行に出かけたりしています。こうした群れは種族や〈大郡〉によって多少異なっていますが、主に成鯨前のやんちゃな若者イルカの学習グループと二つのおとなのグループに区別されます。成鯨グループの一つはメスが育児に専念するグループ、もう一つはペアの相手と蜜月期を過ごすグループです。というのも、メスは妊娠期間が一年、授乳期間がやはり一年以上あるからで、同じ性状態にあるメス同士で子育ての悩みを相談し合ったり、亭主の甲斐性のなさについて(イルカのオスはかなりの浮気者です)不満を漏らして憂さ晴らしをするわけです。イルカたちの行動パターンは、昼日中は岸に近いところで小グループに分かれて休み、夜間はやや沖合に出て深みでイカや魚を漁るのが大体一般的なところです。餌を採っているときには、見張りの役やベビーシッターを仲間が交代で引き受けます。
いま、八〇頭ばかりのバンドウイルカの群れは、黒潮に乗って楽ちんをしながら、餌の近海魚を追ってこの半島を回りこんできたところでした。切りたった断崖の多い半島の突端にある岬のすぐ沖には、水深百メートルほどの大きな暗礁があり、ここに乗り上げた潮は一気に奔流となって半島の東岸に流れこみます。そこに罠が口を開けて待っていることを、イルカたちは知りませんでした。
クレアたちとの距離がまだ離れていたとき、不意に沖合いに十数個の〈沈まぬ岩〉が出現しました。小型の〈岩〉たちは迅速に展開し、イルカの群れを半円形に取り巻きました。四頭にとってはイルカたちに声をかける暇もない、あれよあれよという間のできごとでした。
クレアが仲間に向かって注意を促そうとしたとき、海中にガンガンとやかましい騒音が響き渡りました。耳障りで頭痛を招き思考を著しくかき乱すその音は、以前出くわした〈騒音岩〉よりいくらかましといえ、今度はたまたま通りかかったクジラが巻き添えを食ったわけではありませんでした。十いくつの音源から発せられる不協和音は、明らかに一つの企図を持っていました。聴衆はイルカであり、獲物でした。
「ダ、ダグラス! これ、なんとかならない!?」
塞ぐことのできない不運なクレアの耳に、イルカたちの悲鳴も混じって聞こえてきました。
「なんだ!? なんだ!? なんだ!?」
包囲され、音で脅かされたイルカたちは、コースを変えることを余儀なくされ、次第に半島南端の岬から少し離れた位置に開いた小さな湾へと追いつめられていきました。獲物がしっかりと入りこんだところで、今度は〈ゴースト〉が導入され、湾の入口を仕切って退路を閉ざしました。脱出は不可能でした。八〇頭のバンドウイルカは、小型〈岩〉と〈岩〉から降りた〈毛なしのアザラシ〉に囲みこまれ、水深の浅いところに殺到しました。
「あ……!!」
湾の前面の沖で〈アザラシ〉の作業を注視していたクレアは、思わず叫び声をあげそうになりました。
「見るな!」
ジャンセンが一九メートルの巨体を滑りこませて、彼女の視界を遮りました。
「あ、あ、や……!!」チェロキーも目を飛び出さんばかりに見張って、ヒゲの生えた大きな口を戦慄かせています。
「若造、おめえもだ! 見るんじゃねえ!」
ジャンセンにも、目隠しをして胸の痛む光景を見せないことはできても、音ばかりはどうしようもありませんでした。ショックを受けて半ば放心状態となったクレアの耳に、頭部を打ち砕く鈍い音とともに、イルカたちのかすかなつぶやきが届きました。
「血が……」
「血が……」
「血が失せる……」
「血が失せていく……」
「血が……」
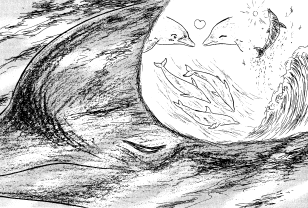 海面は見る間にまぶしいほどの紅色をした鮮血に染められていきました。自らの体内で生命の活動を支えてきた血液──水平線に向けた四〇ノットの疾走、虚空に向けた一〇メートルの跳躍、暗黒に向けた三〇〇メートルのダイブ、惑星のくれた巨大な玩具である土用波に軽々と乗ってサーフィンをした日々、水中にいながらも海面を上から見渡せたその奇妙な感覚、海に満ちる生きものたちの声、声、声、それらを一つ一つ聞き分け解読することのおもしろさ、仲間たちの皮膚の滑らかな感触、耳に心地よい歌声、自ら口ずさむ歌声、大きな類族との邂逅、無言で交わされる視線、風、雨、雲、陽光、自由、どこまでも青い水、愛を知ったこと──身体中を循ってそれらすべての経験を可能ならしめた血液、まだまだ思い出し足らない記憶を溶かしこんだ血液が、いま自らのもとを去り、水の中にどんどん広がって希釈されようとしているのを、イルカたちは意識の奥底に押しやられた苦痛の向こう側に見ました。刻々と増していく脱力感、体温はどんどん奪われていき、しびれるような感覚が襲ってきます。いままでクリヤーだった周囲の音が、頭の中でモヤモヤした固まりとなって渦を巻き、次第に濁っていきます。イメージがぼやけ、世界を彩る色が一つ一つ抜け落ちていき、最後に残ったのは赤一色のみでした。おい、なんで逃げていってしまうんだい?……君らがいるべきとこはぼくの中だろ?……海が真っ赤になるなんて、まるでこの世の終わりじゃないか……。
海面は見る間にまぶしいほどの紅色をした鮮血に染められていきました。自らの体内で生命の活動を支えてきた血液──水平線に向けた四〇ノットの疾走、虚空に向けた一〇メートルの跳躍、暗黒に向けた三〇〇メートルのダイブ、惑星のくれた巨大な玩具である土用波に軽々と乗ってサーフィンをした日々、水中にいながらも海面を上から見渡せたその奇妙な感覚、海に満ちる生きものたちの声、声、声、それらを一つ一つ聞き分け解読することのおもしろさ、仲間たちの皮膚の滑らかな感触、耳に心地よい歌声、自ら口ずさむ歌声、大きな類族との邂逅、無言で交わされる視線、風、雨、雲、陽光、自由、どこまでも青い水、愛を知ったこと──身体中を循ってそれらすべての経験を可能ならしめた血液、まだまだ思い出し足らない記憶を溶かしこんだ血液が、いま自らのもとを去り、水の中にどんどん広がって希釈されようとしているのを、イルカたちは意識の奥底に押しやられた苦痛の向こう側に見ました。刻々と増していく脱力感、体温はどんどん奪われていき、しびれるような感覚が襲ってきます。いままでクリヤーだった周囲の音が、頭の中でモヤモヤした固まりとなって渦を巻き、次第に濁っていきます。イメージがぼやけ、世界を彩る色が一つ一つ抜け落ちていき、最後に残ったのは赤一色のみでした。おい、なんで逃げていってしまうんだい?……君らがいるべきとこはぼくの中だろ?……海が真っ赤になるなんて、まるでこの世の終わりじゃないか……。ジャンセンとダグラスは、まだ経験が浅く血にも慣れていない二頭の年若いクジラを、押しやるように沖へと移動させました。八〇頭のバンドウイルカは水面をざわめかせ、ヒレをバタバタさせてもがき、血の潮を吹き上げながら、次第に弱っていき、その声は一つ、また一つと途絶えていきました。イルカの声がしなくなったのは、音の届く範囲を脱け出たせいか、それとも彼らが深紅に塗りこめられた湾の中で一頭残らず息絶えたからなのか、クレアにはわかりませんでした。
二頭の年配のオスは、岸が完全に見えなくなるところまでクレアとチェロキーを引き連れてきました。黒潮のただ中で、四頭は少しずつ東へ流されていきましたが、いまは水流が身を運ぶに任せることにしました。チェロキーはなんとか落ち着いてきましたが、まだ心臓から血が漏れ出さないか始終確かめていないと気がすまないようです。クレアは──こうやってじっと潮に身を委ねて瞼を閉じているうちに、流れが無慈悲な現実からどこか安全なところへ自分を運び去ってくれないだろうかと、ぐったりと疲れた心のうちでひたすらそれだけを祈っていました。早く帰りたい……〈豊饒の海〉へ、母の胎内へ……どこへだっていい、ここから出たい!! こんな世界から……。
四頭はしばらくの間言葉も交わさず、黒い波の列が陽光を浴びて上下しているのをぼんやりと眺めて過ごしました。沖合に出ると、数日前に通過した台風の影響で波は高くうねっており、巨体のクジラでも波乗りを安全に楽しむことができました。規則正しいリズムで赤子をあやすようにやさしく身体を揺すぶる波のおかげで、彼らの千々に乱れた心も少しずつ鎮まってきました。
ようやく自制心を取り戻したクレアが一言ポツリとつぶやきました。
「どうしてなのかしら? 私、わからない……」
南氷洋を取り囲む西風皮流帯を抜けたところで、殺鯨シャチたちによるハラジロカマイルカの群れの惨殺を目の当たりにしたときから、いつかもっと酷たらしいシーンを見せつけられるのではないかという予感をクレアも抱いてはいましたが、虐殺の現場に居合わせてその一部始終を目撃する羽目になろうとは思ってもみませんでした。そして、遂行者がシャチではなく、最近になってその存在を知った〈毛なしのアザラシ〉であったということも。
「すまんな、クレア。うっかりしておった。あそこには比較的古い中心的な〈岩〉の巣とセットになった〈血の浜〉があったんじゃ。わしもこれほど〈クジラ食の列島〉の沿岸に近寄ったことはいままでなかったもんじゃから……」ダグラスが弁解気味に言いました。
しかし、クレアは彼の言葉が耳に入らなかったように、どんよりと輝きの失せた虚ろな目で再度同じ問いを発しました。「どうしてなのかしら?」
しばらくして老鯨はまた答えを口にしました。「捕食者は、獲物にする動物の血に対して拒絶の感情を示すことはないよ。これは生物界の鉄則じゃ。シャチもサメもわしたちの血を見て騒いだりなどしないじゃろ。わしたちだって、オキアミの死体にいちいちショックを受けていたら、ノイローゼになってしもうわい。〈毛なしのアザラシ〉がイルカやわしたちクジラの捕食者と果たして呼べるかどうかは、また別問題じゃが……」
「ああ。俺だって、イカ殺しの前科を数えあげりゃきりがねえぜ。だが、イカの血を見てもぞっとはしねえ。もっとも、連中の血液の色は赤じゃなくて青だけどな。前にも言ったが、イカってやつは結構知能も高いんだよ。体色やボディランゲージで仲間と会話を交わしてるようだ。幸いにして、俺はイカ語はわからねえけどな。といって、契約違反をする気もねえ。俺たちは黙ってイカを食うし、連中も黙って食われる。連中にとって──そして俺たちにとってもだが──ありがてえことに、全イカ種族を合わせると、俺の体重の百万倍かそこらいるってえ話だ。連中の寿命は一年がせいぜいだが、一匹が数十から数百個の卵を産む。そんなわけで、俺たちマッコウその他の歯持ちクジラ、アザラシたちヒレ脚の連中、マグロとかの大型魚、海鳥なんかがこぞって養ってもらっている。イカイカ様様よ。だが、どっかの契約違反の常習者がイカをガバガバ獲りだしたもんだから、太平洋のスルメとかは昔に比べてがた減りしちまった。やつらは世界の方々の海でいろんなイカ族にどんどん食指を伸ばしていきやがる。その貪欲な連中とイルカが、俺たちマッコウクジラとイカのように、メタ・セティの引き合わせで食う食われるの契約書にサインをしたとは、俺は思わんね」
ジャンセンの言葉にうなずきながら、ダグラスが後を引き継ぎました。
「そういうことじゃ。わしたちヒゲクジラもオキアミとの間に契約がある。〝収獲期〟の四ヵ月以外はヒレをつけん。〈裏〉のシロナガス族は一属のオキアミしか食べぬ。セミクジラ族はもっと細かいカイアシやウミノミをえさに決めて折る。わしとクレアの種族が最も高緯度に、ナガスクジラ族はややそれより低い緯度に、イワシクジラ族はさらに北側に主要な〈食堂〉を持っておる。〈大郡〉によって、あるいは年齢・性別によっても食べ分けがある。自らの生活する海域で獲れるものに依存しておる。飢餓で汲々としているわけではないが、屠る能力があるからといって無闇やたらに殺しはせぬ。オキアミが減ってくれば、〈政を司る者〉がメスたちに繁殖を控えるように触れを出すじゃろうし、そういう時期に生まれた子は実際育ちが悪いじゃろう。それはいたしかたない。豊漁・不漁の差が激しいときは、雑食性の高い種族が調整役を買って出てはくれるが、それにも限界はある。〝食卓〟を囲む者同士、そして食う食われる者同士で痛み分けをするのがそうした場合のルールじゃ。
「じゃが、〈毛なしのアザラシ〉の活動は、そうした生物界の原則から明らかに逸脱しておる。イカばかりか、爆発的な繁殖力を持つはずのオキアミに対してすら影響を及ぼしておるくらいじゃからな。わしらが通り過ぎた二つのトラフに挟まれた半島は──クレアとチェロキーには内緒にしておこうと思ったんじゃが──実は〈イルカ食の半島〉と呼ばれておったんじゃ」
「まーったく、そればっかりなんですねえ」チェロキーが潮のため息を吹きます。
「まあ、わしらがクジラじゃからそういうふうに名付けておるが、他の生きものだってひどい目に遭ってそれぞれに命名しておるかもしれんよ。ともかく、その〈半島〉には百年ほど前まで一〇くらい〈血の浜〉が存在していたんじゃが、いまは残らず潰えてしもうた。理由は明白じゃ。イルカの獲りすぎじゃよ。ここで餌食になったのは主にスジイルカ族じゃが、彼らの犠牲者は一時期年に一万~二万頭を越える数に上った。おかげで、彼らの沿岸寄りの〈郡〉は徹底的に衰微し、〈政を司る者〉はメスに若いうちからペアを組ませ子育てを推奨して〈郡〉の復興に躍起になっておるところじゃ。
「それから、わしらが目前にした〈血の浜〉じゃが、昔は主にクジラが獲れぬときにコビレゴンドウの一族を追いこむ程度じゃった。じゃが、クレアが生まれたくらいのころから様相がガラリと一変した。ここの〈毛なしのアザラシ〉たちは、イルカと見るや誰彼かまわず歯牙にかけだしたのじゃ。コビレゴンドウのほかに、さっきの哀れなバンドウイルカ、東でも屠られていたスジイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、カマイルカ、マイルカ、オキゴンドウ、ハナゴンドウ、そしてシャチに至るまで。たまたま南方から訪ねてきた客鯨のサラワクイルカまで憂き目を見たという。殺害される頭数も急増した。しめてイルカたちの大グループ一つ分を一年のうちに呑み干しておる計算になる。
「あと、〈列島〉の西部の島々にも別種の〈血の浜〉があるそうじゃ。こちらの〈浜〉が顎門を開いて朱に染められることは散発的なようじゃが、イルカやゴンドウがブリを食べるのを、〈アザラシ〉が自分たちの餌を盗まれたと怒って殺すのだという話がある」
「ちっ、ふざけてやがるな。ブリをてめえらの占有物だと思ってるのか? 冗談じゃねえ、ブリはイルカのもんだ。いや、ブリはもちろんブリのもんだよな。大体、連中の一味の大食いの〈魚食〉が沖の魚を独り占めしてごっそり獲り尽くすから、イルカたちだって近寄りたくもねえ沿岸を〈食堂〉にせざるをえなかったんだろ。まあ、海も魚もクジラも自分のものだと思いこんでるやつらにゃ、痛み分けなんてする気ははなからねえんだろうが」憤ったジャンセンは、吐き戻したイカのカラストンビをぺっと口から飛ばしました。
「うむ。潮の流れがあり、そこに住む魚がいる。わしらクジラ族の仲間がいくら自由に移動できるといっても、実際に海で暮らしていくには、他のすべての生物種族同様自然の掟に従うしかない。餌の生きものが移動すれば自らもヒレを動かして追うし、食物がなおもヒレに入らなければ窮乏の時代が過ぎ去るのをじっと耐えて待つしかない。それでもわしらは生き続けてきた。いや、むしろだからこそ〈半島〉の〈イルカ食〉のようにあっという間に滅びることなく存続し、おおむね平和な時代を送ることができたのじゃろう。また、〈毛皮派〉のシャチのように、イルカやわしたちクジラのような大型動物の捕食者の地位に就いた種族は、獲物を狩る場合、群れの中で逃げ遅れた一部の者を選んで捕らえるのが流儀じゃ。決して獲物の血を絶やすことはない。ステラが〝誇り〟について話してくれたとおりな。ところが、〈毛なしのアザラシ〉は違う。イルカのポッドを一網打尽に全滅させる。マッコウのマスターをいともたやすく葬り去る。そうした能力を用いて、一つの種族を根絶やしにすることさえできる。君たちはステラーカイギュウという生きものを知っているかね?」そこで老鯨は二頭の若鯨に問いました。クレアもチェロキーも首を横に振ります。
「彼らは〈豊沃の海〉に住んでいたおっとりした菜食主義者の獣の種族じゃ。体長はクレアと同じくらいあって、主にケルプを食べておった。大きな図体ながら、争いごととはおよそ無縁な平和な種族じゃった。じゃが、彼らのことについてはもはや過去形でしか語れない。もともと多くはなかったけれども、彼らは〈毛なしのアザラシ〉に見つかってからわずか二十数年であっという間に食い尽くされ、滅んでしまったんじゃ。二百年ほど前のことじゃった。彼らの三分の一程度の大きさの親戚種族はまだ緯度の低い地方に生き残っておるが、その者たちも生存環境は年々厳しくなっておるようじゃよ。ほかにも例はある。この〈列島〉の裏の内海にいたアシカの亜種族も絶滅した。海に住むわしたちクジラの仲間は、種族としては分布域を広範に広げることができたから、幸いにも全種族が潰え去る事態には至らずにすんでおる。じゃが、〈郡〉単位で見れば、絶えてなくなったところは歯持ち族ヒゲ持ち族問わずいくらもあるし、現在危機に陥っているところも数多い。いずれの原因も〈アザラシ〉の存在を抜きには考えられん。
「どうも〈毛なしのアザラシ〉は、獲物であれ自分たち自身であれ、血を受け継ぐことの重要性を認識しておらんようじゃな。イルカたちは、メタ・セティとの取り決めを破らない限り〈アザラシ〉には対抗できないことを知っているし、彼らの気質に反する暗い鯨生を送りたくないので、〈血の浜〉のことは極力意識に上らせないようにしておるようじゃ。わしたちクジラがどういった社会生活を営んでいるか、海の中でどのように泳ぎ暮らしているか──例えば、イルカたちが成鯨するまでには一〇年かかり、メスは一頭の子に二、三年かかりきっているとか──ということを〈アザラシ〉たちは知るまい。その証拠に、イルカたちが岸寄りのコースを選択したのは海流の流路が変わったためであって、海の──メタ・セティの勧めに従ったまでなのに、〈アザラシ〉は来遊すれば来遊するだけ残らずたいらげてしまう。彼らがそんなプランクトン算式に増加できるはずがないことなど、よほど知能の低い動物でない限り簡単にわかることじゃ。いずれにしても、このような無茶を続けていれば、辛うじて存続している〈岩〉の巣も早晩自滅するに決まっておろうにな……」
黒潮のうねりの中で老シロナガスが吹き上げた噴気は、本来ならさぞかし荘厳で迫力のあるものだったでしょうが、いまは心なしかそのとどろきが虚ろに聞こえました。
「私、やっぱりなんでこんなことをするのかわからない。〈毛なしのアザラシ〉がわからない……」三頭の仲間を見つめるクレアの涙を流さぬ目には憂いがあふれていました。
「あのバンドウイルカたちの血は消えてしまうのね。身体を満たしていた温もりが消え、ポッドの血と友愛と歴史が時の流れから、海の生命たちの記憶の中から永遠に抹消されてしまうのね。もう取り戻すことのできない闇の中に、本当に、本当に消えてしまうのね……」
三ノットの海の急流に身を揉まれながら、クレアはさめざめと泣きました。フッと歌詞が思い浮かびました。悲しいときに、吹き払われたように空っぽになった頭の中に、クリヤーなイメージが湧き上がってくるのはどうしてでしょうか。クレアは名も知らぬバンドウイルカたちのために鎮魂歌を捧げました。
──もう血を流さないで!
お願いよ
大河のように 潮汐のように
駆け循ってきた赤い流れ
嬉しいことも悲しいことも
みんな溶かしこんできた
時を刻み、前進させる波動
身のうちに充満するエネルギー
世界を感じるたびごとに
絶えず新鮮さを増してゆく
肌を通して伝わる温もり
一頭一頭の胸にしまいこまれた秘めごと
それらがすべて外界に溢れ出し
水泡と消えるのを見るのが
私は嫌なの!
鮮やかな赤は躍動する生命の証
鯨目に晒さずに感じるもの
自分自身の生を感じるもの
だから、私は見たくないのよ……
もう血を絶やさないで!
お願いよ
幼い生命 老いた生命
みなを一つに結ぶ赤い糸
一頭一頭が滴となって
一本の奔流に混じり合うの
吹き上げる潮の和音
水流がみなの肌を等しく撫でていく
愛を確かめ合う二頭を包む祝福
今日も産声が伝える歓喜の波動
悲しみも苦しみも乗り越えて
連綿と受け継がれてきた
終わりのないはずのドラマの
幕が下ろされてしまうのが
私は嫌なの!
烈しい赤は確かな絆の徴
時の流れに同調するもの
言葉にせずに伝え合うもの
だから、私は見たくないのよ……
私に血を見せないで
海を血で染めないで
お願いだから
もう血を流さないで──
黒潮に乗って運ばれた歌は、果たして〈アザラシ〉たちの耳に届いたでしょうか?──