「フッフッフッ、種明かしをしようか、ジャンセン? だが、もう言わずともわかっただろう。構造的には歯クジラ族ならだれでも持っているものと同じなのだからね。いまのは超音波ビームだよ。ソナー音を収束するあれだ。もっとも、一般のクジラにはせいぜい魚やイカにちょっとショックを与えるくらいが関の山だが、私のソナーは絞りの性能からして凡鯨のそれとは出来が違うからね。出力を高めて焦点に音束を集約することで、目標物をいかようにでも料理できる。クジラを細切れに切り刻むことだってね」
「ちっ、ルール違反のヒレばかり使いやがって……」尊大ぶった〈運命の告知者〉に、ジャンセンが苦々しげにつぶやきます。
「ルールは一つ、勝ったが勝ちだ。私はあのディックなのだよ」
そこで白いマッコウクジラは、急にネコなで声に変わって黒いマッコウを諭そうとしました。
「ジャンセン、きみにもう一度だけ運命の潮路を通るチャンスをあげよう。私の部下になるのだ。きみに勝ち目はない」
ジャンセンは自分の運命を手玉にとったつもりでいる超鯨の敵をじっと見据え、自身も抑えた口調で答えました。
「俺は、クレアたちにはあんなことを言ったがな。本当はディックが〈沈まぬ岩〉との最終決戦の後、〈アザラシ〉とともに死んだとは思ってねえ。ディックは自分の運命に勝ったと信じてるのさ」
「ほう?」ディックの生まれ変わりを自称するクジラは、嘲笑の色をあらわにしつつ、興味深げに問いました。「では、彼はあの後どうなったのかね?」
「どうもしやしねえさ。彼はただのマッコウクジラに戻ったのよ。ただの白いマッコウにな。イカを食べ、潮を吹き、海流とともに旅をし、ただのクジラとして一生を終えたのさ。長生きはしなかったろうがな。あんたはディックの再来なんかじゃねえ」
「それが答えか?」
「そうだ。俺も同じさ。俺はただのクジラ、ジャンセンって名のただのマッコウのオスなんだ。俺は自分が心底自由でありてえと思ってる。自分がクジラとしてこの海に生を享けたってこと以外、どんな束縛にも甘んじるつもりはねえのよ。だからこそ、ほかの生きものたちの自由も奪いたかねえ。〈死の王国〉の副官になってえらぶるなんぞ願い下げだ」
二頭の対決者は射るような視線を交わしました。突然、ディックⅡ世は高らかに笑いだしました。
「ハッハッ! きみはおめでたいクジラだ! 実におめでたい! そうやって虚構のメタ・セティを信じながらあの世へ行くがいい。生存への関門はいま閉ざされた。ジャンセン、この私がきみの運命を告知しよう。あと一五分以内にきみは確実に死ぬ」
「おもしれえ、やってみろよ!」
言うなりジャンセンは、尾を強く打ち振って加速をつけました。その彼に、ディックⅡ世は頭を傾けて照準を合わせます。音の〝レーザー〟がパッパッと閃き、ジャンセンの航路を次々に断って背後に迫ります。いくらすばやく変則的に泳いだところで、秒速一マイルに近い音速にはかないません。発砲者はただ首を標的に振り向けるだけでいいのです。超音波の集中砲火を浴びせられ、ジャンセンの肌を切り裂く傷は見る間に増えていきました。
「こうなったら、やつの懐に飛びこむしかねえな……」
 敵のクジラの周囲を旋回していたジャンセンはいきなり向きを転じ、ディックⅡ世に向かって猛然と突っこんでいきました。激しいぶつかり合いに続いて、二頭のオスマッコウの戦いは組んずほぐれつの取っ組み合いへと移行しました。至近距離の肉弾戦となると、ミュータントクジラの新兵器もやたらには使用できません。二頭は全身の三分の一にあたる巨大な鉄槌のような頭を打ち鳴らし、下顎にズラリと並んだ凶器でもって皮膚を穿ち、破壊の意志を込めた尻尾でもって骨も砕かんとばかりにたたきつけます。ジャンセンはともかく超音波ビームを使わせまいとして、相手の身体にぴったりくっ付きながら、歯と尾と頭というノーマルな、彼の使い慣らした自前の武器を駆使しました。経験がものを言って、黒いクジラはわずかな身長差を補って白い超常クジラを相手に善戦していました。
敵のクジラの周囲を旋回していたジャンセンはいきなり向きを転じ、ディックⅡ世に向かって猛然と突っこんでいきました。激しいぶつかり合いに続いて、二頭のオスマッコウの戦いは組んずほぐれつの取っ組み合いへと移行しました。至近距離の肉弾戦となると、ミュータントクジラの新兵器もやたらには使用できません。二頭は全身の三分の一にあたる巨大な鉄槌のような頭を打ち鳴らし、下顎にズラリと並んだ凶器でもって皮膚を穿ち、破壊の意志を込めた尻尾でもって骨も砕かんとばかりにたたきつけます。ジャンセンはともかく超音波ビームを使わせまいとして、相手の身体にぴったりくっ付きながら、歯と尾と頭というノーマルな、彼の使い慣らした自前の武器を駆使しました。経験がものを言って、黒いクジラはわずかな身長差を補って白い超常クジラを相手に善戦していました。激烈な戦闘はクライマックスに達し、二頭は互いに上下になりながら相手の下顎をがっちりと挟みこみました。両者の牙が組み合わさって相手の歯茎に食いこみ、もう簡単には外すことができません。そこでディックⅡ世は、紅い目を細めて低いつぶやきを漏らしました。
「ククク、引っかかったね、ジャンセン君」
「ぁんだと!?」
視線を間近に交錯させながら、策略家のミュータントの参謀は勝利の笑みを浮かべました。「きみ、時計を忘れてやしないか?」
ジャンセンはハッと気がつきました。潜水を開始してからすでに一時間以上経過しています。深さ三マイル弱のこの地点まで潜るのに二〇分余り、帰りは一五分でなんとか海面にたどり着くとしても、もう浮上の準備にとりかからないと遅すぎます。
「フッフッ、きみたち並のクジラの潜水時間はどんなに頑張っても一時間半が限界だ。だが、私は三時間空気なしでこの深海にとどまることができるのだよ。さっききみの生命があと一五分だと言ったのはまんざら根拠のないことではない。もう一つの予言だ。きみは二度と空を仰ぎ見ることはない」
「くそっ!」
なんとかして敵の顎から逃れようと、ジャンセンは右へ左へ身体を錐揉み旋回させました。が、白クジラも彼にタイミングを合わせ、噛み合った両者の顎をねじり離そうという相手の試みを挫きます。ジャンセンの歯肉にディックⅡ世の鋭い牙がググッと食いこんできます。その先端は普通のマッコウに比べてずっと鋭利で研きがかかっていました。おまけに、彼には上顎からもしっかり細い円錐形の歯が生えていたのです。ジャンセンの口の中に次第に血の味が広がっていきました。その大半は自分自身のものでした。
ジャンセンは身体をくの字に曲げると渾身の力を込めて振り回し、遠心力がかかったところで回転を加え、どうにか両者の顎をもぎ離すことに成功しました。そして、水上を目指して全速で上昇を開始しました。もう水圧のことなど気にしてはいられません。顎の根元の部分が鈍痛を訴えます。ねじった拍子に関節をおかしくしたようです。距離を空けた途端、ディックⅡ世の容赦ない超音波攻撃が再開しました。出血量がどんどん増えていきます。あの野郎、たっぷり空気を補給して帰ったら覚えてろよ……。
そこでジャンセンは、ハッとなってブレーキをかけました。上だと思って突っこんでいった方向が暗がりになっていたのです。周囲を見回すと、蛍光照明が弱まり、透明度も落ちて海溝の景観は霞の奥にすっぽり包まれて見えなくなっていました。中長距離用のエコロケーションは依然として用をなしません。
「さあて、どちらが上かな? フフフ……」
白クジラの二つの紅い目だけが、濃厚な白い液体に満ちた空間で爛々と輝いています。ちっ、上と下もわからねえなんてとことんふざけた海だぜ……と、こんなところでグズグズしてるうちに時間切れでお陀仏になっちまうぞ。ジャンセンはかぶりを振って躊躇を振り捨て、いましがた進んできた針路を維持したつもりで直進しました。ところが、しばらく行くと額が何か堅いものにぶつかりました。
「てっ!」
「ハハハッ! どうした、ジャンセン。そっちは海底だぞ?」
ディックⅡ世は上下逆さまに身体を引っ繰り返しました。ジャンセンは視覚に、目に映った敵の体位にだまされていたのです。
くそったれめ! ジャンセンは自棄を起こして闇雲に突き進もうとしました。が、アクセルを踏みかけたところではたと思いとどまり、オーバーヒートしかかった心を冷ましました。落ち着けよ、ジャンセン。このお星さんの重心の位置は変わりゃしねえんだ……。彼は尾ビレを動かすのをやめ、脳油の密度を下げて軽くなった頭が生じた浮力に従って自然に導く方向へと、スピードを落として進みました。
「そら、逃げろ、逃げろ!」
嘲笑とともに無慈悲な超音波カッターを投げつけて、白クジラが彼を焦燥に駆りたてます。上昇を始めてからすでに一〇分が経過し、さっきの闘争でもエネルギーを費やしたジャンセンの筋肉は、そろそろ酸素の不足を訴えだしていました。ジャンセンは生まれて初めて、自分の上にのしかかる水の重みに恐怖を覚え始めました。呼吸を阻み、底へ底へと自分を押しやる一平方センチ当たり百キロ、二百キロもの水圧が、深海族のクジラらしくもなく実感されてきました。
それでも、肺の要求に応えて駆けだしたくなる気持ちを抑え、備え付けの自動浮上装置の働きを信じ、身体のきしみや内臓が裏返りそうになる感覚にも耐えた甲斐あって、やっと燐光の白さではない波の描く揺らぎが目に入ってきました。もうちょいだ──。
ところが……その波間から差す斜光に混じって彼に影を投げかけるクジラがありました。
「ハッハッ! 遅かったね、ジャンセン」
「!?」
ディックⅡ世がゴールの海面から勝ち誇ったように彼を見下ろしています。
「私は水圧の変化に対してもきみたちよりはるかに耐久力を持っている。海底から水面に上がるまでものの五分とかからぬよ」
歯ぎしりするジャンセンの行く手を、白いクジラが黒い影を投じて遮ります。かまわず体当たりするジャンセンでしたが、出血と酸素切れで、強敵を押し返すだけの力が絞り出せません。背中を押し付けられて、彼の身体は徐々に下降し始めました。鼻孔からいままで我慢してきた排気が最後の泡となって吐き出されます。
「終わりだ、ジャンセン! きみはよく戦った。私に歯向かった者の中で最も強かったオスとして、きみの名を記憶にとどめておくよ」白いクジラは勝利の宣言を下して高らかな笑いを海中に響かせました。
「いざさらば! さらばだ、ジャンセン君! モノ・セティの御胸に抱かれて、永遠の眠りに就きたまえ──」
「気に入らねえ、気に入らねえぜ──」薄れゆく意識の中でジャンセンはつぶやきました。「こんなくたばり方はよ……」
ドクガンは怒りの形相もあらわに、飛び出した右目で部下をねめつけました。
「これはまた一体全体なんのつもりだ、副隊長? 説明しろ!」
「てめえに説明する義務はもうねえんだよ」サカヒレは不遜な態度で答えました。
「そら、貴様らもとっとと部署に戻らんか! さもないと、隊規違反で降格か一週間飯抜きにするぞ? バカに付き合って、おまんまの食い上げになってもいいのか!?」
隻眼の親衛隊長は、副隊長の後ろに整列した一八〇名ばかりの隊員たちを怒鳴りつけましたが、だれもその場を動こうとはしません。
「ああ、その心配なら要らねえや。俺たちゃこれから上等のシロナガスをたっぷり頬張ることにしてっからよ」
ははあん……。よく見ると、反旗を翻した隊員たちはいずれも不満げな表情を浮かべ、ときどきシロナガスに物欲しそうな視線を送っています。ドクガンが賓客の応対に当たらせたのは(したがってシロナガスを食する機会を得たのは)エリートクラスの部下だったため、残りの隊員は下の階級に属する者ばかりで、後の連中はサカヒレと一緒にザトウを追わせた十数頭(すなわち、サカヒレに近いグループ)でした。
「なあ、お前ら。その頭にイルカよりマシな脳ミソが詰まってるつもりなら、よくよく考えることだ。一回くらいシロナガスを食いそびれたくらいで、その後の昇進コースを不意にしちまうのはどっかの大バカだけで十分だろ? 大体、こいつを二百頭で分配してみろ、一頭当たりスズメダイの涙しか残らんじゃないか。ほんの一欠けの肉じゃ、せっかくの上等のシロナガスを食った気にもならんだろ? ご馳走にありつきたきゃ、幹部入りをめざして日々精進を怠らず研鑚に励むこった。そうすりゃ、そのうち大物を思う存分味わえる。道理をわきまえろ、道理を。わかったか?」
「もうてめえのケチなごまかしのヒレは食わねえぜ。そのシロナガスの目方は百トン方あるじゃねえか。まあ一〇トンは俺の分だとしても、残りを分けりゃ一頭五百キロ近く行き渡るだろ。エリート風吹かしたいけ好かねえ連中に独り占めされるよか、ちっとでも分け前にあずかれるほうがマシだぜ」
おいおい、体重が百トンっつったって、そのうち食える正味がどれだけあると思ってるんだ? お前以外は骨と皮と脂身しか残らねえじゃねえかよ。ほかのやつも気づけっつーの。どいつもこいつも食い意地ばっかり張りやがって……。ドクガンは改めて、戦闘能力に関しては親衛隊ダントツの実力者であるが故にやむをえなかったとはいえ、サカヒレを副隊長のポストに当てたことを深く後悔しました。俺が留守の間、みんな算数の勉強をほっぽり投げてやがったな……。もっとも、一部の計算高い隊員は、抜け目のないドクガンより無思慮なサカヒレに取り入ったほうが旨味があると考えたのに違いありません。
「そういうわけで、俺たちゃもうてめえの指図には従わねえ。みんな、俺とてめえのどっちが隊長の座にふさわしいかわかってんだよ。てめえが一年も〈園〉を空けている間、隊長の座を放りだしたも同然だったってことに早く気づくべきだったな。本当はもっと穏やかに引継をしてやってもよかったんだが、てめえがそのシロナガスを独占しようだなんて意地汚え欲をかくからいけねえんだ」反逆者の頭領がニヤニヤして言います。
やれやれ、意地汚いのはどっちかね。たかがシロナガス一頭の肉くらいでクーデターをやらかそうとするやつがよ……。
「おい、サカヒレよ。こんなことが〈殿下〉のお耳に知れたらどうするつもりだ? 命令違反で獲物を逃し、〈王国〉を危機にさらしたうえに、反逆罪ときたもんだ。それも、〈殿下〉が〈王国〉の存亡に関わる大事な客鯨を迎えて取り込み中のときに、くだらん動機で要らぬゴタゴタを引き起こしやがってよ。こりゃ極刑間違いなしだな。きっと元素にまで還元されて灰も残らんぞ」
「御託を並べるのはよせよ。そのお客の相手で、いまごろ〈殿下〉も〈神官〉もヒレいっぱいさ。どうせあのミンククジラだかピンククジラだかもすぐにばらされて俺たちの晩飯になるに決まってらあ。どっちにしろ、これはいままでどおり俺たち親衛隊内部の交代劇なんだから、上級クジラも文句はねえだろうよ。俺はただてめえを引きずり下ろしにきただけさ」
ちっ、何もわかっちゃいやしねえ……。まあ、脳ミソが筋肉でできてやがるやつに何を言っても無駄か。苦々しげに頭を振って嘆く隊長の後ろでは、残りの部下たちも精鋭とはいえ、相手方の数のほうが十倍を越える状況で、難しい判断を迫られていました。オロオロする彼らに、クーデターの首謀者が誘いの声をかけます。
「おい、お前らも肩書きどおりちっとは頭が働くんならこっちへ来いよ。自分らだけシロナガスを食いっぱぐれたかねえだろ?」
二頭の上官の間で板挟みにあった十数頭のシャチは、困惑の表情を浮かべて両者を見比べました。が、中の何頭かは隠れるようにコソコソと後ろ側を回って頭数の多いほうへ席を移りました。ハナジロをはじめ残った者たちも、不利な形勢の組に加わってしまった自らの境遇を呪っている節がありました。
「ようし、お前たちはなかなか利口だ。残ったやつに比べりゃな」
ドクガンはドスを効かせた低いグランツ音で反抗する部下たちに向かってうなりました。
「そうか……お前らは本気で俺に逆らうつもりなんだな? いいだろう。だが、一つ覚えておけよ。俺は裏切りを決して容赦しねえ。飯の食い上げくらいで済むと思ったら大間違いだぞ……」
「負け惜しみはよせよ。自分の置かれた立場がわかってねえんじゃねえか?」
もはや新隊長の座をヒレに入れたも同然のつもりでいるサカヒレを、地盤を失いますます窮地に立たされたドクガンは忌々しげににらみつけました。こいつはひょっとして一世一代のピンチってやつか? 俺の打ちたてた親衛隊トップの在任記録は、このド阿呆のおかげで一年ぽっちでストップしちまうのか? え、ドクガンさんよ? いや、もちろんそんなことにはならんさ……。彼は一潮吹くほどの間思案してから、政見転覆を目論む反乱軍のリーダーを挑発しにかかりました。
 「で、俺をどうするつもりだ、サカヒレ? 多勢に無勢で、そいつらに袋叩きさせようってんじゃあるまいな? それとも、まさか貴様はそんな弱虫で意気地なしの卑劣漢だったのか? その逆向き背ビレと同じで、こけおどしの虚勢を張ることしかできんのか?」
「で、俺をどうするつもりだ、サカヒレ? 多勢に無勢で、そいつらに袋叩きさせようってんじゃあるまいな? それとも、まさか貴様はそんな弱虫で意気地なしの卑劣漢だったのか? その逆向き背ビレと同じで、こけおどしの虚勢を張ることしかできんのか?」「なんだと!? てめえと一緒にするんじゃねえ!」
怒りと不揃いの歯を剥き出しにする短気な大シャチに、ドクガンはほくそ笑んで続けました。「なあ、サカヒレよ。ここはシャチ親衛隊の名誉を汚さぬよう、紳士的に優劣を競うとしようじゃないか。親衛隊長のポストはいったん返上しよう。俺とお前との一対一の決闘で、勝者のほうがその座に就く権利を獲得する。もちろん、敗者をどう扱おうと自由だ。その代わり、ほかの連中は一切ヒレ出し無用、破った場合は反則負けってのでどうだね? 俺たちが因縁の決着をつけるにふさわしい、実に騎士道精神にかなった提案だと思うがな」
「望むところよ!」
脇にいた彼のブレーンの部下が、奸智に長けた敵対者の策略に注意を促しますが、ドクガンに唆された単純で意地っ張りのサカヒレは耳を貸そうとしませんでした。これだから、図体ばかりでかくてオツムの足りないやつをあしらうのは楽なんだよな。
「おい、老いぼれシロナガス。饗宴はしばしお預けだ。そこで見物してな」
ダグラスに向かってそう言うと、ドクガンはサカヒレとともにシャチたちの輪の真ん中に躍りでました。
二百名の隊員一同は親衛隊最強の二頭を取り囲み、これから始まろうとするデスマッチの観覧席に着きました。
サカヒレのコーナーで一頭のシャチが騒いでいました。ラングイです。
「親分、親分! あの生意気な片目野郎をケチョンケチョンに伸したってくださいよ!」
「おい、ラングイ。ずいぶんな言い方だな。貴様みたいに無能な落ちこぼれ隊員でも旅の間中目をかけてやった温情を忘れたのか?」ドクガンがきっと彼に右目を向けます。
「黙れっ!! いままでよくもさんざん俺をバカにしてくれたな! この頭でっかちのトックリクジラみたいな醜雄め! だが、親分がこの場でお前をたたきのめしてくださるぞ! いいか、お前はずっと俺のことをホヤだのナマコだのマンボウだのとけなしてきやがったが、俺はしっかりお前の弱点をつかんでるんだ! 俺を見くびったばっかりにお前は自ら墓穴を掘ったんだぞ! ハッ! そうとも、いまに泣きっ面を見るがいい!!」ラングイはこれまでの恨みを晴らさんとばかり、濁声で口角泡を飛ばしてまくしたてました。
「ふん、弱いオットセイほどよく吠えらあ。俺の弱点を見抜いただと? ほう、それじゃあその成果とやらをとくと拝ませてもらうとするか、デバガメスパイ殿の親分さんに」
「あ~~っ、そうやってまた俺のことバカにするぅ!!」
うるさい場外を放っておいて、二頭のシャチはいずれかが死ぬまで続けられる一本勝負に入りました。互いに顔を下に曲げて歯列を見せる威嚇の姿勢で対峙していた二頭のうち、先手必勝型のサカヒレがまず飛び出しました。一〇メートルを越える身体ごとぶつかっていきます。上下にそれぞれ約五〇本ずつの鋭く尖った牙を剥き出して襲いかかります。ドクガンも真赤な口をクワッと開いて応酬します。二頭分の黒白模様が入り乱れ、逆巻く渦と沸きたつ泡の中で、殺戮者のシャチたちは揉み合いながら互いの肉を食らおうとしました。獰猛な衝突エネルギーが鮮烈な血を飛散させます。二百頭の隊員は、新たな彼らのリーダーを定める戦いを、興奮と緊迫感の坩堝の中で固唾を飲んで見守ります。
最初のうち互角と思われた潮吹きも切らせぬ戦闘も、時間が経つにつれて次第に優劣の差が見えてきました。体力のサカヒレは、やはりパワーとスタミナの点で知力のドクガンを凌いでいました。サカヒレは一方的に攻め手に回り、対するドクガンは防御に徹するようになりました。ハナジロたちはいまから、後でどうやって新隊長に取り入ったものだろうと思案に暮れていました。さらに何頭かが勝算の高い側の応援席に移動しました。
「ぐわっ!!」
一瞬の反応の遅れが痛烈なダメージをドクガンに与えました。彼の突き出た右目の上何ミリと離れぬところをサカヒレの歯が切り裂き、鮮血が血走った眼球を覆いました。顔面の右半分にくっきりと歯列の痕を残しながら、ドクガンは頭を振り振り後退します。
「ぬおっ!? 目、目が……!」
「やったぜ、親分!! 見たか、デメエソ野郎め! それがお前の弱点だ! お前の左目が完全に視力を失ってることはとっくにバレてんだよ。お前の行動をしっかり見張ってきた俺の観察眼のおかげでな。右目に攻撃を集中して塞いじまえば、あとはもうこっちのものよ!」ラングイがしてやったりとばかり叫びました。
「くそっ……。だが、俺が地獄耳で通ってるのをよもや忘れちゃいまいな、サカヒレ? 視力を奪われたところで俺にゃ痛くも痒くもないぜ」
「果たしてどうかな?」そう言ったサカヒレの口調は自信にあふれていました。
耳をすましていたドクガンは、不意に対戦者の周囲を取り巻く渦の立てる音が消えたので、うろたえた声をあげました。「む? ど、どこへ行った、サカヒレ!?」
「俺はここだ!」
ドクガンが振り向く間もなく、サカヒレは彼の噴気孔の後ろに尻尾の殴打を見舞いました。首筋をしたたか打たれて隊長はつんのめりました。目眩から立ち直ると、再びサカヒレは姿を消しています。
「どうだ、〝聴た〟か? てめえの自慢のその地獄耳とやらに対向するために、俺はてめえの留守中に日夜訓練を積んできたんだ。皮膚の波打たせ加減によって巻き起こる水流の立てる音を完全に相殺する忍び泳ぎの究極泳法、水遁の術のな」
途切れ途切れに話す間にも、ドクガンに居場所を悟られないよう位置を変えながらサカヒレが続けます。「どうだ、俺様の術を〝聴破れ〟るかな? 狭角の短距離ソナーなら、俺の軌跡を追うことはできねえ。広角の中距離ソナーなら、位置を突き止めたと思った日にゃてめえの喉元を掻き切ってるぜ」
ドクガンは躍起になってソナー音を発しますが、サカヒレは流れるような身のこなしで攻撃に移る隙を与えません。イワシの群れを襲うカツオのように、彼は獲物の身体を一噛み一噛み傷つけて弱らせていきました。そのうちドクガンの体表は、黒白の斑に加えて赤の占める面積がどんどん広がっていきました。隊員たちの目にもすでにいずれが勝利者かははっきりしてきたため、サカヒレが敵を強襲してその肉を剥ぎとるたびにエールを送ります。ドクガン側の応援席は三頭にまで減っていました。
抵抗する気力も果てたのかぐったりしたままのドクガンに向かって、もはや自らの優位を確信して疑わないサカヒレは、破れし者への侮蔑を込めた弔辞を贈りました。
「さあて、そろそろとどめを刺すとするか。まあ安心しな、ドクガン。俺様が最強の親衛隊長としててめえの後を継いでやっからよ。心置きなく地獄へ堕ちな!!」
このとき、サカヒレは一つの過ちを犯しました。血まみれの大目玉のある右目からではなく、失明しているはずの左目の側からドクガンの脇腹へ接近していったのです。いつも自分をギョロリとねめつけてきた冷酷な視線を避け、かばうようにしていた死角の左側から行ったほうが無難だろうと、無意識のうちに判断したのでしょうか。しかし、この選択が、サカヒレにとって己れの生死を分かつ決定的なミスにつながりました。
攻撃者が身動き一つしなくなった同輩の獲物の心臓に牙を立てんとした刹那、その獲物はいきなり振り向いて彼の下顎をガキッとくわえこみました。
「うごっ!?」
ドクガンは相手の脂肪の詰まった顎の骨を髄までしっかり噛み砕かんと、容赦なく力を込めました。白い顎を真赤に染めてサカヒレは後退します。
「バカめ! いつ俺の左目が完全に視力がねえと言った? せいぜい能なしの子分に感謝するんだな。土台貴様は隊長の器じゃねえんだよ。いくら部下の前で魁偉をてらっても、随一の馬力を誇っても、常に相手の一泳先を読み、相手に先を読まれねえだけの機知と周到さを持ち合わせてなきゃ、やっぱり他鯨の上を泳ぐ地位には不向きってことさねぇ」
ドクガンがいつも左目をかばっていたのは、視力がないのを隠すためではなく、明暗を感知する能力があることを部下たちに悟られないようにするためでした。それがいま、この親衛隊長の座をかけた決闘の場において役に立ったというわけです。彼がサカヒレの攻撃をかわしもせずにぐったりと弱ったふりをしていたのも、油断させて水遁の術に頼るまでもないと思わせるためでした。そして、意気ばかりで用心を知らないサカヒレが、最後のとどめを刺す前にわざわざ親切にそのタイミングを教えてくれるだろうということも、彼は計算済みだったのです。
「サカヒレよ、俺が貴様の立場だったらもっとスマートに抜かりなくやっていたぜ。自分の屁っぴり腰の泳ぎ方に酔い痴れて、たかが視力を減じただけで満足してやしねえさ。いいか、本当に相手を打ち負かしたいと思ったら、こうやるんだよ!」
退化した外耳に代わって音の受信機の役を務める下顎を破壊されたサカヒレは、いまや耳が聞こえなくなったも同然でした。対するドクガンは、目を滴る血に塞がれていても地獄耳のほうは健在です。そして、水中の世界では聴覚は視覚よりはるかに重要なのでした。苦痛と外部からの音が断たれたことに対するパニックとで水遁の術をすっかり放棄してしまったサカヒレに、ドクガンは慎重に近づくと、敵の次善のほうの感覚機能を奪いにかかりました。
「ぎゃあああっ!!」
ドクガンはミスのないよう左右の眼球に深々と牙を突きたてました。これでサカヒレは光も音も失ったことになりました。先ほどとは立場が逆となり、今度は無闇に暴れまわるだけの獲物を、ドクガンのほうがいいように料理していきました。数分後には、一時ほとんど権力の座を掌中に治めかけた副隊長は、一〇メートルの肉塊となって波間を漂っていました。
風前の灯の状況から予想外の大逆転によって返り咲いた現職の隊長に、いずれも機能不全の、血糊に覆われた大目玉と不気味な光を放つ小さな目玉とでゆっくりと見渡された二百名の隊員たちは、身の縮む思いで上官の厳命を待ちました。
「ハナジロ、珍しく度胸の要る正しい選択をしたじゃねえか。新副隊長に任命してやろう。残りの二頭も昇格だ」
もう一分もしたらサカヒレの側に鞍替えしようと思っていたところだったハナジロたちは、自分の幸運をモノ・セティに感謝し、ホッと胸をなで下ろしました。
「それからと……あのかしましいバカはどこへ行きやがった?」
列の後ろのほうに隠れていたラングイを、ドクガンに取り入ろうとして他の隊員たちが前へ押し出しました。
「なあ、お前、さっき俺に向かって何か喚いていたな。トックリクジラがどうしたとかデメエソがどうしたとか。ありゃあ、いったいなんだったんだ?」
「あ、いえ、つまり、あれはそうじゃなくてですね、ドクガンの親分はトックリクジラなんかと全然違ってとってもハンサムだなあって言ったんですぅ。アハ、アハ……」
「貴様、最後まで親分つう口癖が抜けなかったな。ふざけた野郎だ。俺が地獄耳と呼ばれるもう一つの理由を教えてやろうか? 聴覚記憶の長期保持力、つまり一度耳に挟んだことは絶対に忘れやしねえんだよ! そんなにハンサムがよけりゃ、貴様も歯並びを矯正してもっと見れる顔にしてやる! ついでにそのおしゃべりも二度とできないようにしてやるわ! おい、そいつの乱杭歯と舌を全部引っこ抜け!!」
「ひぃ~、お助け~~!!」
続いて、親衛隊長は残りの二百名弱の隊員に向かってきっと盲いた目を向けました。
「さて、将来隊長をめざしたいという諸君に、一つためになることを教えてやろう。自分のポジションが有利な間、相手がダメージを受けてるうちにやっつけろ! だが、俺はもう立ち直っちまった。残念だったな、フフフ……。ところで、さっきも言ったが、俺は背信を許さぬ性格だ。かといって、せっかくここまで育てあげてきた二百名もの精鋭をゼロにしちまうのはもったいねえ話だし、それでは〈脂の樽殿下〉もお困りになるだろう。そこで、だ……。隣の者と二頭ずつ組を作って向き合え!」
シャチたちは上官に言われたとおりにしました。
「いま目の前にいるやつを殺せ。生き残ったほうはヒレに穴を開けるくらいで勘弁してやる」
互いに同じ境遇に置かれて怯えの感情を共有していた者たちの視線が、みるみる憎悪と敵意に変わっていきました。観戦者と対戦者との立場が入れ替わり、ドクガンは一頭で悠々と百のバトルを楽しみました。全身に傷を負い、目まで流血に覆われながらも、冷酷非道なミュータントシャチのボスはニタリと口を開いて、いましがた倒したばかりの裏切者の血にあふれる口腔と牙をひけらかし、もう一頭の傍観者に声をかけました。
「待たせたな、老いぼれ。あと少しで宴会を再開してやっからよ」
強力な捕食者でありながら同族内でいがみ合うことの最も少ないといわれてきたシャチの一党の血で血を洗う争いに、ダグラスは海面の一点をじっと見つめて嘆きました。
「ああ、なんたる醜態! なんたる痴態! わしのクジラ族の歴史が、このような醜悪な一ページをもって最後の章を閉じようとは。トホホホ……」
クレアは愕然として、下顎をわななかせながら累々と積み重なる知鯨、友鯨たちの亡骸を見つめました。ヒレをゆっくり動かしてそろそろと進みます。と、死んでいるとばかり思っていたクジラたちがむくっと身を起こしました。見開かれた瞳はみんな紅色を帯びていました。生気のない紅い目をした、自分のよく見知っているはずの仲間たちに対して、クレアは一瞬背筋の寒くなるのを覚えました。みなは海底を離れて浮かび上がると、彼女のほうへいっせいに紅い視線を注ぎました。クレアは前進をやめ、反転して逃げだしたくなる衝動に駆られました。
紅目のチェロキーが言います。
「アネさん、生きてたって世の中つれないじゃないですか。恐い思いや、嫌な思いや、辛い思いをするだけっすよ。〈詩鯨〉として名と作品を残せばそれでいいじゃない? 一曲歌ったら、後はパーっと散りましょう。パーっとね」
「違うわ……」クレアはかすかに首を横に振ってささやくように言いました。「違うわ」
紅目のダグラスが言います。
「のう、クレアよ。真に意味をなすものは種族の歴史じゃ。歴史の前では、個々のクジラの生存の可否など重要でない、矮小なイベントにすぎなくなる。では、歴史とはなんじゃろう? それは、死の集積にほかならぬのではないかな? 種族の偉大なモニュメントを築く礎石の一つとして、わしたちも歴史に参加するべきだと思わんかね?」
「違うわ、違うわ!」クレアはより強く首を振り、より大きく声を張り上げました。
紅目のジャンセンが言います。
「俺は生きてえ、生き延びてえっていう欲望がどうも気に入らねえな。大体よ、日々生存闘争の崖っぷちからほかのやつを蹴落としといて、自分だけ這い上がろうなんてのは根性が曲がってやがるぜ。おい、クレア、そうは思わねえか?」
「どうしてあなたたちはそうやって私を苦しめるのよっ!」クレアは激しく首を振り、半泣きになって金切り声をあげました。
紅目のイルカたちが燐光に輝く水面を飛び跳ねます。いつものように意気揚々として生を謳歌するのではなく、整然と並んで厳かな死のリズムに乗って放物線を描きます。
「死! 死、死、死! 死、死、死、死、死! 死、死、死、死、死、死、死──」
紅目のコククジラたちが頓狂な歌を口ずさみながら、行列を作って通り過ぎます。
「いてまえ! いてまえ! いてまえ!」
「世の中ちっともおもろない」
「いてまえ!」
「あの世やったら仰山おもろいことありまっせ」
「いてまえ! いてまえ!」
「一度死んだら二度と苦しまんですむで。ゴカイもヨコエビも食べ放題や。腹がパンクするまで食えますがな。パンクしたかてまだくえる。一度死んだらもう死なん。何も恐いもんなしや。ちゃいまっか?」
「いてまえ! あんたもいてまえ!」
紅目のハイイロミズナギドリが、けたたましく鳴きながらクレアの頭上を旋回します。
「セイゼイオ大事ニ、セイゼイオ大事ニ、セイゼイオ大事ニ、キャラキャラ──」
紅目のダンダラカマイルカのオスが、宙にジャンプしながらクレアのことを罵ります。
「へっ! ミンクかい。次はお前らが〈沈まぬ岩〉に滅ぼされる番だぞ、ざまあみろ!」
今度は紅目のイシイルカの群れが海面を飛び跳ねるようにしてやってきました。
「〈ツキンボ〉が来るよ!」
「わーい、〈ツキンボ〉だよ!」
「ぼくらを殺すよ!」
「わーい、殺されるよ!」
「うれしいな! うれしいな!」
「ぼくらを滅ぼすよ!」
「わーい! わーい!」
「楽しい〈ツキンボ〉だよ!」
「滅びの日まであと幾年!」
「滅びの日まであと幾日!」
続いて、ユラユラとうごめく〝聴えない〟壁にかかった海の生きものたちの死骸が視界に入ってきました。〝死の壁〟=〈ゴースト〉でした。おびただしい苦痛の並ぶ〝死の通廊〟を通るクレアの目に、大きな影が一つ飛びこんできました。ミナミトックリクジラの幼い子です。彼女が急いで近寄ってみると、その子は噴気孔がほんのわずか水面まで届かなかったばかりに、すでに潮吹きをやめていました。と、その事切れているはずのミナミトックリの坊やがパッチリと瞼を開きました。紅色の目でした。
「シ──」
クレアは〈黒い脂〉のただ中にいました。ラッコが、海鳥が、魚が、アザラシが、うめきの海にもまれて悶えていました。無数のうめき声の大合唱です。
「生命はなくなるよ」
「生命はなくなるの?」
「生命は死になるよ」
「生命は死になるの?」
耳に流れ入ってくる絶命のコーラスを聞くまいとして、クレアはほとんど絶叫に近い声で叫びました。
「もうやめて!!」
苦悶の歌声に満ちた海域から逃れようと、クレアは必死で尾ビレを打って泳ぎました。どんよりと黒ずんだ海の色は、いつのまにか見目も鮮やかな深紅に変わっていました。
「血だ!……」
「血だ!……」
「血だぞ!……」
「血!……」
目の紅いバンドウイルカたちが、自らの体内から流れ出た血に咽返りつつ狂喜しています。クレアは思わず瞼を閉じ、闇雲に駆けだしました。血の海を脱け出して再び周囲が白い海に戻ったところで、ふと面を上げると、美しい白黒模様の描かれた流線型の姿が目に入りました。
「シャロン!! 助けて、お願い!」
シャロンは紅色の目で射るようにクレアを見据えながらまっすぐ近づいてきました。
「私の母、〈毛皮派〉なのよ──」
紅目のシャチは真赤な口をかっと開いて獲物のクジラめがけて突き進んできました。クレアの全身を戦慄が駆け抜けます。
「クレア、私のために死んでちょうだい! お友達でしょ?」
「いやあっ!!」
襲ってきたシャチの姿は溶け去るように消え、代わって彼女は氷の海、南氷洋にいました。ロス海〈大郡〉のミンククジラたちが、〈食堂〉に出かけたり、仲間と談笑したり、子に乳を与えたりして平和そうに過ごしています。ああ、帰ってきたんだわ、私!
リリの胸ビレを引いたアンがクレアを迎えました。
「ああ! リリ! リリッ! 会いたかった!!」
「お母さん、お兄ちゃんが寂しがってるよ」
クレアは困惑した顔で、冷めた表情をした紅い目のわが子を見つめました。
「ねえ、一緒にお兄ちゃんのところへ行こうよ」
「クレア。レックスが逝ってしまった。私たちの大好きだったレックスが……。でも、だれだって結局は逝くんだわ。あなたのジョーイもね。私たちも一緒に逝ったほうがよくはない? どうせ同じことなんだもの、いますぐだって変わりはしないわよ」
クレアは声もなく、口を震わせながらゆっくりと首を横に振りました。
「あら、いやだって言うの? レックスが殺されたのは全部あなたのせいだっていうのに……。じゃあ、いいわ。私があなたの代わりにあの鯨のパートナーに、この子のお母さんになってあげる。さあ、リリ、お父さんやお兄ちゃんに会いに行きましょう」そう言うと、紅目のアンはリリと連れだって泳ぎ去っていきました。
「待って、アン! リリッ!! 行っちゃだめーっ!! そっちには〈沈まぬ岩〉が──」
紅目のモーリスが立ちはだかり、冷厳な口調で言い放ちます。
「新生児の数が多すぎますね。間引かなくては!」
紅目のフィーブルがらせんを描くように舞いながら、遠く狂おしい声で予言の言葉を繰り返します。
──心して聴よ……
生の仮面を被りしものの正体を……
時の終端/宇宙の終末/すべてが落ちこむ虚無/
静かなる暗闇/光なき静寂/魂の帰還/
万物万霊を司る絶対存在
その名、口にするも晴れがましや……
〝死〟と──
どこかにまともなクジラはいないかと〈豊饒の海〉を駆けずりまわった末、ようやく齢を重ねた信望厚いメスクジラがクレアの目に止まりました。彼女ならきっと大丈夫よ──
「おお、マーゴリア! どうか私をお救いください、敬愛する〈来し方の語り手〉!」
マーゴリアは穏やかな紅い目で、若いメスの瞳の奥をじっとのぞきこみました。
「単に生き延びることが尊いのではないぞ、クレアよ。なぜ五頭のクジラは兄弟のために己が命を捧げたか? 誠に尊いのは愛じゃ。やさしさじゃ。母と子の愛情じゃ。仲間同士の友愛じゃ。死をもいとわぬ愛じゃ。愛は死じゃ。それをわしらは尊ばねばならぬ。お主は息子のために死ぬるか? 愛のために死ぬるか?」
クレアは声も出ずに首を振ると、逃げるようにして彼女のそばから離れました。だれか……だれでもいいから、私を助けて!
まもなく白い燐光の海の中にクジラの姿はなくなりました。いったいどれくらいの間泳ぎ続けたでしょうか。もう時間と距離の感覚もなくなったころ、憔悴しきって虚脱状態で漂っていたクレアの前方に、一頭のクジラの影が現れました。ミンクのオスでした。
「レックスッ!!!」
クレアはだれよりも会いたかったそのクジラのそばへ駆け寄りました。
「ああ、レックス! レックス!! お願い、私を助けてちょうだい! みんな、みんな、みんな、寄ってたかって私をいじめるのよ!!」
紅い目のレックスは彼女の耳にそっとささやきかけました。
「クレア、ぼくのところへ来ないか?」
ませたこどもみたいな悪戯っぽい瞳、何気ないふうを装いながらも秘密を隠し持ってでもいるかのようなしゃべり方、ちょっと首をかしげて微笑む仕草は、どこからどこまでレックスそのものでした。クレアはかつて愛したパートナーのやさしさに引きこまれかけましたが、それでも首を振って後退りました。
「行けないわ、私……」
「なぜだい?」
「私、いま死ぬわけにいかないの」
「寂しいことを言うね」紅目のレックスはちょっと悲しげな表情をして言いました。
「ぼくはただ、きみの愛が欲しいだけなのに」
「ああ、レックス! 私もあなたを愛してるわ! あなたの後を追おうとしたことだってあったわよ!! でも、でも──」
葛藤に苦しむクレアに、レックスはじっと穏やかな眼差しを投げかけます。ああ、このまま何もかも投げだして彼のもとへ飛びこんでいけたら、どんなにか幸福だろう!
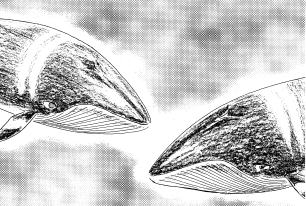 「だめだわ……」
「だめだわ……」うつむいていた顔を振り上げ、彼女は目の前にいる紅目のクジラを仰ぎ見ました。
「あなたを愛してるの。あなたを感じてるの。いまでも! 日差しの温もりに、穏やかに揺れる波に、私をやさしく包みこんでくれる海の水に……。たくさんの生きものたち、あなたにいろいろなことを教えてもらった小さな種族たちの懸命に生きる姿に……。あなたがいとおしんだ幼い生命たちに……。一頭一頭の出会うクジラたちに……。私がともに旅を続けてきた仲間たちに……彼らのユーモアに、聡明さに、勇敢さに……。彼らが無茶ばかりする私を気づかってくれるとき、そんな彼らのやさしさの中に、私はあなたを見るのよ……。あなたが驚きに目を見張った世界、あなたが美しさに心惹かれた世界、悲しみに胸を痛めた世界……あなたと分かち合った空間、あなたとともに過ごした時間、あなたが知ったこと、感じたこと、愛したこと、私と二頭で共有したものを、私はいまでも感じ続けているのよ! あなたを感じていたいの! あなたを愛し続けたいの!
「私を守るために、私を生かすために、あなたは自らの生命を犠牲にして逝ってしまった……。自分一頭だけ図々しく生き残っている資格なんて、私にはないかもしれない……。でも、私が生きている限り、あなたの一部は──私の中に残っている、私の覚えているあなたは、生き続けるわ! 私の生命の続く限り、私はあなたを生かし続けるわ! あなたのことを絶対に忘れないわ! でないと、逝ってしまったあなたは、〈沈まぬ岩〉に屠られていってしまったあなたは、本当に死んでしまうんですもの!!
「なにより、ジョーイは私とあなたの子なのよ! 彼の血の中にあなたの血も脈づいているのよ! あなたの分身なのよ! あなたが感じた世界、あなたが知った世界を、私はジョーイにすべて経験させてあげたいの! 私とあなたが生きたこの海を思う存分泳がせてあげたいの! たくさんの生命に触れさせてあげたいの! 明日病気になって死んでしまうかもしれない。シャチやサメに食べられてしまうかもしれない……。でも、今日をあの子が生きられるように、私は全力で彼を護りぬくわ!! 彼がこの世界に生まれてきてよかったと思えるように、私たちの生命を引き継いでよかったと思えるように……。そして、私とあなたの生命とともに、ジョーイが自分の生命を次の者に受け渡していけるように、生命がずっとずっと続いていくように……。そのために、私は生きる。私は負けないわっ!!!」
レックスのビジョンはぼやけて消えました。
巨大なミュータントクジラの王が口を開きました。〔強情な小娘だ〕
「ジョーイを返してください!」クレアはもはや一片の恐れも抱くことなく化けクジラに向かって要求しました。
「お願いです。ジョーイを、息子を返して!!」
〔ならぬ!〕〈脂の樽殿下〉は断固とした口調で拒絶しました。
〔お主の択る道は二つに一つしかない。新王の乳母となるか、死かだ〕
クレアは負けじと首を振り、毅然とした声で繰り返しました。
「返してください」
〔お主、それほどまでに生きたいか?〕〈殿下〉はさらに低く抑えた声で問いました。
クレアは無言でしたが、顔には生の意志のみがはっきりと表示されていました。
〔世界が滅びんとしているのに、なおも己が生に固執するか! 己が子に拘泥するか! よかろう、お主の意志が本物かどうか確かめてやる〕
ミンク大王は巨大な口を開けて怒りの混じった冷酷な笑みを浮かべました。その恐ろしい笑みの奥で無数の紅色の光がちらつき、彼の口からこぼれ出てきました。対になった小さな紅は団子状に群れ固まり、クレアに向かって接近してきました。紅い目の主はダツでした。銀色の細長い身体をしたその魚は、まるで〈毛なしのアザラシ〉の使う銛のように見えました。ダツはクレアの周囲にわーんと群がり、飛ぶように旋回しだしました。何尾かが彼女のそばを掠めすぎ、鋭く尖った上下のクチバシがさっと赤い糸を引きました。
「痛ッ!!」
〔お主の身体をこれから寸刻みに切り刻んでやる。だが、殺しはせぬ。お主は漸近的に死へと向かうのだ。限りなく死に近づきながら、決して死に至ることなく、倍加する苦痛のみを受け続けるのだ。余の要求を呑めばすぐに解放してやる。死を望むならば、それでもよい。心臓を一突きにして楽にしてやる。いずれを選択するもお主の自由だ。さあ、お主の言葉どおり、生きられるものなら生きてみよ! 生きてみるがよい!!〕
ダツの動きが素早くなり、たちまちクレアの肌に何条もの紅い筋が走りました。
「あっ!」
操られた魚はクレアの体表にほとんど平行に接触して、表皮をえぐっていきます。傷の数はみるみるうちに増えていきました。多量の血が黒い滑らかな皮膚に染み渡ります。神経の一本一本が苛まれるようです。しかし、戦う武器も防御の手段も何一つ持たないか弱いメスのヒゲクジラには、苦痛に身をよじる以外なす術もありませんでした。
〈殿下〉の胸ビレを振る合図とともに、ダツはいったん攻撃をやめました。
〔どうだ、降参する気になったか?〕
「か、返して、くだ、さい……」身体を小刻みに震わせてやっとのことで声を絞り出したクレアの頭の中には、それ以外の返答の言葉は思い浮かびませんでした。
〔まだ言うか!!〕
拷問が再開されました。クレアはいまや、頭から尾の先に至るまで全身の皮膚を寸断されて鮮血にまみれていました。表皮が、皮下脂肪が、筋肉が穿たれ、白い海水と真赤な血液が混じり合います。クレアの意識はフッと遠のきかけました。すでに彼女の目は流れてくる血のために視界が利かなくなっていました。目そのものが無事なのは、無慈悲な責苦の仕上げに最後まで残しておこうというのでしょうか。苦痛の向こう側、紅くにじんだ瞼の裏のスクリーンに、ジョーイの顔がぼんやりと浮かびます。
生きたい!! でも……どうすればいいの!? 私はいったいどうすればいいの!!??